 学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
学園祭のビューティーコンテストがフェミニスト女子学生たちによって占拠された。しかしアイドル女子学生3人によってビューティーコンテストがさらにジャックされてしまう。彼女たちは宣言した。「あらゆる制限を取り払って真の美を競い合う〝ビューチーコンテストオ!〟を開催します!」と。審判に指名されたのは地味で目立たない僕。真の美とは何か、それをジャッジすることなどできるのだろうか・・・。
恐ろしくて艶めかしく、ちょっとユーモラスな『幸福のゾンビ』(金魚屋刊)の作家による待望の新連載小説!
by 金魚屋編集部
七、赫映姫
ふいに訪れた暗闇のなか。
「笑止千万呵々大笑抱腹大笑唖然失笑」
宴もたけなわを迎えつつあったビューチーコンテストオ会場に、上空から嘲笑が安っぽい花吹雪のごとく降り注いだ。
あはははははは、 けひひひひ、 ふははははは、げはげは、 うひゃひゃ、 けらけら、 げひげひ、
けけけけ、 どひゃひゃひゃ、
みょはははにょははは、 ぷっ、 くっ、
うひゃひゃ、 のはははは、 にょはははは。
数知れぬ笑いが重なり合い、ぶつかり合い、エコーを響かせながらキャンパスに溢れかえった。
「な、なんだ」
「これはいったい」
「誰だ、上から目線で俺たちを笑うのは」
そして、学生たちは見た。教員たちも見た。職員たちも見た。近隣住民たちも見た。カラスも見た。ネコも見た。犬も見た。赤ん坊は寝ていた。よそ見していたぼくも、あわてて見た。いったい誰なんだ、いきなりキャンパスを暗がりに連れ込んだ、いや包み込んだのは?
巨大な円盤
が、
上空に浮かんでいた。
金属製の灰皿を裏返しにしたような、わかりやすいUFO。典型的なアダムスキー型だった。ただし、かなり巨大なもので、キャンパス全体がその影のなかに隠れるほどだった。映画『インデペンデンスデイ』に出てきたやつくらいデカかった。
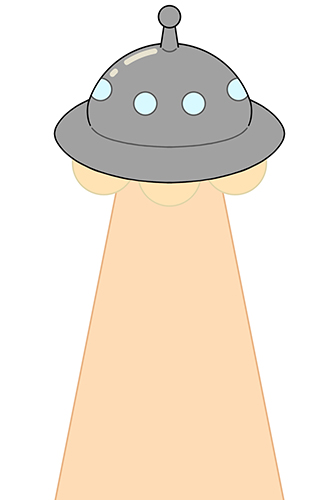
「うわ、こりゃまずい侵略される」
「地球最後の日だ」
「やばっ、やばっ、これゲキやばっす」
誰もがこの世界の終わりを妄想した。
タコのような姿をした宇宙人に地球は征服され、地球人たちは奴隷としてこき使われるようになるのだ、きっとそうだ。そして、これまで水族館の隅でいじけていたタコたち、タコ焼きやの鉄板の上で細切れになって焼かれていたタコたちが大きな顔をして闊歩し始めるのだ。タコたちは、くにゃはあ、くにゃはあと笑うにちがいない。
「てめえらよくもくにゃはあこれまで、俺らをコケにくにゃはあしてくれたなあ、俺たちの悲鳴をくにゃはあくにゃはあ聞きつけて宇宙からの親戚が来てくれたからくにゃ、これで立場は逆転なのさあくにゃはあ。細切れにされてくにゃはあ、小麦粉の玉に埋められる気分をくにゃはあ思い知らせてくれよおぞくにゃっはあ!」
なんてほざくのだ。そうなのだ、きっとそうだ。調子に乗ったタコたちは、最後には「くにゃはあ」じゃなくて、「くにゃっはあ」って笑うのだ。そうなるに決まってる。
いや違うだろ。地球人は餌になるのだよ。ここは巨大な顎を持った昆虫型宇宙人ギガントバグのレストランのための放牧場になるのだよ。アース・ミート、別名ジンニクというやつが輸出される牧場、人間牧場となるのだよ、この星は。産めよ殖やせよ地に満てよ、そして収穫されよと、これからは白昼堂々と無差別交尾が奨励されるだろう、そして生まれたジンニクのこどもたちは大切に放牧され、飼育された後に屠られてパック詰めされて、宇宙のレストランやスーパーへと発送される。ナイフとフォークをもったギガントバグたちが、大口開いてこれを食らう。ああ、なんて未来図なんだぁ! 屠られるのも喰われるのもいやだけど、唯一交尾の解禁だけが喜びとなるわなぁ。そうこの星は乱行の星となるわなぁ! だって俺らはもう家畜なんだから。どうせ殺されて喰われるんだから、ヤラにゃあそんだしなあ。うわあ、そうだよ、きっとそうなっちまうんだよ。
「はいはい、やめてやめて」
上空から根拠のなさ過ぎる憶測に対して水が差された。非常に高性能のスピーカーを装備しているらしく、その声はすべての人の耳にクリアなハイファイ音、そして完璧な日本語アクセントで届けられた。うひゃあ、宇宙人のインテリジェンス、パねえ! なんて思ったのはぼく。
「あのね、行っとくけど、あんたらの星のガキんちょむけ特撮なんかでよくあるみたいな『この緑の星はわれわれがいただくぜ!』とか、いうクッサイせりふ、間違っても言わないから。ありていにいって、ダメだしこの星。オワコンだし、オワッテルし。NGだし、ノーグッドだし。そりゃせいぜい二百年前くらい前まではそれなりによかったよ、でもさ、もうだめじゃん、汚れまくってるじゃん。空気も水もアウトじゃん。放射能もダダ漏れじゃん。まったくさ、今ごろ脱炭素とか言っても遅いし、それで代わりに原発増設とかって頭わいてるの? としか思えんしさ。ますますダメになるだけじゃん。マジでいらねえし、こんな星」
「あ、そうなんですか」
地球は青かった、緑の星、生命の星、水の惑星、・・・美しい星的な地元讃美の発想を真っ向から否定されて、キャンパスに溢れていたローカル宇宙の住人である地球人諸兄は大いに失望した。
「そりゃそうよ。もはやさ、宇宙観光旅行の準指定訪問地からも外される寸前よ、君ら。気づいてないかなぁ。このところUFOの目撃情報激減してるっしょ? あれみんな基本的に観光目的だったわけよ。ギャラクティック・トラベル・カンパニーって大手旅行会社があってね、あっ、ダサイ名前とか思った? でも、これあれだらからね、わかりやすい地球の言葉に置き換えてるだけだからね、ほんとんとこはさ、君らには発音できないし、聞こえもしないかっこいい社名だからさ、そこんとこ勘違いしないでね。
まあ、ちょっと前まではさ、そりゃあ砂漠でレッツ砂遊びとかいってペルー辺りでお絵かきしたりとか、モアイ辺りでレッツ彫刻ぅとかいって石像作ったりとか、おふざけでモノリス置き忘れ遊びとか、畑の作物踏みつけてサークル模様描いたりとか、ちょっと地球人連れ出してチップ埋め込む改造してみたりとか、いろんな遊びしてたもんよ。でも最近は空気悪いしさ、水汚れてるしさ、変なウィルス続々とわいてるしさ、人気ないんだわこの惑星」
なんだか、だいぶげんなりする発言だった。宇宙人にとってこの星はもっと魅力的だと思ってたのに、全然そうじゃなかったなんて。火星人も、バルタン星人ももう来ないってことだもんね。未知との遭遇も起こらなければ、インデペンデンスデイのために戦う必要も無い。「E・T」だって、名台詞は「お・う・ち・か・え・る」じゃなくって、「そ・も・そ・も・い・か・な・い」になっちゃう。
「わたしらもちょっと近くの大マゼラン雲あたりまで来ててさ、ついでにちょこっと地球っていう滅び行く星冷やかして行きますかってな感じでこの辺まできたわけだけどさ、めったくそ幻滅してたところなわけよ。そんななかで、一個所だけ妙な盛り上がり見せてる個所があったからグーグルマップ(うん、そりゃ使うよ。この星じゃ便利だからね)で検索してやって来たわけだけど、大爆笑だわ、まったく。ぜんたいなによこれ。ほら、ここでいまやってる奴」
「え、ビューチーコンテストオですけど」
稗田が空に向かって答えた。
「び、び、び、びゅーてぃー?」
「ええ、そうです、正確にはビューチーですけど」
「あはは」
腹がよじれる音が聞こえるほど痛快な笑い声が響いた。
「宇宙のさ、辺境のさ、ちっぽけなさ、滅びつつあるさ、くそダッさい、みっすぼらしい星のさ、出来損ないのさ、低脳のさ、ブサイクな生命体がさ、おこがましくも厚かましくもビューティー語るんですか? 語っちゃうんですか? 美をうんぬんしようってんですか? うんぬんできるってお思いなんですか? あはははは、いやこりゃ参った。こんなよくできたギャグ、久しぶりだわ。ボケが宇宙スケールだわ、ギャラクティックだわ。なんかもう笑けて、おっかしくって、ハラワタ虫が騒いでたまらんわ。あ、あのねハラワタ虫ってのはね、わたしら進化した生命体の場合、共生体制がばっちりなわけでね、思考活動はノミソ虫、感情活動はエモ虫消化活動はハラワタ虫ってな具合に、まあ地球のとは全然違うけど、虫って呼ばれてる生命体に委託してるわけでね、でもまあこいつらがその笑い上戸っていうか、ほんとお笑い大好きでさ、笑いを主食としているわけでね。そんなこいつらが満腹になるくらいだからね、ほんと。当分食事しなくていいってくらい笑いこけてたから。まあ、それくらい笑えるわけよ、あんたらのやってるチンケなビューティーっつうやつはさ」

「お言葉ですが宇宙のお方!」
おっ、司会者の矜持っつうもんなんだろうか、司会の稗田が食いついた。
「うん、なにかな?」
完全に余裕かました態度。くっそムカつくわぁ。
「えっとですね、こっちもね、ただのビューチーコンテストオじゃないんですよお。従来の、女性蔑視的な性差別、年齢差別、既婚者除外のミスコンという枠組みを超えただけじゃなくてですね、ル・ポールのドラアグクイーン・コンテストみたいに、ジェンダーの区別を乗り越えただけじゃなくてですね、あらゆる規制を外し、万人が自らの誇る美を競い合える場としてですね、装いも新たに新装開店、本日この日の開催となったわけでしてね」
「なに言っちゃってんのよ、笑止笑止」
宇宙人はてんで取り合ってくれなかった。
「つーかさ、おたくらのビューティはさ、そもそもの枠組みが狭小すぎただけじゃないの?」
鋭いツッコミが入った。宇宙的視野から見た場合、なんという狭っ苦しい価値観のコンテストを行っていたかを、思い知らされる一言であった。
「しかしですね、ゴーマンかましてる宇宙のお方」
稗田君それでも引かない、めげない、諦めない。なかなか強い子だわあんた。
「そうした趣旨があらゆる領域にアピールしたということなのでしょうか。神は細部に宿るのことわざ通り、弱小大学にすぎない本学であるにも関わらずですね、実のところ思いもよらぬさまざまな可能性を秘めた存在が正体をひそめて潜伏していたことが、どんどん明るみに出てきたわけなんですよ。神話界はもとより、霊界からも、さらには地獄界からも意表を突く参加者たちが登場してですね、もう見ているだけで世界がぐわらぐわらあって轟音たてながら広がっちまうような、マーベラスきわまりないスペクタクルが展開しているわけでして」
それはまさに事実だった。通常のミスコンではあり得ないスケールというか、人間の幅としても想像を超え過ぎたレベルの参加者たちがステージを賑わせていた。それでも円盤は動じなかった。動かざること円盤のごとし。そんなコトワザがあったような気にさせる、盤石な円盤であった。
「なぁにいってんのぉ。それってさあ、いずれにしても地球中心の発想でしょ。地獄っつったって、地球の奥のどこか、科学的にはマグマしかないはずのどこかからやって来てるわけでしょ。霊界っつうのもさ、あんたら人間の死者たちですでに人口過密状態になってるあの世界のことだよね。それもつまりは、人間と地続き、地球と地続きな世界でしかないよね。神話つったって、地球上のそれぞれの地域固有のローカルな神様たちなんでしょ。田舎くささきわまるよね、それって。
それに比べてわたしらはどうよ? 言ってみりゃ、ほんとの〈外部〉だからね。三次元なんてのもほんの一部としか考えてない、N次元の存在だからわたしら。レベルがもうダンチなわけよ。地球なんてさ、この宇宙からしたら、っていってもさ、わたしらだって宇宙の全体を把握してるわけじゃないんだけどさ、とにかくだだっ広いわけでさ、たとえばあんたらの言葉に恒河沙ってのあるよね。ガンジス川の砂の数ってあれ、無限の比喩的なあれよ。わかりやすくいえばさ、地球なんてその恒河沙の砂粒のひとつにすぎないといってもホメすぎなくらいでさ、実際には恒河沙の数の恒河沙があったとして、つまりあれよ、恒河沙の恒河沙乗ね。その恒河沙の恒河沙乗のなかのぉ、ひとつの恒河沙なかのぉ、砂粒ひとつぅ、ってくらいな存在に過ぎないわけよ、この星なんてえのはさ。わかるかなあ、わっかるかなあ、想像力及ぶかなあ? およばないだろうなあ。
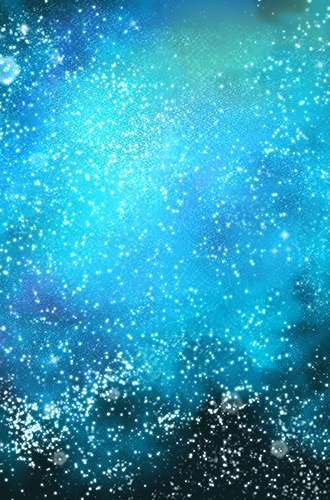
そんな星のさ、エクストリームにローカルなビューティーなんかさ、わたしらから見たらもう、ど田舎で豚たちが美豚コンテストしてるみたいな感じなわけ。あれ、そんなブランドおたくらの星にあったよね。類美豚だっけ? 軽知恵ってのもあったけか。愚痴とか罵罵詈とか、写メルとか、減るメスとかね。
もっといえば、ど田舎の地面の下でその田舎だけに固有な種のアリたちが、美アリコンテスト開いてま~す、みたいな? ね、わかる、笑えるでしょ、それって」
「お言葉ですが!」
なおも食らいつく稗田。偉いぞ、見上げたど根性だぞ、稗田。あとでドトールでコーヒーおごってやる。なんならホットドッグも食っていいぞ。
「そこまで偉そうなことをおっしゃるのであれば、あなたたちも参加されてはいかがでしょうか? そしてきっちり優勝されたならば認めましょう。あなたたちこそが美しいと。どうでしょう?」
あはははははは、 けひひひひ、 ふははははは、げはげは、 うひゃひゃ、 けらけら、 げひげひ、
けけけけ、 どひゃひゃひゃ、
みょはははにょははは、 ぷっ、 くっ、
うひゃひゃ、 のはははは、 にはははは。
ふたたび笑いの紙吹雪が舞い踊った。そう、安っぽい紙吹雪が。
「よかろう!」
余裕綽々の声が答えた。
「そこまでひれ伏したければ、ひれ伏させてやろうではないか。なるほど地球人は、そのレベルにふさわしくひれ伏すのがお好きなようだ。宇宙スケールの美というものがいかなるものなのか、田舎者どもよ、しかと見届けるがよい」
円盤の下部に小さな穴が開いた。いや、実際には穴ではなかった。それはビームの射出口のようだった。
まばゆいビームが照射された。とはいえ、それはSF画によくあるような破壊的なレーザービームではなく、むしろSF映画によくあるようなビーム・ミー・アップ!的な転送光線であるようだった。ビームがステージの中心にまばゆい繭を作った。
「もっとわかりやすくしてさし上げよう」
ご丁寧に円盤から別の光線が重ねて照射された。それはホログラムを作り出すビームのようで、ステージから天に向かって巨大な竹がそそり立った。立体感を伴ったマンモス・バンブーだった。その中心部が居合い切りよろしくスパッと斜めに断ち切られた。ふたたびさっきのまばゆい光がぱあっと噴出し、その光そのものの権化のような眩しい美貌が出現した。
「う、美しい!」
「いや、過ぎるぞ。美し過ぎる」
「まるで魂が吸い取られるような気分だ」
そう、それが誰であるかはもはや疑いようがなかった。
「か、か、かぐや姫だ」
ピンポーン!って感じ。
「ふたたび地球に降臨なさったぞ」
あはははははは、 けひひひひ、 ふははははは、げはげは、 うひゃひゃ、 けらけら、 げひげひ、
けけけけ、 どひゃひゃひゃ、
みょはははにょははは、 ぷっ、 くっ、
うひゃひゃ、 のはははは、 にはははは。
嘲笑が降り注いだ。
「どうだ。参っただろう。完璧なる黄金比。完璧なる肌の艶。完璧なる長き黒髪。完璧なる声音。おまけにわたし脱いでも完璧なんですぅ、見せないけどねぇ。ってわけですわ。
かつて、その美貌によってさんざん地球人どもを魅了し、魂抜きにし、骨抜きにし、翻弄し、無理難題で求婚者たちを死へとおいやって弄んだ挙げ句、さっさと月に帰っていった中世無責任野郎ってわけさ」
「ああ、確か仏の御石の鉢とか」
「蓬莱の玉の枝とか、火鼠の皮衣とか」
「あとは、龍の首の玉、燕の子安貝」
観客席からいろんな声が上がった。アニメにもなってるせいか、みんなの知識もそれなりのものだった。
そうなんですよ、と宇宙船の主は満足げだった。
「そうそう、貴族どもがそんなあり得ない宝を手に入れようとして命を落としたものだったわけよ。それはつまり、手に入らないのはそれらの宝ではなく、かぐや姫本人だったということの喩えだったわけよね。

それもそのはず、彼女は地上の人ではなかったのでありんすよ。いや確かに生命体ではああるんだけど、われわれが開発したAI生物っていうかね、インプットされた情報をまんま体現して三次元化する粘土生命体みたいなやつなわけ。いわば万能ゴーレムやね。それに、われわれの科学の粋を寄せ集めて数値化した、地球人の理想とする美をインプットしたわけよ。一応日本でプロトタイプを実験したから、和風にローカライズはしたわけだけどね。まあ、それ見た地球人どもの騒ぎようったらもうハンパなかったよね。そこらのセレブとかそういった類いの浅はかな感じのとは違ってさ、美を巡るビッグデータの超平均値満たしてる上に、どんな学者も及ばない知識と同時に、どんな野人も及ばないストリートワイズを兼ね備えた万能完璧無双無敵美女だったからね。うわべと中身が比類なく釣り合ってたわけ。それでも、身の程知らずに彼女をものにしようとした愚か者たちは、次々と命を落としたわけ。手に入らないものを手に入れようとしたらそうなるのは仕方ないことだよね。ある意味自業自得ってやつよ。
さあ、いまここにこの二十一世紀仕様にアップデートしたかぐや姫Ver、三・〇をお届けする次第だ。さあ、腰抜かせ、尻餅つけ、あっけに取られろ、おっ魂消ろ、脱魂せよ。愚かな地球人どもよ、これが美だ。争うべくもない絶対の美なのだよ。肯うしかない圧倒的な美なのだよ。ひれ伏すしかない崇高の美なのだよ」
実際そうなった。会場の観客たちは皆、腰を抜かし、あっけに取られ、おっ魂消、脱魂した。いまにもひれ伏す寸前だった。
「どうかわたしと結婚してください!」
汎監視システムで世界中を監視している巨大ネットビジネス・コングロマリットのCEOから即座にぴぴぴぴっと求婚のメッセージが届いた。
「わたしは、年商数百億ドルの富豪です。タックスヘイブンを利用しまくっていますから、税金も払っていません。稼ぎがそのまま収入なのです。そんなわたしは、この地上であなたが欲しいものすべてを提供することが出来ます。さあ、どうぞわたしの豪邸へおいでなさい」
「いいでしょう。もしあなたがあのかわいらしい四次元生物ポンティプパッチャをわたしのために手に入れてくれたなら、わたしは喜んであなたの豪邸に足を踏み入れましょう」
「ポンティプパッチャですと?」
「ええ、ポンティプパッチャです」
「四次元にいるのですね?」
「ええ、四次元生物ですから」
ほぼ同語反復の会話が交わされた。
「御意!」
大富豪は承諾のメッセージを送ってきた。
「わが財団の総力をあげて、そのピンチヒッターを手に入れましょう」
「ポンティプパッチャね」
かぐや姫VER3が訂正した
さっそく富豪は巨費を投じて四次元世界探索に乗り出した。三次元世界では誰も並び立つことができない富を手にした男だった。だから、彼は「この世に金で買えないものはない。いわんや妻をや」と思っていた。しかし、果たして四次元は「この世」なのだろうか? 金によって築かれた彼の力は、四次元世界でも通用するのだろうか。
「さきほど四次元への扉が開いたそうです」
あっと言う間に報告が届いた。金の力は凄いなと誰もが驚いた。不可能とされた四次元への扉すら、金の力で駆り立てれば、人間には開くことが可能なようだった。とはいえ、問題はこれからである。富豪は屈強な部下たちと、私兵たちを引き連れて四次元世界へと消えていったという。
「愚かですこと」
かぐや姫は着物の袖で口を被いながら、ホホホホホと艶やかに笑った。
「わたしはさる大国の長です。権力という意味ではわたしの右に出るものはいないでしょう。あなたの命令とあれば、わたしは核ミサイルの発射ボタンすら気軽にポンと押すでしょう。いや、ポンポンと、ポンポンポポンと押すでしょう。たとえば、どこかの国の犬があなたに吠えかかったとか、別の国の屋台の飯がまずかったとかそんな理由であってもです。あなたを不快にした国を、わたしは一瞬で抹消することができるのです。どうです、わたしの大いなる権力の懐に抱かれてみませんか」
次に現れた求婚者は権力の塊だった。南の海に現れた熱帯性低気圧が、徐々に勢力を増し、ついには超大型台風へと育つように、下層階級から成りあがって最高権力者へと上り詰めた「人類がこれまでに体験したことがないほどの権力」の持ち主だった。彼が近づくと権力特別警報が発令されるほどであった。
本人が近づくと権力による被害を恐れてあたりに人がいなくなってしまうので、今回は3Dホログラムによるヴァーチャルアバターが送り込まれてきた。
しかし、さすがは家具屋の姫、いや、かぐや姫である。いささかも、みじんも、ミジンコほども動じた風はなかった。
「では、お聞きしましょう」
にこやかにアバターの顔を正視した。
「あなたは自分の国にそのミサイルを落とせまして?
じつは、かつてあなたの国に行ったとき、わたしは心ないペットの飼い主のせいで、犬のうんちを踏みました。あの不快な体験はわたしにとって、許しがたいものです。さあ、その国を、つまりはあなたご自身の国を罰してくださいませ」
「うぐぐ」
人類がこれまでに体験したことがないほどの権力の持ち主はうめいた。その似姿であるところのステージの上のアバターもうめいた。
「押したい、そりゃ押したいよ。ポンしたいよ。あなたを不快にさせた国が、わたしの国だというのならば。ただ、問題は、そうした場合わたしの権力もいっしょに消え、いやそれどころかわたし自身も消えてしまうという問題が生じるということなのです。その場合、わたしはあなたへの求婚の根拠を失うばかりか、求婚するはずのわたし自身もいなくなってしまうというジレンマに直面することとなってしまう。押すべきか、押さざるべきか、それが問題だ」
解決不能のジレンマに陥った権力者は、「ポンすべきか、せざるべきか」という悩みに苛まれるポン・ハムレットと化した。姫恋しさと権力惜しさ。姫欲しさと自分惜しさ。二つの感情が低気圧と高気圧のように拮抗し、せめぎあい、押し合いへしあい、どちらの感情も強烈すぎて答えが出せず、核のボタンの前で呻き続けているということだった。
「はははは、いやあ、こいつは参った。並び立つ者なきプレイボーイとして、この地上のあらゆる美女たちを陥落させてきたジゴロな俺だ。わかるよ、数知れない女性と関係してきた俺だからこそわかるよ、あんたは確かに最上級、いや究極の美女だよ。さあ、おいらの閨房へようこそ。めくるめく快楽、果てしない悦楽、無情の愉楽、至上の至楽へとこの俺が誘ってさしあげよう。ハーバード大学で閨房学の博士号を取得し、ニューヨーク、ロンドン、パリ、東京で房中術のセミナーを定期的に開催しているこのおいらさ。独自に開発したアクロバティックな体位、おいらの指を見るだけで昇天する女性もいるというフィンガーテクニック、おいらがしゃべるだけで悶絶する者続出の甘いささやき。人生のすべて、生活のすべてを女性の悦びに奉仕するためだけにささげてきたこのおいら。アイドルグループ、ジゴロ四八手のプロデューサーとしても知られてる。大ヒット曲『ヘヴィー・ローテーション(オン・ザ・ベッド)』は、ほかの星でもヒットしたって聞いてるぜ。さ、さ、さあ、さあ、あ、さあ、ずずずいぃぃぃっと、こちらへ、こちらへぇぇぇぇぇ」
かぐや姫の前にどこでもドア的なものが出現し、そこからカサノバみたいな貴族風の衣裳に身を包んだ男が現れた。
「どうだい? おいらの自伝『わが生涯の物語』に新たな一ページを付け加えようよ」
「この扉の向こうには何があるの?」
「これは、『どこでも閨房』というカサノバの秘密道具のひとつなのさ。ネヤエモンという万能ロボットにもらったんだ。この扉をくぐればいつでも閨房、いつでもベッド、いつでも快楽ってわけ。さあいらっしゃい、かぐやの姫よ、かぐやかなるお姫様よ、かぐやき姫君、かぐわしき姫殿よ!」
つやつやの肌をした男は年齢不詳だった。もしかしたら、ものすごい年齢なのかもしれなかったが、耐えず精を注入してきたせいだろうか、得体のしれない自信とエネルギーを感じさせた。そんな究極のナンパ男を、かぐや姫は値踏みするように見た。
「ふふ、満足させることができるかしら、このわたしを」
「もちろんだとも。宇宙の果てまでお連れしましょうぞ」
手を取られるままにかぐや姫は扉の向こうに消えた、と思ったら秒で戻ってきた。いや実際、扉の向こうに一瞬でもいたのかといぶかしむくらい早かった。
「口ほどにもないお方でしたわ。一瞬でミイラになってしまわれました」
そう言ってふたたびかぐや姫は、着物の袖で口元を被って、ホホホホホと笑った。
会場中の観客の背筋にぞくりと寒気が走った。
それきり、もう誰もかぐや姫に近づこうとする者はいなかった。惹かれるのは確か、拝みたいほどに美しいのは確か、ただ、あまりにも神々しかった。あまりにもこの世離れした美しさだった。
「さて、どうかな諸君、これでおわかりだろう。素直に負けをみとめたらどうだろう」
上空の円盤から声が聞こえてきた。
「これをしのぐ美はないということ。すなわち誰にも届くことのかなわぬ美。そういうことだ。そういえば、この国には高嶺の花という言葉があるが、まさにそれ。しかもかぐや姫はただの高嶺ではない。もはや見えないほどの高見、届き得ない高見にそれは君臨している。いったい誰がそこへと到達することができるだろう。この到達不能性こそが美なのだ。絶対に触れ得ぬもの、届き得ぬもの、憧れ焦がれて焼け死ぬほどの存在、それが美なのだということ、とくと納得めされたか!」
「いいえ、認めないわ!」
力強い声が響いた。
(第07回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『ビューチーコンテストオ!』は毎月13日にアップされます。
■遠藤徹の本■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


