
なにも語らずなにも願わずわれとわが貧しき夢と君のほかには
寂寞を友とし生きるからまず空を凝視することより始む
断念の後は笑って生きるのだ睦月如月弥生三月
かの女探してくれよ新宿の空に揚げたや広告気球
われがピエロかピエロがわれか分からなくなりたる頃にさようならを言う
月光のした照る庭の草叢に俺に似た児が俯いている
星抱き眠らんものをなにもなしカスタネットと月光のほか
(『中也断章』昭和五十八年[一九八三年]十二月刊)
中原中也の実人生に沿って歌を詠んでいるが、『中也断章』は福島の短歌的抒情が最も鮮やかに表現された歌集である。現代作家は政治を含む社会の変化を作品で表現しなければならない。しかしそれは短歌芸術の〝目的〟ではない。「なにも語らずなにも願わずわれとわが貧しき夢と君のほかには」にあるように、短歌芸術の根は、残酷な現実の猛威に吹き曝された後に現れる〝夢〟を表現することにある。「寂寞を友」としながら「笑って生きる」ような人間の弱さと強さが人間存在の実存に即した抒情である。

福島泰樹著『中原中也の鎌倉』冬花社刊 平成二十六年(二〇一四年)
生きている限り人間は、滑稽で残酷であり、孤独だが生の源泉ともなり得る甘美な抒情から逃れられない。絶望の淵でふと湧き出る甘美な抒情が生の証であり、糧なのだ。この抒情が幾たびもの大きな社会変化にも関わらず、千五百年もの長きに渡って短歌を生き延びさせてきた。それは短歌だけでなく、妄執にまみれた幽鬼が登場するお能にも見られる。「星抱き眠らんものをなにもなしカスタネットと月光のほか」は、より良き社会、より良き精神を希求しながら、現実世界で人間が受け取れるのは至高の何事かが発する微かな光だけだという福島の思想を表している。人間は手にした小さなカスタネットで自らを鼓舞してゆくほかないのである。
賢治幻想Ⅱ
この春をもって台東区立坂本小学校は廃校となる。創立は明治三十二年四月一日。
壱
焼け野原にバラックが建ち風が吹きわれらは勁く集う学舎
賢治との出会いを問わばこれやこの闇市、痩せた父のゲートル
空襲で焼け出された家族眠る 酸っぱい花梨も熟れてゆく夜か
うら若き母なら父よ 春暁のあなうら若き母なら父よ
爛漫の春をうたわんいのちなり一年二組つつがなきなり
兄が唄う「風の又三郎の歌」瓦礫に零れ消えゆく夕陽
(『賢治幻想』平成八年[一九九六年]十月刊)
『中也断章』で掴んだ作歌法を、福島は次々に新たな対象に援用していった。『続 中也断唱〔坊や〕』(昭和六十一年[一九八六年]十月)や『蒼天 美空ひばり』(六十四年[八九年]十月)、『賢治幻想』(平成八年[一九九六年])などがある。ただ福島は『中也断章』の憑依歌法を繰り返したわけではない。孤独な個の実存を支える抒情原理まで精神を下降させると、また猥雑な現実世界に戻って来る。それができるのは、死者の変わることのない精神を基盤に据えているからである。福島が歌を詠むための依り代として死者――特に中原や賢治といった夭折した文学者を選んだのは当然である。
中原は明治四十年(一九〇七年)に生まれ、昭和十二年(一九三七年)年に三十歳で没した。賢治は明治二十九年(一八九六年)生まれで昭和八年(一九三三年)に三十七歳で夭折している。七十歳、八十歳までの長命なら、戦後の一九七〇年代、八〇年代まで生きたはずである。その間には太平洋戦争と終戦があり、戦後社会の大きな動揺があった。満州事変を主導した陸軍軍人・石原莞爾と同じ法華経教団である国柱会の熱心な信者だった賢治が、戦前・戦中の国粋主義風潮にまったく背を向けて、無傷のままいられたとは考えにくい。血の気の多かった中原も同様である。彼らは大正デモクラシーの時代に精神の羽根を伸ばし、日本が狂信的な皇国主義社会に突入する前に亡くなった。夭折もその時期も彼らが望んだわけではない偶然である。しかし純なまま途切れた夭折者の精神は、その後を生きる文学者の指標となり得る。特に作家がかつての仲間と世界を信じ切れない時代にはそうである。
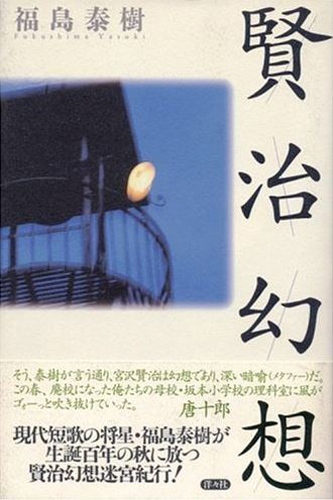
福島泰樹著『賢治幻想』洋々社刊 平成八年(一九九六年)
福島は反体制・反権力的な独立不羈の戦後精神を守り抜こうとする詩人である。それを支えるのは取り返しようもなく不変・普遍化してしまった死者の純な精神である。死者の精神を共有することで「私」と「他者」の連帯――つまり「われわれ」の精神は回復し得る。いつの時代でも同時代を巡る作家の精神は複雑である。その記述は芳香を放ち、時に腐臭となることもある。しかし果実に種があるように、文学でも核のない生成はあり得ない。核となる精神を持たない作家の作品は、どんなに詳細に現実や状況を描こうともなんの香りも放たない空虚である。
七月二十四日快晴。朝、友川かずきからTEL、「たこさんが死にました。小田原の警察に遺体がありますので、これから行きます」、悲しい声だ。たこさんに宜しくと言おうとしたが電話はきれてしまった。
御飯三膳たべているのださびしくば たこ八郎のいない夕暮
飲んだくれしどろもどろの人生だい ましろき骨となりて帰宅す
*
八月二十五日夜、展転社柚原正敬君来る。宮澤賢治についてなにか語れと言う。
「雨ニモマケズ」にふれて、たこ八郎は現代の宮澤沢賢治だと語ってしまう。そ
ういえば、盛岡中学時代の学帽をかぶった賢治の顔は、たこ八郎と瓜二つだ。
欲ハナク決シテ瞋ラズ ひょうひょうといつもの暗い路次帰りゆく
一日ニ玄米四合味噌野菜酎ハイあればたのしきものを
*
たこ八郎を通して眺めると、たこ八郎と宮澤賢治、たこ八郎と中原中也。
たこ八郎を通して眺めると、三人共によく似ている。
なぜか中也とたこ八郎が肩組んで百人町を闊歩しておる
赤ん坊の中原中也とたこ八郎 泣き悲しみを播き散らすのだ
(『妖精伝』昭和六十一年[一九八六年]七月刊)
福島の少年時代はボクシング全盛期で、毎日のようにボクシング中継がテレビ放送されていた。子どもの頃からのボクシングファンだったわけだが、昭和五十六年(一九八一年)、三十八歳の時に意を決して日東拳に入門した。トレーニングを続けるうちにプロボクサーたちとの交流が始まった。ファイティング原田やたこ八郎といった往年の名選手とも知り合うことができた。
斎藤清作ことたこ八郎はファイティング原田と同門で、フライ級東日本新人王準決勝で原田と同門対決することになり、ジムの命令で試合を放棄した。原田はその後フライ級世界王者になったが、たこは日本フライ級チャンピオンを頂点として引退した。プロボクサーになる前から左目がほとんど見えず(プロテストは視力表を丸暗記して誤魔化した)、プロになってからは相手に打たせて疲れたところを反撃するというスタイルが祟り、パンチドランカーになってしまったのだった。ボクサー引退後、たこは由利徹に弟子入りしてコメディアンになった。テレビや映画で売れっ子になったが、相変わらず物がほとんどない安アパートに住み、質素な生活を続けた。昭和六十年(一九八五年)、真鶴の海水浴場で酔って海に入り溺死した。四十五歳だった。『妖精伝』はたこ八郎の追悼歌集である。

人気者になっても奢らず飾らず、飄々と生きたたこ八郎の姿を多くの人が証言している。福島はそのようなたこに、中原や賢治と通底する精神を見出した。ただ『中也断章』(昭和五十八年[一九八三年])を書いて以降、福島の歌集には以前にも増して散文が併録されるようになる。歌論ではないエッセイの著作も増える。短歌は人間の最も純な抒情を表現するのにふさわしい形式である。しかし恥や挫折や失意にまみれた人間の生の全体を、短歌だけで表現することはできない。コップから水が溢れるように、短歌を核とした福島のエクリチュールが散文として溢れ出していったのだ。それが福島のライフワークである「短歌絶叫」の原理にもなっている。
「短歌絶叫」はその言葉から想像されるような絶叫パフォーマンスではない。福島はその独特の低い声で、死者たちの錯綜する妄念を露わにするように散文の地の文を朗読してゆく。最後に朗読される短歌は死者たちの妄念を浄化する一筋の光のようなものだ。それは古来からある詞書と和歌の構成にぴたりと一致している。短歌絶叫はその総体として一つの物語であり、日本文学の基層である短歌の力を感じさせる総合芸術である。
敗れざる者死すなかれごうごうと時代の風が吹き過ぎゆけり
壮大な零といわんも相集う熱き稲穂の喧嘩友達
なにを時代におもねる必要どこにある人間は死ぬその真実を
(『さらばわが友』一九九〇年十二月刊)
肉体は襤褸となるも精神の孤立を叫び開きし眼
吹雪吹雪吹雪けば痛きはらわたのけざむき朝の夢より醒めつ
目を瞑ればガードの上を燃えてゆく省線電車われ生れにしを
(『黒時雨の歌』一九九五年二月刊)
この春も闌けて桜花は吹雪けども水は流れて還ることなし
ならばいざ溢れる水のあふあふの天地開闢宣言をせよ
愉快だな世界は一つであるものか飢えて殺してくたばろうとも
(『茫漠山日誌』一九九九年六月刊)
福島は七〇年代に現れた前衛歌人の一人である。しかしその表現の本質は、新たな表現方法(文体)を創出するような前衛性にはない。むしろ福島の前衛は後ろ向きだ。短歌の基層に届くことが彼の前衛である。福島の短歌は文語体で表現される。この書法の選択は意図的なものだ。現代は必ず過去の短歌文学の根にまで到達していなければならないからである。福島短歌の骨格は口語だが、表現は短歌の歴史を遡ることができる文語体なのだ。この詩人の精神は、口語短歌の時代でもいささかも動揺することがないだろう。(了)
鶴山裕司
* 写真は二〇一六年八月十日の吉祥寺曼荼羅における福島泰樹「短歌絶叫コンサート」のスナップ(撮影・鶴山)
■ 福島短歌絶叫は毎月10日に吉祥寺曼荼羅で開催されます ■
■ 福島泰樹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

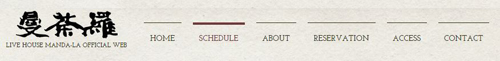
![遥かなる友へ~「福島泰樹短歌絶叫コンサート」総集編 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51etcHYqhTL._SX250_.jpg)
