
福島泰樹の短歌は、現代短歌にとって喉元に刺さった棘のようなものなのではないかと思う。福島は一九七〇年の安保闘争の時代に歌壇に現れた。そのため左翼系の詩人だと思われがちだが、あの時代、創作者を含む多くの人々が左傾思想を持ち行動したのだ。そこには個人の思想信条を超えた大きな時代のうねりがあった。
昭和二十年八月十五日に日本は太平洋戦争に敗戦した。祖国が敗れたことは激しいショックと不安を国民にもたらしたが、終わってみれば戦争は、集団催眠にかけられたような悪夢だった。冷静になれば竹槍でB29に勝てると考えた方がどうかしている。戦前の皇国主義に代わり、国民は大きな期待を持って戦後民主主義を受け入れたわけだが、誰の胸の中にも〝なぜあんなことが?〟という疑問は残った。また終戦を境に国民が総入れ替えになるはずもなく、政治指導者はもちろん、大政翼賛会などで戦争協力した文化人、それに少年・少女として日本の勝利を祈った子どもたちもまた、そのまま戦後の民主主義社会を生きることになった。
杓子定規に言えば、厳しく〝戦争責任〟を問われたのは一部の政治家たちだけである。吉本隆明は初代全学連委員長だった武井昭夫と共同で『文学者の戦争責任』を書いたが、文化人に対する追究はその後大きな盛り上がりを見せなかった。彼らは戦意昂揚のための文学や絵画を制作したが、明治維新以降の長い時間をかけて近代日本に蓄積した、巨大な歪みに巻き込まれただけだとも言える。戦後には「一億総懺悔」という言葉が流行った。「負けるわけないよね」という一般市民や子どもたちの声が戦争終結を遅らせ、歓呼をもって多くの若者を戦地に送り出したのも確かである。ほんの少し前に自ら発してしまった言葉は、単に「政治家たちに騙されたから」ではすまない重いものだった。
昭和二十年代後半には、一度は戦犯とされた政治家や財界人が公職復帰し始めた。それは文学の世界でも同じだった。多くの文学者は戦争責任を痛感していたが、なぜあんな馬鹿げた事態になったのかを理路整然と説明できる者はいなかった。彼らは説明不可能な〝なぜ?〟を封印したまま、戦後の精神復興のために尽力し始めた。歌壇・俳壇では斎藤茂吉主宰「アララギ」や高濱虚子主宰「ホトトギス」が自由な表現に飢えた人々の支持を集め、またたく間に戦前を凌ぐ大結社に成長していった。従軍していた文学者も続々と帰還してきた。彼らは戦争被害者であり、加害者でもあった。また何よりも〝生死の境を見た〟彼らの肉体と精神は強かった。いつの時代でも優れた人材は限られている。戦後文学はまず、戦前から活躍していた著名文学者たちと、戦中にすでに大人になっていた文学者たちによって始まったのである。
言うまでもないことだが、六〇年安保の中心となったのは学生たちである。一九六〇年に二十歳として、彼らは戦時中はまだ子どもだった。無邪気だったとはいえ、その多くは皇国少年少女だった。彼らが物心ついたとき、新たな、だが旧態依然たる戦後システムはほぼできあっていた。時の首相は元A級戦犯の岸信介であり、文学の世界でも戦前からの大物と壮年期を迎えた従軍派文学者たちが旺盛に活動し始めていた。寺山修司が演劇人として、子供心には煌びやかな狂乱の祝祭のように見えた戦争にノスタルジーを抱きながら、一世代上の従軍派文学者たちに対しては「戦争に行ったのがそんなに偉いのかよ」といった激しい反発を感じていたように、六〇年代の若者たちの心は屈折していた。六〇年、七〇年安保はもちろん政治運動だが、それは戦後第一世代の若者たちのアイデンティティ確立のための闘争でもあった。
安保闘争は様々に総括できるが、戦前・戦中に大人だった人々が作り出した現体制を打破しようとする運動だったのは確かである。プロの政治家でも革命家でもなかった学生たちに破壊後の明確なヴィジョンがあったとは言えず、何よりもまず体制打破が優先された運動だった。その意味で安保闘争は第一次大戦後にヨーロッパで起こったダダイズムに似ていた。終戦によって戦前の体制が崩壊したことは、日本社会の全てが一度白紙還元されたことを意味するはずだった。しかし現実は違っていた。相も変わらぬ戦前からの諸勢力がしぶとく生き延びていた。戦前の皇国主義に積極的に荷担したわけではないが、命を賭して国のために戦ったわけでもない戦後の若者たちは、自らの肉体と精神を賭けて戦後のゼロ地点を模索したのである。
樽見、君はいまどうしているのだ。六六年二月、ぼくたちがかかげた狼煙は、日本のカルチェ・ラタンの先がけとして、今日へと問いつづけているのではないのか。「70年国会で会おう!」とは、活動家、樽見が最後にくれた消息不明の手紙だ。
一月
樽見、君の肩に霜ふれ 眠らざる視界はるけく火群ゆらぐを
あれはなにあれは綺羅星 泊り込む野営・旗棹しか手にもたぬ
バリケード築くこの手は凍てたるを 机に睡る卑猥なビーナス
憩はむに椅子なし窓も塞ぐゆえ 騒立つ指の一〇の凍傷
(『バリケード・一九六六年二月』昭和四十四年[一九六九年]十月刊)
昭和十八年(一九四三年)に東京で生まれた福島は、六〇年安保闘争を十七歳の高校生の時に見た。一浪して早稲田大学に入学したのは三十七年(六二年)のことである。七〇年の日米安全保障条約自動延長阻止に向けて再び学生運動が盛り上がる中、早稲田大学では学費値上げなどに反対する早大闘争が行われていた。福島も闘争に参加した。そのかたわら早稲田短歌会に所属して旺盛に歌を詠んでいた。闘争のために意図的に一年留年した後、四十三年(六八年)四月に僧侶になるために仏教系の学校に入学した。処女歌集『バリケード・一九六六年二月』は仏教学校在学中にまとめられた。早稲田短歌会の佐佐木幸綱が跋を書き、三枝昂之が解説を執筆している。版元の世話をしたのは馬場あき子である。福島自筆の年譜には「ロマンがあるうちに刊行しておこうという想いに駆られ、尼崎にて第一歌集を纏める」とある。
一九六〇年代から七〇年代に刊行された歌集の中で、『バリケード・一九六六年二月』は最も特異な作品集の一つだろう。前衛であっても歌人は歌詠みであり、特に当時はなんらかの〝雅〟を歌集に付加するのが常だった。しかし福島の処女歌集のタイトルは散文的だ。そのルポルタージュ的表題は、作家にとって短歌は目的ではなく、手段なのではないかと読者に思わせる。実際、六〇年から七〇年の安保闘争の時代、今では忘れ去られてしまった膨大な数の反体制詩(社会詩)が書かれた。それは詩の形を取った政治思想表明のための道具だった。そのような詩人たちの多くは政治の季節が過ぎると詩から離れていった。福島の表題にはそんな危うさがある。だがこの危うさは、短歌に政治的主張という夾雑物が紛れ込んで生じたものではない。

『バリケード・一九六六年二月』は級友だった樽見某への呼びかけで始まる。早大闘争を最も真摯に闘っていた活動家の一人だったようだ。しかし「樽見、君はいまどうしているのだ」とあるように、歌集刊行の六九年にはすでに音信不通になっていた。樽見は「70年国会で会おう!」という手紙を寄こしたが、七〇年安保の国会前闘争には姿を現さなかったのではなかろうか。
ただ福島は樽見を責めていない。「樽見、君の肩に霜ふれ 眠らざる視界はるけく火群ゆらぐを」とあるように、青年は肩に霜が降るまで凍えながら立ち尽くしている。視界を遮るものはなく、闘争のシンボルである炎は、身体を温めてくれるはずの火群は遠くに揺らいでいるばかりだ。樽見は同時代の青年の象徴であり、福島自身の姿だろう。福島は自筆年譜で七〇年安保のために用意したヘルメットに、「根源的敗北を敗北し続けよ!」と書き殴ったと回想している。彼は政治闘争としての安保が敗北に終わることを予感していた。
処女作品集には作家の資質の生地が鮮やかに表れる。特に優れた作家の場合はそうだ。『バリケード・一九六六年二月』は口語の詞書と文語の短歌から構成される。学生時代が終われば誰もが生活のために社会に溶け込み、味気ない日常を送らねばならないことは目に見えている。そのような散文的日常は闘争の最中にも流れていたはずなのだ。にもかかわらず青年たちは、より良き自己と、より良い社会のヴィジョンをつかのま夢見た。福島の場合、それが短歌へと言語化されている。七〇年安保を目前にして、福島はすでにその弔歌を詠んでいるのだと言っていい。
また短歌以外に散文を含むことは、福島が歌を頂点としながらも、その周囲に溢れ出す情念や思想を抱えた作家だということを示している。誰が考えても学生の主張通りに政府や大学が動くはずはない。だから問題の本質は、必ずしも学生運動の勝敗にはなかった。社会・文化領域ともに戦前・戦中世代が中心とならざるを得ない社会で、戦後世代がどのような精神を獲得できるのかということである。その意味で『バリケード』は、政治的に敗北してもなんら変わらない全共闘世代の精神の砦の意味でもある。
君黙しわれは下向く冬の旅 未完成ならわれシューベルト
三月のさくら 四月の水仙も咲くなよ永遠の越冬者たれ
二日酔いの無念極まるぼくのためにもっと電車よ まじめに走れ
(『バリケード・一九六六年二月』昭和四十四年[一九六九年]十月刊)
ぼうぼうと塔けぶるかな一月のついに立たざる漆黒の旗
切口をさらす刺身に箸刺せばどっとあふれる涙誰がため
死に至らぬ絶望それがおれたちの生活 酒場の勘定払う
(『エチカ・一九六九年以降』昭和四十七年[一九七二年]十月刊)
福島の歌人としての思想は第二詩集『エチカ・一九六九年以降』で出揃っている。『エチカ』は哲学者スピノザの主著の題名だが、「倫理」という意味である。福島は後記で「歌は志であり、道であろう。更に私はエチカという一語を付け加える。(中略)自らを厳しく律してゆかなければなるまい。倫理学として私は歌を選んだのだ。ふかぶかとおのれの根に降りたら、そこぶかく情念の火を揺さぶりつづけなければなるまい」と書いている。
後に『もっと電車よ、まじめに走れ――福島泰樹 わが短歌史』というエセー集をまとめていているように、処女歌集『バリケード・一九六六年二月』が福島の原点である。政治運動としての安保闘争は敗北に終わった。しかしそこに加わった青年たちの精神が、既存システムを破壊した荒野にまで達していなければ運動自体の意味が霧散してしまう。『永遠の越冬者たれ』とはそういうことだ。全共闘世代は闘争の代償としての〝エチカ=倫理〟を負っている。だがあくまでそれを貫き通そうとすれば、人は社会的敗者になってしまうかもしれない。進むべき道は既存のレールの上にはないからである。

福島の精神は「死に至らぬ絶望それがおれたちの生活 酒場の勘定払う」といった歌によく表われている。一首だけの絶唱なら高揚した青年の口からふと溢れ出すこともあるだろう。六〇年安保の最中に自死した岸上大作は幸福なのだ。しかし福島は闘争の後に「死に至らぬ絶望」がやってくることを知っていた。しかしそれが原点だとしても、人はいつまでも寒々とした精神の荒野に佇み続けることはできない。〝転向〟の誘惑を拒否するなら絶望を深め、どうしても消し去れない炎を希望に変えるほかない。
帰り来て夕飯を食うそれだけのことに費やす生き様と知れ
孤独にてひとりの熱き砂浜を穴掘っておる生きろ生きろと
(『晩秋挽歌』昭和四十九年[一九七四年]十一月刊)
築けわが観念の城現実の砦 激して杭打ちしかな
春や春すでに別れる人もなし青柳の糸かぜに乱る
(『転調哀傷歌』昭和五十一年[一九七六年]六月刊)
色変えてまた色変えて生きなむとすよ紫陽花の真藍の川風
潔くわが心境を述べるならあかねさす夜ぬばたまの昼
(『風に献ず 自刃せる村上一郎氏に』昭和五十一年[一九七六年]七月刊)
仏教学校を卒業すると、福島は住職として静岡県沼津市にある山中の寺に赴任した。七〇年安保闘争真っ盛りの昭和四十五年(一九七〇年)十一月のことである。下谷の住職として東京に戻ってくるのは八年後の五十二年(七七年)のことだ。二十七歳から三十四歳にあたる。福島は自らの人生と時代状況を短歌で直截に表現する詩人だが、青春を賭けた政治闘争の舞台であった東京を離れて田舎の住職として逼塞する日々を、「帰り来て夕飯を食うそれだけのことに費やす生き様と知れ」と表現している。また内に秘めた精神を「築けわが観念の城現実の砦 激して杭打ちしかな」と詠んでいる。一九七〇年代は多くの作家にとって、自らの表現欲求の本質を問い直される時期だった。(中編に続く)
鶴山裕司
* 写真は二〇一六年八月十日の吉祥寺曼荼羅における福島泰樹「短歌絶叫コンサート」のスナップ(撮影・鶴山)
■ 福島短歌絶叫は毎月10日に吉祥寺曼荼羅で開催されます ■
■ 福島泰樹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

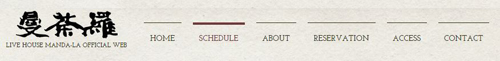
![遥かなる友へ~「福島泰樹短歌絶叫コンサート」総集編 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51etcHYqhTL._SX250_.jpg)
