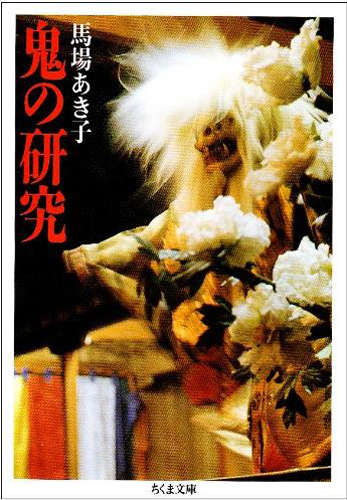
人間の生と人類の歴史には類似点がある。だからこそユダヤ、キリスト、イスラームといったセム一神教は人類の始まりと終末を描いた聖典を創出したわけだ。人類の歴史に終わりがあるかどうかは別として、その始まりがあり、人間の幼年期、思春期、青年期、壮年期になぞらえることができる期間があるのは確かである。またこの〝歴史〟という抽象思考は、人類だけが手にすることになった言葉――特に書き文字によってもたらされている。
書き文字には始まりと終わりがある。アイヌを始めとする無文字文化民族の神話歌謡が循環的世界観を持つのに対し、書き文字文化民族の神話は直線的である。世界開闢から民族の歴史が物語的に解き明かされてゆく。神話だけではない。『万葉集』の長歌と反歌は音韻と掛詞を多用した歌謡が書き文字の浸透によって、一首の独立短歌(結節点)へと言語的に昇華してゆく過程を鮮やかに示している。この始まりと終わりという書き文字概念は、やがて書物という形態を生み出す。始まりと終わりのページを持つ書物は書き文字思想の具現化である。一つの世界観は、一冊の書物にまとめられることで表現される。あるいはある世界観を一冊の書物に封じ込めることによって、人は初めて新たな世界観(認識)に踏み出してゆけるのである。
日本文学で人間の幼年期になぞらえられるのは、記紀(『古事記』『日本書紀』)から『万葉集』成立くらいまでの古代だろう。思春期は『古今集』や『源氏物語』が成立する平安中期頃まで、青年期は『新古今集』成立あたりの平安末期から江戸初期頃、壮年期は幕末くらいまでということになるかもしれない。言うまでもなく幕末には明治維新が起こる。それは日本が初めて経験する未曾有の大転換だった。有史以来、日本は中国に真っ直ぐ顔を向けてきた。文字はもちろん政治・経済・文化に至るまで、一貫して中国文化を受け入れてきたのである。それが明治維新を境に欧米に変わる。千五百年近く続いた文化規範が中国から欧米文化に変わったのである。それは新たな幼年期の始まりとでも呼べる時期だった。夏目漱石らの明治の文豪たちが、古典文学とは別に、日本文学における特権的な位置を占めているのはそのためである。彼らが維新から始まる現代日本文学の基礎を作った。
ただ明治の文豪たちは何もない所から現代文学の基礎を作り上げたわけではない。欧米から怒濤のように流入する様々な思想や文学形式を受け入れながら、過去の日本文学を新たな文化規範の下に再編成したのである。この日本文化の再編は様々な角度から分析・検討することができる。大別すれば新たな欧米文化を中心に日本文学の変容を検討する方法と、欧米文化の流入によっても変わることのない、日本文化の基層を検討する方法がある。
文学を形式と内容にはっきり分類することはできないが、神(特権的作家主体=近代的自我意識)を頂点とする欧米文化の構造が、小説はもちろん、俳句や短歌といった伝統文学をも刷新したのは確かである。しかし強固な自我意識を中心とした文学構造は受容できても、日本文化には欧米のような神的概念が存在しない。そして現在の、二十世紀以降の文化的普遍者とでも呼ぶべき東西均一の自我意識文学の地平の中で、最も日本文学らしい特質を形成しているのは欧米的な神による救済のない無神論的風土である。この風土は文学のみならず、日本人全般の精神風土として存在している。
この日本的精神風土は、醜いと呼べるほど肥大化した自我意識を中心に据えながら、決して救いの訪れない現代の私小説に至るまで表現されている。私小説が日本独自の小説形態だと言われているのは周知の通りである。その原初を辿ればわたしたちは日本文学の古典に行き着くだろう。記紀歌謡や『万葉集』はもちろん、仏教思想の影響が濃いが、よく読めば『古今集』や『源氏物語』にも無神論的風土は表現されている。しかし日本的精神風土が最も鮮やかにその姿を現すのは中世に入ってからである。特に能楽は、それまでの日本文学のエッセンスを集約し、一つの基盤的な型にまで昇華した芸術である。
言うまでもなく能楽は純粋な文学――つまり紙に文字で書かれた完結したテキストではない。舞台芸術である。しかし可変的な舞台芸術だからこそ、日本的精神風土が最も端的に表現されている。能には本質的に救いがない。どうしても解消できない現世的苦悩と妄執をひたすら描いている。能の厳格な様式は、この妄執を的確に表現するために存在する。不定形に溢れ出しそうになる妄執を様式によって封じ込めているのである。また厳格な能の様式は、内部的には蠕動し続けている。使用する能面や台詞を少し変えるだけで、同じ演目でも解釈が多様化する。それは能の主題である妄執が無限に多面的であることを示している。
明治維新以降、多くの文学者が欧米的な知を基盤として日本の古典文学の再読に挑んだ。ただその視線は記紀から『新古今』に至る、古代と王朝文学に向かいがちだった。平仮名表記を含め、この時代に日本文学の基礎が形作られたのは確かである。しかし現在まで続く日本文学の原点は、仏教的救済思想が大きく揺らぐ中世室町初期――特に能楽によって成立している。能楽を的確に理解するためにはテキストの読解だけでは足りない。実践を含めた舞台芸術全体の理解が求められる。そのような困難に挑んだ文学者もまた大勢いた。ただ能楽をテキストと舞台芸術の両面から、ほぼ完全に読み解いた最初の文学者は馬場あき子だろう。能楽が極めて日本的な矛盾の止揚芸術だということを明らかにしたのである。
〈鬼とは何か〉という命題は、さかのぼるにしたがいたいへんむずかしく、民俗学的な把握にも未開の部分を残している。「鬼ハ帰ナリ」と説明された中国の鬼は、死者の魂の帰ってきた形と考えられているが、この〈鬼〉の字を〈おに〉と訓じたとき、中国の〈鬼〉と日本の〈おに〉の微妙な混淆がはじまったと考えられる。(中略)
以上のような、鬼の原像追及のなかに民俗学の一分野を見ることは、今日ではすでに常識となったことであるが、これにたいして、日本の鬼が土俗的束縛を脱し、その哲学を付与されたのは、中世において鬼女〈般若〉が創造されたことをもってはじめとしてよい、と考える。
〈般若〉とはもちろん能の鬼女で、それは中世の鬼の中でももっとも鬼らしい鬼である。なぜなら、三従の美徳に生きるはずの中世の女が、鬼となるということのなかに、もっとも弱く、もっとも複雑に屈折せざるを得なかった時代の心や、苦悶の表情をよみとることができるからである。(中略)
世阿弥は〈鬼の能〉にふれて、「形は鬼なれども、心は人なるがゆへに」という一風を想定している。私が〈鬼〉とよばれたものの無残について述べようと思うのも、このような人間的な心を捨てかねて持つ鬼にたいする心寄せからである。
(馬場あき子『鬼の研究』昭和四十六年[一九七一年])
初期評論集『鬼の研究』には馬場の思想が端的に表現されている。「鬼」は言うまでもなく中国で発明された文字である。世界初の漢字辞典である許慎の『説文解字』(永元十二年[西暦一〇〇年])によれば、「鬼」字は「鬼頭」をかぶった「人」の象形文字である。時代は下るが清朝の学者朱駿声の『説文通訓定声』には、「人帰スルトコロ鬼トナス」と書かれている。「いずれにしても「鬼」字を解けば、それは招魂によって帰ってくる死者の魂であることは明らかである」(馬場)。古代中国では死者を呼び戻すための招魂の祭祀が行われていて、シャーマンなどが鬼頭を頭にかぶって死者を演じていた。死者を擬く人の姿が「鬼」字となり、転じて死者をも「鬼」と呼ぶようになった。
この「死者の魂の帰ってきた形」であり「死者」そのものを指した中国の「鬼」字が、いつ頃から日本で使われ始めたのか、また古代中国では「シ」音だが、それがいつ頃から日本で「おに」と訓読みされ始めたのはか正確にはわからない。ただ「鬼」字に次第に中国とは違う意味が付与されていったのは確かである。折口信夫はよるべない魂を〈もの〉と呼んだが、幕末の考証学者・狩谷棭斎は折口に先立ち、それは「あしきもの」や「もののけ」の〈もの〉を指すのであり、『日本書記』の「邪鬼」がそれに当たると論じた。日本では「まがまがしき諸現象の源をなすものが、〈鬼〉の概念に近いものとして認識」(馬場)されていったのである。
馬場は「「鬼」字の登用について注目すべきことは、『古事記』がまったくこの文字を捨てているのにたいして、積極的で、しばしば闘争的でさえある『日本書記』が、この文字をさかんに使用していることである」と書いている。『古事記』が国造り神話などを含み、『日本書記』がより史実に即した編年体の天皇列伝であるのは周知の通りである。成立時期はほぼ同じだが『古事記』の方が古い神話伝承を含んでいる。それは神話時代には茫漠とした「まがまがしき諸現象の源」としてあった鬼の概念が、正史である編年体の『日本書記』においてはっきり存在の形を取って現象し始めたことを示している。わたしたちがイメージする具体的な鬼の姿は、まず正史によって形作られたのである。つまり政治的言説が鬼の形を生み出している。
天暦九年(九五五)大内裏の北野に一夜に千本の松が生え、道真を斎えとの宣託があったので、ここに社を建て、「天満大自在天」と尊称したが、それでもなお憤りは冷えず、しばしば内裏は火災に焼亡した。(中略)ついに、正暦四年(九九三)一条天皇によって正一位太政大臣が贈られ、道真の曾孫幹正が勅使に立てられた。(後略)
思えば気の遠くなるようなながいながい怨みであった。しかしながら、いささか日本人ばなれのしたような、九十年という何代にもわたる長大、かつ、強烈な憤怒と怨みは、この時すでに道真個人をはなれたものとなっていたといえる。(中略)政治の暴力によって破滅した老右大臣、誠実な儒学者への同情が氏の長者藤原氏の富裕の専制への憤りに転化するには、さして時間のかからぬほどに、民衆は貧しく苦しんでいたし、そのできる抵抗といったら、不幸な暗い風説に托して、強大なものへの呪詛と憤懣をささやきあうことぐらいであったのだから。
(馬場あき子『鬼の研究』)
菅原道真は藤原氏嫌いの宇多天皇の時代に頭角を現し、醍醐天皇の御代に右大臣にまで昇進した。藤原氏以外の貴族としては異例の出世だった。しかしそれにより左大臣・藤原時平と激しく対立することとなり、時平の讒訴によって大宰権帥に左遷され九州太宰府で没した。延喜三年(九〇三年)のことである。道真死去から一条天皇が正一位太政大臣を追贈するまでの九十年間、朝廷は道真の怨霊に怯え続けた。内裏への落雷や貴人の急死は、すべて道真の祟りだと思われるようになっていったのである。現在では道真は学問の神様として祀られ、いわゆる天神様は穏和な表情をしているが、室町時代頃の道真像が憤怒相の鬼神であることはよく知られている。
馬場は『鬼の研究』で道真以外にも政治的に敗北し、表舞台から去って行った例を数多く挙げている。例えば大国主や一言主は大和朝廷によって滅ぼされた土着の古代豪族だと考えられている。土蜘蛛も同様で、彼らは土着先住民であり大和朝廷に平定された。時代は下って平安王朝になるが、大江山の鬼や酒呑童子は京周辺の山中に居を構えた盗賊集団で、当時台頭しつつあった朝廷武士によって討伐された。彼らの多くは後に手厚く祀られ、それにより朝廷(権力)を守護する役割を与えられた。権力を脅かす不穏で得体の知れない力だった者たちは、滅ぶことで形ある鬼や天狗のイメージをまとうことになったのである。わたしたちが抱いている鬼のパブリックイメージは権力が作り出したものである。節分の鬼が、ひたすらに追い払われることで日常的平安をもたらす役割を担っているのと同じ構造である。
これら権力によって平定された鬼は、ほとんどの場合〝男の鬼〟として表象される。彼らは権力に取って代わることができる力と価値観を有していたからこそ攻め滅ぼされ、その力の源を恐れる権力によって祀られ国家安寧の礎として権力構造に組み込まれていった。しかし政治的操作だけで世の中の底辺に蠢く不穏な力を抑え込めるはずもない。恐ろしげだがどこか滑稽で寂しげな鬼のイメージの裏面には、常に激しい憤懣や怨みが渦巻いている。それが権力によって牙を抜かれる前の鬼の本姿である。この鬼は魔のように人々の心に忍び込み、厳しい法と秩序によって支配する権力を背後から脅かす。この鬼には本質的に形がない。権力によって平定されることもない。このような鬼が現実世界に現象するとき、それはしばしば〝女の鬼〟の形を取る。
『堤中納言物語』の作者は、なお不詳というべきであるが、この「虫めづる姫君」という短編をみるとき、そこにあるものは美意識の倒錯という以上に、価値観の破壊と転換への積極的な自問の姿である。人びとから嫌悪される毛虫や蛇のうごめきに、あまねき生きものの真率にして苦しげないのちのさまをみつめ、蝶となる未来を秘めた変身可能の生命力に、醜悪な現実を超える妖しい力を感受していた美意識とは、まさしく爛熟しつつある王朝体制の片隅に生き耐えている無用者の美観というべきである。世の良俗美習に随順することを拒んだ美意識、反世間的、反道徳的世界に憎まれつつ育つ美の概念、少なくとも「虫めづる姫君」の一篇は、そういう心によって描かれた短篇といえる。
(馬場あき子『鬼の研究』)
「虫めづる姫君」は平安時代末頃に書かれた『堤中納言物語』の中の一篇である。虫めづる姫君は毛虫が蝶に羽化する過程を楽しみ、蛇の鱗の動きに惹かれている。ただ姫君は表立って社会に異を唱え反旗を翻す者ではない。王朝時代の女性の習俗に従って、あくまでしとやかに垂れ幕や几帳の影に身を隠しながら、秘かな美の反逆に耽るのである。平安時代の高貴の姫君は男の為政者の政治的駒だった。藤原氏を始めとする高官らの未来は、入内させた娘が皇子を産むかどうかにかかっていた。そのような姫君の一人である虫めづる姫君があるとき、「鬼と女は人に見えぬぞよき」という言葉を洩らす。この言葉に馬場が鬼の本質を見ているのは言うまでもない。鬼は本質的に不定形で目に見えないものである。
『鬼の研究』で馬場は不定形の怨嗟の情念としてある〝鬼的なもの〟が、次第に一つの具象的イメージへと練り上げられてゆく歴史を明らかにしている。『日本書紀』「神代記」には「彼の国に、多に螢火の光く神、及び蠅声なす邪しき神あり。復、草木咸に能く言語あり。――吾れ葦原の邪しき鬼を撥ひ平けしめむと欲ふ」という記述がある。「鬼」は「もの」と読まれているが、神聖で超越的な力を持つ「螢火の光く神、及び蠅声なす邪しき神」の総称である。この鬼は『日本書紀』「斉明記」の天皇崩御の箇所では「朝倉山の上に、鬼有りて、大笠を着て、喪の儀を臨み視る」と記述されるようになる。斉明天皇は蝦夷・粛慎征伐を行い、百済救済のために朝鮮に出兵した。斉明天皇に武力で討伐された者たちの怨みは深く、兵役や労役のために駆り出された民衆の苦しみは世に充ち満ちていた。それが大笠をかぶって天皇の葬列をじっと見る異形の鬼の形を生み出した。
もちろん古典に現れる鬼の姿は様々である。平安時代初期成立の『伊勢物語』第六話は、在原業平が思い人の二条后高子を盗み出したが、彼女は鬼に食べられてしまったという話を載せている。しかし『伊勢物語』はこの鬼啖に続けて「御兄堀河の大臣、太郎国経の大納言、まだ下らうにて内へまゐり給ふに、いみじく泣く人あるをききつけて、とどめてとりかへし給うてけり。それをかく鬼とはいふなりけり」――高子の兄弟の藤原基経・国経がまだ身分の低い時だったが宮中に参内された時に、ひどく泣く人がいるのを聞きつけて、引き返して取り返しなさったのである。それをこのように鬼の仕業だと言ったのだ、と記述している。つまり実際には基経・国経兄弟が、業平から高子を奪還したのである。兄弟にとって高子は后として入内させるための大切な駒だった。まんまと業平に姫を奪われた恥辱と高子と業平の艶聞を隠蔽するために、彼女は鬼に食われて消えたことにしたのだった。
『伊勢物語』第六話の鬼は姿を隠す必要がある権力の異名である。ただ業平の元に鬼が現したことには必然性がある。馬場は『鬼の研究』で鬼に食べられた女の奇譚を数多く紹介している。当時の女性たちは社会的弱者であり、異界から現れた鬼であれ、権力や群盗の異名としての鬼によってであれ、常に虐げられる対象だった。その女性たちが社会に向けて自己主張できる唯一の武器が和歌だった(その多くが男[社会]との贈答歌の形を取った)。その男社会の中で、業平は平城天皇の孫という貴種だが皇統を外れ、臣籍降下したあぶれ者だった。虫めづる姫君と同様に社会的無用者だったのである。その「身を用なきものに思いなし」た業平が持っていた唯一の武器もまた和歌だった。社会的に抑圧された者たちの情念渦巻く和歌の世界に身を置き、女性たちとその世界を共有できたからこそ、業平の背後に鬼が出現したのである。業平は光源氏と同様、女性的な心を知る人だった。
時代が進むにつれて権力の締め付けはきつくなる。権力は社会に渦巻く不穏な憤懣と怨恨を、鬼や天狗といった目に見える形に整理して権力機構に組み込んでいった。それは男の権力者が男の反逆者を平定し、帰順させる場合には比較的有効に機能した。しかし権力の手は女性たちの世界には及びにくかった。女性たちは虫めづる姫君のように、「人に見えぬぞよき」場所に身を置きながら社会を鋭く批判し続けたのである。この女性たちの情念も鬼と化していった。むしろ男性的な情念があらかた権力に組み込まれてしまった後に、決して消え去ることのない女性的な情念が、鬼としてその禍々しく美しい姿を垣間見せたのである。
中世という過酷な時代にいたって、はじめて誕生した〈女の鬼〉は、ある夜、ある時、絶望に冷えさびた情念をかき立てつつ、とてつもなく美しい言葉を噛みしめ味わうようにうたいはじめる。それはむしろ、ひとつの秩序に順応して生きるもの以上に人間的でさえある。にもかかわらず、それは社会的拒絶と正面からぶつからざるを得ない。人間的なものの回復を求めるその哀切な祈りも、破滅した部分だけが烙印のように拡大されている〈鬼〉にとってはまったく空しい。そのうえ、旅僧は女主人との約束を破って、その閨房をのぞくのである。この残酷な最後の背信行為によって、かずかずの情念の贄を秘めた閨をのぞかれた女が、羞恥のきわみ鬼となることはむしろ美しすぎるくらい人間的なことではないか。
(馬場あき子『鬼の研究』)
馬場が語っているのは能『黒塚』(安達原)についてである。廻国行脚の僧一行が陸奥国安達ヶ原で行き暮れて、老媼の住む粗末な一軒家に宿を借りる。老媼は問われるまま今の苦しく孤独な生活を語り、昔の煌びやかな生活について語る。夜更けに老媼は薪を取りに出る。その際、決して閨を覗かないよう念を押してゆく。寺男が我慢できずに閨を覗くと、そこには男たちの死体が積み上げられていた。恐れおののいて僧たちは逃げ出したが、鬼となった老媼が追いかけてくる。しかし僧たちの行法によって調伏され、「あさましや恥ずかしの我が姿や」と自らの姿を恥じて、闇の中に消え去ってゆくのがその梗概である。
馬場は『黒塚』を、最も端的に〈女の鬼〉が表現された作品だと捉えている。しかし『黒塚』は特殊な作品でもある。「「黒塚」は「鉄輪」や「道成寺」や「葵の上」のように、〈愛の復讐〉という般若もの固有の目的をもっていない」(馬場)。それは鬼が消え去る理由にはっきりと表現されている。鬼と化した媼は僧たちの祈祷では成仏しない。彼女は自らの心のあさましさと容姿の醜さに気づいて自らの意志で闇に消えていったのである。それは「意外にもきわめて内省的な羞恥の情」(馬場)の湧き上がりによる溶暗である。
安達ヶ原に住む鬼女伝承は、源兼盛の和歌「みちのくの安達原の黒塚に鬼こもれりときくはまことか」から生まれた。説話文学では単純に女が鬼となり、食べるために旅人を殺していたのだと語られる。しかし能『黒塚』の作者(金春善竹とも言われるが不詳)はそれを採用しなかった。『黒塚』の見所は「さてそも五条あたりにて、夕顔の宿を尋ねしは、日陰の糸の冠着し、それは名高き人やらん」といった、『源氏物語』の六条御息所を想起させる老媼の華麗な過去の回想である。また鬼が僧侶一行を追いかけてくるのは彼らが禁を破って閨を見たからである。非は僧一行の側にある。また確かに閨には死体が積み重なっていたが、鬼が最初から僧侶一行を食い殺そうとしていたのかどうかは判然としない。鬼は「さしも隠しし閨の内を、あさま(あからさま)になされ参らせし、怨み申しに来たりけり」と言うばかりである。
『黒塚』の老媼(鬼)は、過去の栄華をよすがに、生きる目的もないうらびれた今を耐えている。彼女は表社会から弾き出され抑圧された人間の一人である。その胸の内に渦巻く怨嗟が閨の死体となって現象したとも捉えられる。また閨の男たちは彼女を社会の底辺に追い詰めた者たちかもしれない。あるいはもはや老媼のように憤懣の声すら上げられない、弱々しい社会的落伍者(男たち)の累々の死体かもしれない。いずれにせよそれは「かずかずの情念の贄を秘めた閨」である。その心の恥部を覗かれた老媼が鬼と化したのである。
このような権力が決してなだめ得ない、社会の至る所に渦巻く情念の在り方は女性のものである。しかし女性しか持ち得ない情念という意味ではない。ジェンダー理論にあるように、〈男性性〉と〈女性性〉は厳然たる生物学的相違であると同時に、社会・文化的に形成された性差でもある。特に文学を始めとする表現の世界ではそうである。男性作家が男の世界しか描くことができず、女性が女性の世界しか表現できないということはない。〈男性性〉と〈女性性〉は生物学的相違に関わらず、一個の人間の中に存在する社会・文化的思想ベクトルである。それを詩人・小説家で批評家の小原眞紀子は「テキスト曲線」で表現している。

© 小原眞紀子
テキスト曲線が使われたのは『源氏物語』論においてだが、小原は「制度そのものが「男性性」のものなのです」、「そしてテキスト曲線の「山」=制度の頂点=権力の中枢に近く立つ源氏が、心も身体も溶けるように溺れるのは、この右側の「海」=女性性そのものです」と書いている。また「テキスト曲線において、中心のなだらかなところが俗世である「社会」に当たります。私たちは究極の「男」や「女」そのものとしてでなく、男も女性的な面を持ち、女も適当に男性化されつつ、社会生活を営んでいる」と説明している。
至高観念同士として捉えれば、テキスト曲線の男性性ベクトルの頂点において人は神的(あるいは仏教的)救済を夢想する。女性性ベクトルの頂点では人を包み込み癒してくれる、純粋無垢な母性を見出すはずである。また対概念として捉えれば、男性性ベクトルの頂点を冷酷な政治秩序、女性性ベクトルの頂点をそれを脅かす憤懣に満ちた情念と措定することもできる。この両ベクトルの頂点に現れる観念が成立したのは『新古今和歌集』から『源氏物語』、『新古今和歌集』に至る王朝時代である。もっと正確に言えば、権力による社会的ヒエラルキーの確立が進むにつれて、王朝女流文学がそれを揺るがす女性性ベクトルとして成立していったのである。
一度送りこまれたら永遠に浮かび上がれそうもないこれら地獄の住人の罪状がまた、魚鳥獣などを殺した殺生罪であったり、邪淫妄語罪であったり(中略)世の生活者たるもの、その罪状の一つにも当たらないというものはありえないといえる。(中略)それに比べると、極楽のイメージは単一すぎてむしろ寂しいくらいだ。しかし、それは人々が浄土そのものの空想にまずしかったということではなく、生活実感にひびく八大地獄を底辺にかかえてはじめて成り立つ浄土のイメージは、平穏安息の一点に収斂されるもの以外になかったというべきかもしれない。(中略)たとえそれが、いわゆる権力体制を強め、現世の秩序の中に、いよいよ民衆を束縛固定することになったとしても(中略)この架空なものがもたらす空想は、同時になお隠微に、仏の守護する権力体制そのものをも挑発しつづけたといえるだろう。奇妙なことに、地獄においては〈死〉というものがない。それは、死以上の過酷な残虐のみが支配する世界であって(中略)気が遠くなるほどの責め苦の時間の果てに、それはまさしく徐々に〈生〉に向かって動いている世界なのである。(中略)それは不死身で、しぶとい。そして醜く卑しいながら、ふしぎに確実な、手ごたえのある生命感をどろどろと底流させている。
(馬場あき子『世捨て奇譚』昭和五十四年[一九七九年])
『世捨て奇譚』で馬場は、『往生要集』や『今昔物語』、『日本往生極楽記』など平安時代から鎌倉時代に書かれた説話集を元に、世を捨て極楽に往生したいという当時の人々の願望を読み解いている。「往生とは、浄土に往って、彼の地に新生することであり、永遠に地獄の黒煙猛火を離脱したこと」(馬場)である。当時の人々にとって、死後に浄土に新生できるかどうかは人生最大の関心事の一つだった。現世で人々を浄土に導く役割を担う高僧はもちろん、貴人から庶民に至るまで、人々は驚くべき情熱を傾け往生をこいねがった。

最近になって創建当初の姿に復元された、藤原頼道創建の極彩色の宇治平等院鳳凰堂を見ればわかるように、当時の仏教は幻視的な密教だった。人々は意識朦朧とした状態に陥る念仏修行や臨終の際において、まざまざと仏の来迎を幻視し、地獄の責め苦の有様を具体的な細部に至るまで見た。当時は「地獄と極楽がすでに明確な体系の中にある」(馬場)時代だった。そのような体系化が必要だったのは、何よりも秩序ある国家体制確立のためである。飛鳥時代に仏教がもたらされて以降、朝廷はそれを鎮護国家のために活用した。言うまでもなく日本固有の神道には浄土と地獄という概念がない。現世の罪によって死後に地獄に堕ちることを心から恐れ、浄土をこいねがう心性は、「権力体制を強め、現世の秩序の中に、いよいよ民衆を束縛固定する」役割を果たしたのである。
ただ馬場は「〈厭離穢土〉などという、反人間的な稀代な逆説が、最も人間的な求めであるとして信じられるためには、どれほど過酷な生活の具体が必要であったことだろう」と書いている。また「発心という行為が、世を捨てるという思想が、最も消極的に見えていて実は最も根深い、かたくなな現実批判であるとすれば、発心者はおそらく地獄に現実を見、現実に地獄を見ていたにちがいない」とも述べている。当時は貴人から庶民に至るまで、ある時期に出家して世を捨てることが多かった。〝世捨て〟は原理的に、非は現実社会の側にあるとして、それを強い意志をもって捨て去ろうとすることである。それは地獄のような現世への「かたくなな現実批判」でもあった。しかし生きている限り世を捨てることなどできはしない。
〝世捨て〟を前提とすれば、テキスト曲線の男性性ベクトルの極点には体制護持的な〈浄土〉がある。この浄土の対概念であり、往生指向が強まれば強まるほどその具体的イメージを膨らませていったのが、女性性ベクトルの極点にある〈地獄〉である。この地獄は「仏の守護する権力体制そのものをも挑発しつづけた」が、〈浄土〉と〈地獄〉は共に世界に必要不可欠な要素だった。それは人々が、極めて人間的な倫理を育むための思想フレームの役割をも担ったのである。しかしそれらは人間が作り出した観念の極に過ぎない。
極論を言えば、〈浄土〉と〈地獄〉は観念という点で同質である。そのため仏教説話ではしばしば〈仏〉と〈鬼〉が交わり合う。ただ〈浄土〉と〈地獄〉という観念の極を離れれば、中間にあるのは現実世界である。この現実世界に生きる人間は、地獄に堕ちるのを恐れ極楽往生をこいねがう。人間は不安定な生を超脱し、安心立命できる観念の極を希求する生きものなのだ。しかし浄土も地獄も決して人間の前にその姿を現しはしない。撞着的な言い方になってしまうが、死によって断ち切られるまで、そこには無間地獄のような〈生〉の苦しみしかない。馬場は地獄について、そこには「〈死〉というものがない」、「それは不死身で、しぶとい。そして醜く卑しいながら、ふしぎに確実な、手ごたえのある生命感をどろどろと底流させている」と書いたが、それは本質的に、裸眼で人間の生を見つめた際の過酷な現実認識である。
鶴山裕司(中編に続く)
■鶴山裕司詩集『国書』■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■



