
歌状況は挽歌の時代に突入した。すなわち、六〇年代短歌にはいまだ可能であった行為する者としてのわれは、そこにはない。また呼びかけるべき他者〈他者=われわれ〉という図式もそこにはない。つまり、呼びかけるべき〈われ〉と、呼びかけに応えるべき〈われ〉とが共有すべき関係性は遮断され、直接伝達形としての〈われわれ〉は、もはや存在しないのである。〈われわれ〉の〈われ〉と〈われ〉は引き裂かれ、死という絶対の高嶺に登った者にむけて、ひたすらに献辞を捧げる〈われ〉の、内なる行為のなかにすべては収斂されて在るのである。
それゆえに、七〇年代挽歌をなすということは、生者たるわれわれが、死者の志を、生者たるわれわれの志として体現しうるのではないかという仮構をつくりだし、その中に死者と生者を結ぶわれとわれたるわれわれを喚起しようという営為にほかならない。
(福島泰樹「七〇年代挽歌論補足」)
福島は「七〇年代挽歌宣言」をして、現在に至るまで挽歌を詠む歌人である。その表現基盤が確立されたのが七〇年代初頭だった。そこにはもはや〝われわれ〟と呼ぶべき連帯はないという認識がある。〝われわれ〟とは〝われ〟と〝他者〟の直接交流によって生み出される精神の共同体だが、そんな紐帯は存在しないのである。それは一義的には七〇年安保闘争の敗北によって生じたものである。しかし福島は文学者だ。安保闘争の最中に掴んだ精神の〝高嶺〟を、どのように維持するのかが最大のアポリアである。現実社会で〝われ〟と〝他者〟を結びつける状況が霧散してしまった以上、それはより内向的なものに――つまり〝生者〟が〝死者〟の不変の精神を共有することにならざるを得ない。それにより、現実社会状況に左右されない〝われわれ〟の精神的共同体を実現できるというのが福島の思想である。
一九七〇年代は厳しい時代だった。昭和四十四年(一九六九年)には前衛俳人・安井浩司が出奔している。七〇年夏には高度経済成長の象徴でもあった大阪万国博覧会が開催されたが、七月に歌人の岡井隆が失踪した。また十一月には三島由紀夫が東京市ヶ谷の自衛隊駐屯地で自死した。四十六年(七一年)に全共闘世代の良心ともいえる高橋和巳が死去し、五十年(七五年)に歌人・小説・批評家で、優れた『北一輝論』を書いた村上一郎が自死した。福島は村上の悼歌集を出版し、「潔くわが心境を述べるならあかねさす夜ぬばたまの昼」というダブルバインド的な歌を詠んでいる。文学者たちの出奔や自死はそれぞれ背景の異なる複雑なものである。しかしそれは同時代の文学者が起こした事件であるという意味で、原則的には天災と事故である東日本大震災(福島第一原発事故)などとは比べものにならない意味を持っていた。
人々の耳目を一身に集める社会的大事件が起こらなかった分、七〇年代の人々の精神の変化はより自発的で根深いものだった。自由詩の世界だが、吉本隆明は『戦後詩史論』でこの時代を「修辞的な現在」と規定した。簡単に言えば、五〇年代、六〇年代に確立されたかに見えた戦後精神が崩壊し始めたのである。俗な言葉で言い直すと、勤め人として働き家族を養う平穏な生活が、独立不羈であったはずの思想を浸食していったのだ。

自由詩の詩人たちは同時代の変化を言語実験で表現しようとし始めた。明るい未来を約束する高度経済成長の波に呼応するように、未知の新たな言語表現の可能性を追い求めたのである。いわゆる〝現代詩の実験〟だ。ただ詩人の思想と新たな表現が密接に結びついていたのは、鮎川信夫、田村隆一、吉本隆明らの「荒地」派の時代から、最初の現代詩派である入沢康夫、岩成達也らが登場した時代までだったと言っていい。七〇年代に登場した多くの詩人の言語表現は、新しく見えようとも思想的裏付けを持っていなかった。それを小手先の言語テクニックという意味を含めて吉本は「修辞的な現在」と呼んだ。
自由詩の世界で起こっていたことは、当然だが小説界や歌壇、俳壇でも生起していた。ただ歌壇、俳壇では、詩壇や文壇で起こった劇的変化がワンテンポ遅れて始まった。現代短歌は塚本邦雄の『水葬物語』(昭和二十六年[一九五一年])を嚆矢とするが、その影響が顕著になったのは一九六〇年代に入ってからである。歌人・俳人は桑原武夫の『第二芸術』論(昭和二十一年[一九四六年])に大きな衝撃を受けたが、それを消化して初めて短歌・俳句の〝戦後現代〟が始まった。そのため短歌の世界では、自由詩壇や小説文壇よりも戦後社会の変化を辿りやすいところがある。五〇年代は新たな戦後精神の勃興期だが、それが熱を帯びるのは六〇年代に入ってからである。そして七〇年代には福島が書いたように「挽歌の時代」が始まった。
ザクロザクロ俺はガクガク君グググ擬音で語る人生もある
かなかなの金切声を真似しつつしんにさびしくなりにけるかも
(『夕暮』昭和五十六年[一九八一年]九月刊)
一木の優しさゆえにあかあかと陽は登りけりあかあかとまた
人間はみな泡沫だよ父上よ山茶花散ってゆくではないか
(『月光』昭和五十九年[一九八四年]十一月刊)
福島の短歌を通読すれば、戦後社会とその精神的変化を手に取るように理解できるようなところがある。「ザクロザクロ俺はガクガク君グググ擬音で語る人生もある」に典型的なように、福島の絶唱は擬音と繰り返しで表現されることが多い。痛切な断念や渦巻く情念が撞着的な言葉で溢れ出るのである。六〇年と七〇年の政治闘争に敗れた青年たちのその後には、転向と言えば誰の身にも転向はあった。その生きるための苦渋に満ちた選択をなんびとも責めることはできない。だが福島は、「だけど君の精神は変わっていないんだろう?」と声をあげ続けている。ただ「しんにさびしくなりにけるかも」とあるように、八〇年代になってまでそんな思想にこだわる者は急速に少なくなっていた。
戦後思想は本質的に独立不羈の精神である。戦前に政府が是とした皇国主義を一瞬でも信じた人々にとって、戦後に政府が是とした民主主義もまた頭から信じ切れるイデオロギーではなかった。そのため終戦時のほぼ完全な空白状態を経験した人々は、どんな社会変化にも左右されない個の精神を思想の基盤に据えた。決して社会の大勢に靡かないという意味で、それは広義の反体制・反権力思想だった。自由詩の世界で最後までそれを維持し続けられたのは、鮎川信夫や田村隆一、飯島耕一といった一握りの詩人たちだけである。また福島らの戦後の青年たちは政治闘争に明け暮れたが、鮎川ら従軍経験のある詩人たちは六〇年、七〇年安保闘争を静観した。世代的な差異と言ってしまえばそれまでだが、鮎川らは福島が七〇年代になって見出す「挽歌の時代」を先取りしていたのだと言っていい。鮎川もまた死者にこだわった詩人だった。
十年ほどのタイムラグがあるが、福島は自由詩の世界での戦後詩人になぞらえられるだろう。ただ一九八〇年代の「修辞的な現在」の時代に多くの戦後詩人たちが、かつてはあれほど明瞭だった思想を失っていった、あるいは思想を維持するために詩の創作手法――つまり現代社会の認識方法を変えざるを得なくなったように、福島にも困難が襲いかかった。転機になったのは歌集『中也断章』である。
中也断唱 弐
大正十四年十一月、泰子、小林秀雄宅に転居す。
真鍮の光沢よりもま輝ける笑みを湛えて出てゆきにけり
茶碗下駄歯刷子襦袢と分けやれば嫁ぐ娘の母のごとしも
リヤカーを引いて夜道を急ぎおり盗まれたのか差上げるのか
星降る夜の話なんかに誘われ月光曲しかおれは歌わぬ
(『中也断章』昭和五十八年[一九八三年]十二月刊)
『中也断章』は中原中也の人生に沿って短歌を詠んだ連作歌集である。よく知られているように中原は京都時代に女優の長谷川泰子と同棲したが、大正十四年(一九二五年)に上京すると泰子は小林秀雄の元に去り、彼と同棲し始めた。中原と小林の緊張をはらんだ友人関係は終生続いたが、二人ともまったくこの恋愛事件については語っていない。しかし大岡昇平が詳細な調査に基づく伝記『中原中也』をまとめており、事件の概要はおぼろにわかる。「リヤカーを引いて夜道を急ぎおり盗まれたのか差上げるのか」とあるように、中原は泰子の荷物をまとめて小林宅まで付き添って行った。ただ福島の歌は事実に基づきながら飛翔する。「星降る夜の話なんかに誘われ月光曲しかおれは歌わぬ」は、言うまでもなく福島の中原理解に基づく創作である。
福島は『中也断章』執筆中の状態について、「なにを見ても、なにを聞いても中也に直結していった。そんな昂奮は三日三晩におよび、ついには体中の節々は鈍い痛みを発し、ノートはみるみる歌で埋まっていったのだ。歌を作ることに、かくも長時間熱中したことは、あとにも先にもこの時が初めてであった」と歌集「跋」で書いている。詩の世界で、詩人が時代も環境も異なる人間の精神に自己のそれを重ね合わせて作品を作る方法は、ペルソナと呼ばれる。ある作家や時代精神を的確に表現するための方法だが、福島の作歌法は過激である。方法的な理知性はほとんどなく、作家の肉体と精神を賭けた憑依だと言っていい。ではなぜ中原が選ばれ、福島は彼の精神の何に憑依しようとしたのだろうか。

福島泰樹著『中原中也 帝都慕情』日本放送出版協会刊 平成十九年(二〇〇七年)
私は私の短歌的抒情の源流を、伝統的短歌からではなしに、朔太郎や静雄、中也から汲みとってきたのだ。彼らの詩業のうちに私は、なぜにこの国の詩が五句三十一音に収斂されていったのか、彼らが否定したものは短歌のもつ秩序と拘束であり、短歌そのものではなかったのではないか、ということを見ていたのである。彼らの詩業のうちに私は、歌なるものの源泉としての短歌をみようとしていたのだ。
(『中也断章』「跋」昭和五十八年[一九八三年]十二月刊)
「私は私の短歌的抒情の源流を、伝統的短歌からではなしに、朔太郎や静雄、中也から汲みとってきたのだ」とあるように、福島は日本の詩の歴史を遡るようにして〝短歌的抒情の源流〟を把握しようとしている。それは一九八〇年代の「修辞的な現在」の時代に、言い換えれば〝戦後前衛の解体の時代〟に歌人の誰かが行わなければならなかった原理的探求である。一九八〇年代に詩の前衛は終わり始めていた。あるいはさらなる〝前衛の変容〟が求められていた。
吉田一穂は「詩は短歌的原罪を負っている」と言ったが、おおむね北原白秋の時代まで自由詩は短歌的抒情と共にあった。白秋門から一穂と萩原朔太郎という二人の俊英が現れたのは奇妙な出来事であり、必然でもあった。白秋は日本の初期象徴主義を代表する詩人だが、その内実はマラルメらのヨーロッパ象徴主義詩とは大きく異なる。馬場あき子が白秋短歌について「韻律が白秋の思想だった」と指摘したように、白秋詩の抒情は意味ではなく韻律(音)で表現されていた。処女詩集『邪宗門』が徳川時代まで禁制であったキリスト教を題材にしながら、いかなる反体制思想も描くことなくギヤマンや天鵝絨といった異国情緒溢れる言葉の語感によって成立しているように、白秋作品は雰囲気詩である。日本語の古語・稀語を外国語に接する時のような新鮮さで取り扱うのが白秋的手法だった。またそれが白秋が生きた明治から大正時代の〝現代〟の捉え方だったのである。
白秋は生涯に渡り、心地良い韻律で構成されるが、意味的には驚くほど希薄な雰囲気詩を書き続けた。この極端なほど徹底した試みがあったからこそ、そこから意味と、意味を超えた何事かを表現しようとする奇矯なイメージに満ちた一穂や朔太郎の詩が生まれて来たのである。朔太郎が『詩の原理』--「序」にあるように正確には「自由詩の原理」--を書いたのは偶然ではない。島崎藤村から白秋に至る自由詩は短歌的抒情と韻律を基盤にしているが、朔太郎の出現をもって自由詩は日本文学における独自のアイデンティティを確立した。
朔太郎が確立した自由詩のアイデンティティは、戦後の戦後詩や現代詩まで引き継がれた。白秋までのいわゆる近代詩は、多かれ少なかれ日本文学の過去の遺産を新渡来のヨーロッパ詩に折衷させていた。しかし朔太郎以降日本の自由詩は、各時代の〝変化〟をいち早くその表現に取り入れるようになった。岩成達也が『詩的関係の基礎についての覚書』で「一つの新たな世界把握には一つの新たな書法が対応する」と書いたように、社会が大きく変化すればそれに呼応して自由詩の書法も変わる。だから自由詩なのだ。日本文学における自由詩は、各時代の〝前衛〟であることをそのアイデンティティの基幹に据えた。表現は未熟であろうとも、自由詩は各時代の変化をダイナミックに捉えるアンテナ文学であろうとしたのである。
この自由詩の前衛性の影響を、一九六〇年代になってはっきり短歌・俳句の世界は受けることになる。短歌では塚本邦雄、岡井隆が双璧だろう。俳句では高柳重信の前衛俳句運動がその代表である。福島もまた前衛短歌運動の渦中から現れてきた歌人だ。しかし八〇年代には自由詩的前衛が岐路にさしかかっていた。短歌・俳句芸術もまた、新たな書法によって現代を表現するという自由詩的前衛を受容・消化した上で、今一度自らの基層を確認することを迫られたのである。
福島の短歌はその最も早い試みだろう。彼は短歌芸術の枠内でのみ歌を作ってきた歌人ではない。「彼ら(朔太郎や静雄、中也)の詩業のうちに私は、歌なるものの源泉としての短歌をみようとしていた」とあるように、短歌芸術を一度相対化した上でその〝源泉〟を把握しようとしている。そのアプローチ方法は正しい。短歌芸術の根を認識把握できなければ、歌人は本質的に八〇年代以降の現代を生き延びられなかったと言って良い。(下編に続く)
鶴山裕司
* 写真は二〇一六年八月十日の吉祥寺曼荼羅における福島泰樹「短歌絶叫コンサート」のスナップ(撮影・鶴山)
■ 福島短歌絶叫は毎月10日に吉祥寺曼荼羅で開催されます ■
■ 福島泰樹さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

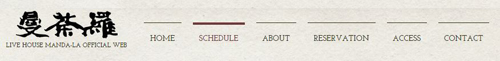
![遥かなる友へ~「福島泰樹短歌絶叫コンサート」総集編 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51etcHYqhTL._SX250_.jpg)
