 世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
世界は変わった! 紙に印刷された文字の小説を読む時代から、VRでリアルに小説世界を体験できるようになったのだ。恋愛も冒険も、純文学的苦悩も目の前にリアルな動画として再現され、読者(視聴者)はそれを我がことのように体験できる! しかしいつの世の中でも悪いヤツが、秩序を乱す輩がいるもので・・・。
希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、極めてリアルな近未来小説!
by 遠藤徹
十二、『三四郎』第二章 『三四郎』第二章 森の女(前編)
昼飯を挟んで、俺たちは第二章に取り組んだ。三四郎が食った弁当、広田と三四郎が食った水蜜桃と弁当のイメージが体に残っていた。だから、その日のカップうどんの昼飯はよりいっそう惨めな感じを俺たちに与えた。
「あのさ」
と声をかけてきたとき、高満寺は、すでに三杯目のカップうどんに箸をつけているところだった。一杯目が「どん兵衛きつねうどん」、二杯目が「まるちゃん黒豚カレーうどん」、そして三杯目は「なつかしの豚汁うどん」というやつだった。熱々の麺だというのに、彼女が食らう速さは尋常ではなく、俺はまだ一杯目の「赤いきつねうどん」を、半分も食い終えていないところだった。
「どうせなら、谷崎風に『もとより気の利きいた料理屋などのある町でないのは分っていたから一時のしのぎに体をぬくめさえすればいいのでとある饂飩屋の灯を見つけて酒を二合ばかり飲み狐うどんを二杯たべて出がけにもう一本正宗の罎を熱燗につけさせたのを手に提さげながら』仕事に戻るってな感じの風情が欲しいわよね」
「ああ『蘆刈』だね。なかなか渋いところをついてくるじゃないか」
君にそんな教養があったとは驚きだ、などとはとても言えないから、何重にもオブラートをかぶせるとこういう言い草になる。
「たまたまよ」
ああ、やっぱりね、と思ったが、当然口にはださず、ただ「あぢっ、あぢっ」とうどんをすする俺。そう、誰知ろう、誰も知るまい、知る気もなかろうけれど、俺は猫舌なのだ。
「前に事件があってね、それで張り込みで入ったことがあるのよ、そのうどん屋に。いまでも京都の大山崎の方にある実在の店らしいわよ」
「へえ。行ってみたいものだな」
そんなことなら、『蘆刈』にダイブして、そのうどん屋の客席でカップめんを食えばよかったと思う俺であった。でもまあ、お酒もきこしめすのであれば、お相手が高満寺でないときの方がいいな。うん、そうだ、それに限る。

「なに、にやついてんのよ」
高満寺に突っ込まれて、美女との逢瀬という妄想のしゃぼん玉は、しょぼんと弾けた。
「はい、ランチ終了。仕事仕事」
時計を見た高満寺が三杯目の汁を豪快に飲み干して、がたりと立ちあがった。そして、まだ一杯目の赤いきつねすら食べ終えていない哀れな猫舌男を、たらふく食った大女が再び小説の内部へと追い立てた。
「ああ、待って、楽しみに残しといたおあげがまだ~」
当然ながら、怪力女に赦しの心はなかった。あれ~、ご無体なあ。
a:たいへんな動き方
第二章は『三四郎が、東京で驚いたものはたくさんある』と、典型的なおのぼりさんの驚きから始まる。
「熊本弁でいえば、『三四郎が、東京でたまげたもんはぐっさりあったばい』という感じかね」
「さあ、方言のことはよくわからないわ」
高満寺はどうでもいいことのように答えた。まあ実際どうでもよいことである。いや、ちょっと待てよ・・・そうでもないかもしれない。だって、三四郎はこの小説の中で熊本弁を一切出さないからだ。母の手紙だって、熊本弁で書かれているはずなのに、その内容は、三四郎というフィルターを通して標準語で記述されるばかりである。三四郎が方言を封印していることには、明らかな地方コンプレックスを見て取ることができるだろう。当然その背後にあるのは、社会的ヒエラルキーにおける東京と熊本との落差である。
「三四郎が驚いたものとして四つほどあげられているよね。一つは電車がちんちん鳴ること。二つはその電車に非常に多くの人間が乗り降りすること。三つ目が丸の内。四つ目が、一番驚いたこととされていて、それはどこまで行っても東京がなくならないこと」
「三つ目だけ『丸の内で驚いた』ってとても簡潔に記されているだけよね。いったい丸の内の何が三四郎を驚かしたのかが明白でないわ」
「うん、これはこの小説が、当時の世相を当然の背景として描かれたものだったからだね。新聞小説ってのはそういう時事性をもったものだったんだ。だから、当時の読者は皆これだけで了解できたということだよね」
でも、今の俺たちには当然わからない。だから、「蘊蓄」ボタンを押して、丸の内の歴史を少しさかのぼってみることにした。
「薀蓄」によれば、江戸時代後期までは丸の内は大名屋敷が並ぶ地域だったようだ。ところが、明治元年天皇が江戸城に東幸し、大名たちがことごとく地元へ引き上げたことで廃墟と化した。当初、陸軍の兵舎をここに建てることが計画されたが、資金繰りで頓挫し、結局造船業で名をなした三菱財閥が、この丸の内の土地を買い受けることとなった。
しばらくは「三菱が原」と呼ばれる原野のまま打ち捨てられ、草隠れに賭博が行われるということで「賭博が原」と言われもするような風紀治安の悪い地域であった。その後、日清戦争を期として開発が始まり、東京府庁、三菱第一号館、第二号館、第三号館が次々と建造され、東京商業会議所も明治三二年にこの地に建てられる。三菱はさらに開発を進め、日露戦争が終わるころまでに煉瓦作りの建物が並ぶ「一丁倫敦」を完成させる。そして、明治四四年には帝国劇場と今日の東京駅にあたる中央停車場の骨組みができあがっていた。
「つまり、あれだね。『三四郎』が朝日新聞に掲載されている時点では、丸の内は建設ラッシュのただ中にあり、洋風の建物が続々と出現し、さらには初めての大がかりな鉄筋コンクリート建造物であった、東京駅の基礎工事も行われていたということになる。コンクリートミキサーやコンクリートタワーが初めて使われたのもこの地であったらしいよ。いってみれば、最新鋭の技術の粋を尽くして、丸の内には洋風の街が出現しつつあったということになるね」
VRでは、調べたことが体験として追加される。だから、俺たちの読書体験にも、赤煉瓦の建築物の写真やら、建造中の東京駅の工事風景などが実在の写真を元にした動画として再構成されて復元されていった。俺は、三四郎の目を通して、明治四十一年の東京の激変を体験することができたという実感を得た。
「『すべてのものが破壊され、同時に建設されつつある』という三四郎が抱いた感慨は、この部分を受けてるわけよね」

「薀蓄」ボタンを連打しながら、高満寺も興奮していた。にわか歴女のできあがりというわけだ。
「ちんちん鳴る電車だって、東京電車鉄道の電化が明治二六年、東京市街鉄道の開通が明治三五年、東京電気鉄道の開通が明治三十三年だから、まだまだ新規で新しいものだったわけよね。それまでの馬車や徒歩の生活から、電車で移動する生活へと生活やビジネスのあり方が激変していく時代だったわけよね」
「うん、『たいへんな動き方である』と書いてあるけど、実際そうだったんだろう。そして、『今までの学問はこの驚きを予防するうえにおいて、売薬ほどの効能もなかった。三四郎の自信はこの驚きとともに四割がた減却した』とある。さらに『この劇烈な活動そのものがとりもなおさず現実世界だとすると、自分が今日までの生活は現実世界に毫も接触していないことになる。洞が峠で昼寝をしたと同然である』と三四郎を打ちのめす。『現実の世界は、かように動揺して、自分を置き去りにして行ってしまう』と不安を感じることになる」
「確かに、旧態依然とした牧歌的かつ保守的な熊本の田舎から出てきた若造にとって、激変しつつある東京の風景は衝撃だったでしょうね。まさにカルチャーショックってわけよね」
「でも、ここでも三四郎は表面的な変化に驚いただけだとされている。実は『明治の思想は西洋の歴史にあらわれた三百年の活動を四十年で繰り返している』のに、三四郎はこの変化の背後にある思想界のそういう『たいへんな動き方』にはまったく気付かないままだとされている」
「思想の『たいへんな動き方』ってなんのことかしら」
「そうだなあ」
思想ってやつには詳しくないからなあと思いながら、「薀蓄」ボタンを押すと、いろんな例が出てきた。俺はそのうちのひとつに目をつけた。
「たとえば、こういうのがあるよ。国家に対する考え方の変化だ。明治の初めには、国家のためではなく、平民の生活向上のためにこそ欧化すべきだと人民の側に立った徳富蘇峰と、いや、そのためには国家の独立こそ最優先だと考える三宅雪嶺らの国家主義の対立があったようだよ。ところが、日清戦争を経ると、徳富蘇嶺も高山樗牛も誰も彼もが大陸進出推進派と化してしまった。さらに日露戦争の勝利が、この傾向を助長してしまったんだね。日本は、自らを東洋にも西洋にも勝る偉大な国家と錯覚するに至るんだから。これはまさに『たいへんな動き方』じゃないかな」
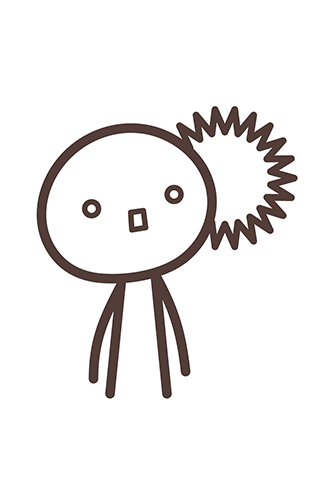
「そうね」
「つまり、『三四郎』は、東洋の大国に、ついで西欧列強の一角に勝利した自国を、根拠もないままに特殊ですぐれた「美しい国」と思いこもうとしていた時代、「明治の栄光」と呼ばれる時代を背景としているわけだね。ここから、満州国建国や国連脱退、そして三国同盟、そしてミッドウェー海戦や原子爆弾投下、ポツダム宣言受諾まではひとつながりなわけだ。日本が危ない方向へと確実に一歩を進めようとしていたこの時点で、『「滅びるね」』と言ってのけた広田はその意味で、慧眼の士であったことがわかるよね」
「根拠なく自分をエリートだと思っている三四郎は、その意味では当時の日本の思い上がりの巧みな比喩だともいえるわね」
b:マザーズボーイ
「で、カルチャーショックで、取り残されたと落ち込んでしまった三四郎をまず救ってくれるのが母からの手紙ということになるわけだ」
「結局、三四郎はマザコンよね。故郷と母親は、いつだって暖かい存在であり、現実逃避のための繭なのよね。そういう意味できわめて重要な存在なのよ、三四郎にとっては。この後も、東京でなんらかのショックを受けるたびに三四郎は、その痛手を母親を通して緩和するものね。驚くたび、傷つくたび母親に代表される故郷に回帰することで、三四郎は自分をなんとか保つことができているわけよね。『ママ、ママぁ』って感じで、全然自立できてる感じがしないわ。二十三歳って信じられないくらい・・・しっかせえよ。そぎゃんこつばしよったら、バカのすってんのってゆわるっぞ!」
怒鳴った。それも(たぶん、にわか仕込みの)熊本弁で。三四郎との同化モードに入っていた俺は、直接この恫喝をうけたことになる。高満寺は、三四郎のマザコンぶりにご立腹のようだった。
「その伝でいくと、そもそも、三四郎はまったく労働していないよね。学生だからと言ってしまえばそれまでなんだけどさ。毎月母親から二十五円も仕送りを送ってもらって、そのお金でのうのうと暮らしている。お金に不自由したことがないから、後のエピソードであるように友人の与次郎に頼まれると有り金全部貸してしまうし、しかも与次郎が返さなくても責め立てることもない。結局、その金を母親にさらに工面してもらうという有様なんだからね」
「完全に母親の手のなかにいると言うことよね」
そう、三四郎は典型的なマザーズボーイだったのである。
「でも、三四郎はそのことをまったく自覚していないよね。学問を修めた、あるいはこれから修めるであろうエリートな俺! って感じの目線で、故郷を、そして母親を見下している」
母親の手紙の内容は、さっき見たような膨張主義や、大陸進出論や、自国を特別な存在とみなす国家の奢りとはまったく無関係だよね。今年は豊作でめでたいとか、作の青馬が急病で死んだとか、お満さんに鮎をもらったけど、送ると腐るから食べてしまったとか、身の回りの些細なことが彼女の世界のすべてだということが手紙からは伝わってくる。
「三四郎はそれを軽蔑するのよね。学のない女だと見下しているわけよ。その一方で、その軽蔑している相手に癒され、そして全面的に依存してる。『三四郎はこの手紙を見て、なんだか古ぼけた昔から届いたような気がした。母にはすまないが、こんなものを読んでいる暇はないとまで考えた』くせに、繰り返して二度も読むんだもの。そして三四郎は三四郎なりにその矛盾した行動に気付いてもいる。『要するに自分がもし現実世界と接触しているならば、今のところ母よりほかにないのだろう』と述懐してもいるわけだからね」
スケベで傲慢でマザコンな二十三歳、それが我らが主人公というわけだ!
うーむ。
(第14回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『虚構探偵―『三四郎』殺人事件―』は毎月15日に更新されます。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■










