 月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
月子(つきこ)・楡木子(ゆきこ)・好女子(すめこ)・夾子(きょうこ)の医家に生まれ育った四人姉妹に、立て続けに事件が襲いかかる。始まりはあのとき。いや、違う。絡まり合った過去の記憶。あるいは謎の糸口は…。詩人・批評家でもある小原眞紀子の手になる、ノスタルジックでハードボイルドな金魚屋ロマンチック・ミステリ・シリーズ第5弾!
by 小原眞紀子
第六幕(前編)
夾子宅から戻るタクシーの中で、文彦は資料のコピーを見続けていた。
逮捕の知らせを受け、わたしたちはすぐに家を出てタクシーを拾った。
妹の住む2DKは、バス通りを十五分ほど行ったところにある。
車を降り、暗い砂利道を踏んで近づくと、一階の角部屋の二つの窓に灯りが見えた。
出てきた夾子は虚ろな目をし、アンサンブルのスーツ姿でアップの髪は崩れんばかりだった。病院から戻り、着替えもまだのところを踏み込まれたらしい。身柄を拘束させまいと抵抗したのか、ダイニングの椅子はあちこち向き、奥の畳の間に書類や衣服が散乱していた。
「別件だって、別件逮捕なのよ」
夾子は相当に取り乱していた。人権派で名の通った玉井弁護士には、さっき電話で連絡したと言う。
「先生が今、警察に抗議を。たった一シートの精神安定剤の窃盗なんて、アネクチンの線が、いくら弱いからって」
逮捕。
帰りのタクシーの中で、再びその言葉は重く覆い被さってくる。
わたしにも起こり得るのか。
損害賠償、つまり金の話だけでは済まないことが。
「ミュンヒハウゼン、か」
我が家の玄関の鍵を回しながら、文彦は呟き、頭を振る。
夾子の部屋には、数年前のわたしの脚本のコピーがあった。彼の任意の取り調べの際に、警察から渡されたのだという。
「そんなこと、どうして黙ってたんだ。ミュンなんとか人格障害ってのは、何なんだ」
夫は畳に仁王立ちで夾子を睨みつけた。
日頃から夾子を甘ったれと決めつけ、厳しく接してきた文彦に、妹は震え上がった。
「余計な心配をさせたくなくて、」夾子はか細い声で答えた。
「警察はあれこれ揺さぶりをかけてくるからって、弁護士の先生も」
ネットで調べたという資料を、妹は箱から出してきた。
「ミュンヒハウゼン症候群。演技性人格障害の一種で、医療関係者による殺人事件の動機形成がそれに当てはまると言われる」
演技性。
医療関係。
わたしの芝居と彼の逮捕は、これで結びつけられるのか。
「今日びの警察ってのは、頭が短絡した馬鹿ばっかりじゃないか」
夫は夾子を怒鳴りつけた。
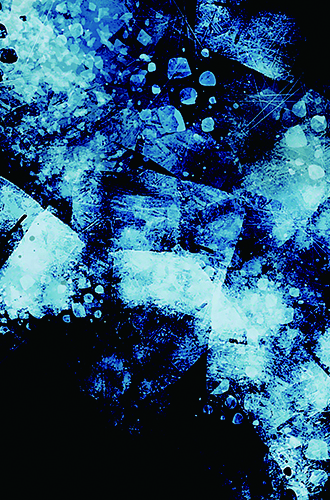
「今日びに限らず、警察ってのはそういうものだって」
震える声で夾子は言い、文彦の剣幕に怯えつつ別の資料を渡した。
「米国でナースが児童の患者に劇物を注射した。自ら異変を発見して、患者をドラマチックに救ったのが典型例。ほかに、母親がわざと我が子を傷つけて病院に駆け込んで、医者の前で献身的な母を演じるとか」
「その医者に気があったのか?」
そうじゃなくて、と夾子は疲れ果てた声で続きを読む。
「独身時代には自傷して、悲劇のヒロインとして数回受診し、」
「そんなことが楡木子の脚本と、いったい何の関係がある」
勢いあまってか、夫は夾子の頭を小突いた。
「ト書きに、人を殺せとでも書いてあるのか!」
ないわよ、と、その手を振り払い、夾子は顔を覆った。
「だけど警察は、専門家にも見せたって。忠くんも姉さんも、ミュンヒハウゼン型性格傾向が強いって。でも、そんな専門家の分析なんて、各々違うものだって、玉井先生もおっしゃったわよ!」
リビングの照明を点けると、テーブルはまだ冷酒の瓶や寿司桶が並んだままの状態だった。
数時間前、同窓会よろしく岐波を接待していたのが、呑気の極みだったように思えた。
ソファにかけた途端、文彦は笑い出した。
「ほら吹き男爵、ねえ」
ミュンヒハウゼンとは「ほら吹き男爵の冒険」に出てくる男爵の名だと、夾子は言った。物語の名にし負う、同じ性格の真田とわたしが意気投合した、というのが警察の推測らしかった。
彼は病院で患者に毒物を注射し、わたしは美希に問題を起こさせることで人々の注目を浴びようとしていた。たまたま陽平が死に、美希は病院に隔離されたことで、わたしの影響を脱し、真実を語りはじめた、と。
各々の件に互いが関わっていたか、すなわち物心両面での相互幇助があったことを証明できるかどうか、現在、捜査中という。
理不尽だった。
まるでナンセンスな夢に放り込まれたみたいだった。
もとよりフィクションは、わずかな事実と恣意的な関係性で出来ているものだ。だが警察が創り出すストーリーは、同じフィクションでありながら、現実そのものとして扱われるのだ。

そんなことがまかり通っている社会を、わたしはずいぶんと無条件に信用していたものだ。自分では十分、懐疑的で皮肉な人間だと思いながら。
「大学にまで手をまわして、脚本を入手したなんて」
劇研顧問の教授は、なんと思ったことか。
そんな世間体の類は些末なことに違いなかったが、まだしも日常的な現実感がある。ただ現実にしがみつきたいがために、わたしはむしろそんなことで、自ら絶望的な気分に追い込まれようとしていた。
が、夫は再び笑い出し、わたしはさらなる悪夢へと踏み込むような感覚に陥っていた。
文彦はしかし、自棄になっていたわけではなかった。
翌朝、テレビと新聞は、准看護師が僅かな薬剤の窃盗容疑で逮捕されたという事実を伝えていた。もっとも未成年なので、顔や名前は出ない。
コメントとして、「近頃、医療ミスも疑われる不審死が相次いでいるという訴えもある」と、何事かを匂わせるのみだった。
その日、演劇教室は出席者ゼロだった。もはや陽平の件だけでなく、真田の逮捕との関わりも噂になっている、と肌で感じられた。
時間はあり余っていたが、夕飯を作る気にはなれなかった。
「聖清会病院は、かなりの負債を抱えているらしい」
岐波の事務所から戻り、夫は言った。
今朝早く連絡した岐波弁護士は、昼過ぎには、その情報をもたらしてくれていた。
缶詰のブイヤベースを啜りながら、「やっぱり最大手だけのことはある。人脈も情報量も圧倒的だよ」と、文彦は気を引き立てるように感心してみせた。
だが、今回は運がよかったというべきだろう。
岐波の事務所で見習い中の新人弁護士の父親が、聖清会病院で長く外科部長を勤め、先頃クリニックを開業した医者だったのだ。
「あの病院なら、そのうち潰れるって、パパが」
事務所でテレビを見ていて、そう言い出した彼女を、岐波はすぐさまパパのクリニックへ走らせた。
「でも、大きな病院は、今はどこだって経営が苦しいのよ」
わたしは文彦に言った。
缶入りのブイヤベースは、何だか金属臭がする。
学会でも高名な佐武院長は月子の九大医学部の先輩で、妻の院長代理は同級生だった。熊本から出てきた夾子は、そのツテで聖清会病院に勤めることになったのだ。
「あそこは最先端医療の研究治療もやっていて、それが大赤字だって、夾子も前から言ってたわ」
「いや。もともとの負債の原因は研究事業でなく、投資の失敗だ」

学究肌の院長をよそに、不動産事業に乗り出したのは三和子院長代理だったという。副院長でない「代理」の肩書きも、その便宜のためらしい。そして不動産の含み損が膨らんだ後、むしろそれを糊塗するかのように、骨髄液電気分解術を導入した。
「さらなる設備投資を負ってまで、なぜと思うだろう。だが、脳障害からくる運動機能改善の地域研究認定というのを受けて、県から多大な補助金を得たらしいよ」
「まさか、それ目当て、ってこと? 認定なんて取り消しになるわよ」
そうだ、と文彦は頷いた。
「治療成績が芳しくなく、研究の実体が尻すぼみとなれば、研究費は出なくなる」
研究予算の獲得は、大学に勤める文彦にとっても身近な苦労のはずだ。
「新人弁護士のパパは外科部長として、研究体制や実績のねつ造を強要された、と言っている」
「まだ現役の医者が、よくもまあ、そんなことを」
「うん。娘に訊かれて答えただけで、公の場で証言するかどうか。ただ、最初の打ち上げ花火で病院に呼ばれ、研究治療に張り切っていたところが、実際には債務超過の尻拭いに利用された。その憤懣はやるかたないらしい」
打ち上げ花火。
数年前、夾子の就職の際、姿を見かけた三和子院長代理と、その言葉とが重なった。
「最近、老人介護施設を併設したろう? そっちは順調らしいが、病院の方が保たないようだ。とすれば介護事業は別法人にして、計画倒産というシナリオも出来てくる」
「なんですって」と、わたしは訊き返した。
夫は皮肉な笑いを浮かべた。
「看護師ひとりの犯罪で、病院が破産するなり、経営縮小に踏み切るなりしても、不運な事件のせいにすれば補助金の返還は免れる」
すごくドラマチック、とわたしは呟いた。
「岐波さんと、そんな話をしているの?」
「ふん。あの病院の件には、何の興味もないさ」
日焼けした腕で、夫は空いた皿を押しやった。
「ただ、ミュンヒなんとか型性格、とやらで解釈する馬鹿らしさを指摘したいだけだ。この説明なら少なくとも、金銭と名誉の利害という動機がある」
動機。
そんな古色蒼然とした概念が、まだ通用するのだろうか。
「人は単に性格で犯罪を犯すことはない、と思うね。それなりに追いつめられた理由があるはずだ」
そもそもアメリカの特殊ケースを、そのまま当てはめるなんて非常識だ、と文彦は肩をすくめる。
特殊ケース。
非常識。
夫はまだ、真田を十九かそこらの看護師としか認識していない。
彼を見れば、何か尋常でないことが当てはまる、と感じはしないか。
気がつくと、激しく抱き合っていたときの、わたしのように。
「年増とはいえ、女医と看護師が婚約したんだ。夾子の言う通り、」
その言葉に、思わず文彦の顔を見つめた。
「真田くんとやらは、周囲の中傷にさらされたと考えるのが、日本的だろう」
病院の債務超過という情報は、文彦には何か現実的な手応えを与えたようだった。自身のペースを取り戻したように、翌朝は母校の研究室へと出向くと言い出した。
彼が家を出て少し経ってから、わたしはバスで聖清会病院へ向かった。
夾子に一度、怒る夫のいないところで問いただしたかった。
ナースステーションから内線を入れると、昼休みまで中庭で待っていて、と妹は言う。
中庭のベンチから見上げると、空は美しく晴れ上がっていた。
ここ数日、気候のことなど目に入っていなかった。
と、木立ちの向うに、白衣姿が見えた。小太りで、夾子にしては背が低い。女は手を挙げると、急ぎ足でやってきた。
「楡木子さんでしょ? お久しぶり」
院長代理の佐武三和子だった。
「さっきナースステーションで、後ろ姿をお見かけしたの。すぐにわかったわよ、スタイルがいいもの」
三和子は満面の笑みを浮かべ、ベンチの隣りに腰掛けた。

明るい色に染めた髪はくるくるとパーマがかかり、医者というよりもピアニストか何かのようだ。
「夾子さんをご紹介いただいたとき以来ねえ。月子さん、お元気?」
打ち上げ花火。
彼女は万事が要領よ、と姉は陰口を叩いていた。
「このたびは、いろいろと」
挨拶しかけたものの、どう続けるべきか迷った。
「いいえ、こちらこそ」
三和子院長代理は、濃く化粧した目を大きく見開いた。月子の同級生で優秀なはずだが、しゃべり方も蓮っ葉で、どこかふわふわしている。
「いずれはっきりすると思うけど、医療ミスなんかなかったの。もちろん、故殺なんて。だけどスタッフ連中には、警察に余計なことを言うのがいてね」
院長代理の顔から、わたしは一瞬も目を離せなかった。
スタッフ連中には、か。
「真田くんはまだ若いけど、患者さんに人気があってね。特に女性のお年寄りには」
くすりと笑い、意味ありげな視線で見る。
「芝居を使った療法を試したいって、準備を進めてたわ。あなたの出ていた雑誌も、彼から見せてもらった」
この女だ。
そうに違いない。根拠もなく、わたしは直感した。
彼とわたしの接点を、最初に警察に漏らしたのは。
「こちらは、最先端医療の研究に熱心でしたものね」
と、わたしは嫌味を言ったつもりだった。
ええ、と誇らしげに頷く三和子の様子は、以前と少しも変わりない。
万事、要領よ。
月子の言葉が再び思い出された。医学部で力のありそうな男を物色したあげく、今じゃ自分も旦那と同じ技量に見せかけてるのよ。
「帝都大の研究も引き継いだものだから、忙しくて。好女子さんは、どうなさってるの?」
その口振りは明らかに、田舎の産院ごときを大仰に考えたがる好女子を馬鹿にしていた。
「美希ちゃんはここでよく、夾子さんと遊んでるわ。こう言っちゃ失礼だけど、好女子さんの娘にしては可愛らしいわね」
「ええ、まあ。わりと神経質だし」
「あら、だって神経症なんだから」
屈託なげに笑いながら、こちらをじっと観察している。
陽平の転落死についても当然、聞き及んでいるだろう。
「外来の受付、患者さんでいっぱいですね」
わたしは相手に矛先を向けた。
「今のところは、ね」
中庭の植え込み越しに、三和子は病院の玄関前を見やった。
「報道があって以来、入院の方はキャンセルが出てるのよ。総合病院はただでさえ火の車なのに、潰れでもしたらどうしてくれるのかしら」
(第11回 第六幕 前編 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
*『幕間は波のごとく』は毎月03日にアップされます。
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








