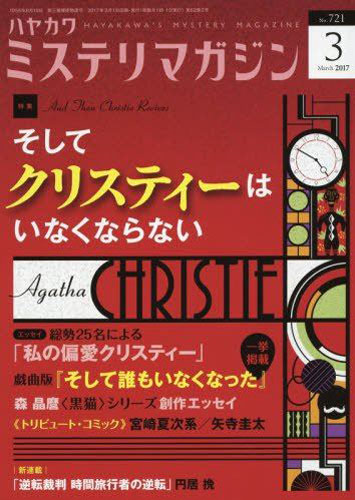
アガサ・クリスティーの特集である。これまで何度となく繰り返されてきたであろうクリスティー特集だが、「そしてクリスティーはいなくならない」というタイトルが付いている。そう、なぜクリスティーはいなくならないのだろう。それはたぶん、ミステリーというジャンルの問題にもかかわる。
そもそも、クリスティーはひとつのジャンルである、とも言える。それはクリスティーという個によって規定されるから、ジャンルとしての発展や継承はない。それでも独立したジャンル性を有するのは、いまだ汲めども尽きぬ謎があるからだ。ミステリーにとっては最高のことだが。
クリスティーに内包される謎とはしかしもちろん、犯人は誰か、というものではない。それは各作品で解かれている通りなのだから。かと言って、たとえばパトリシア・ハイスミスのような人間存在にかかる謎というものでもない。ハイスミスの謎は “ 文学 ” そのものだが、クリスティーの謎はそれとは違う。少なくとも通常の意味で “ 文学的 ” なものではない。だがそれは本当に “ 文学 ” ではないのか。
その問いに答えるには、“ 文学 ” とは何かが再び問われる。逆に言えばクリスティーの文学性を問うことは、各時代の “ 文学 ” の規定に寄与する。もちろんミステリーは常に “ 文学 ” を逆照射してきた。すなわちストーリーはこのように構成されるべきという典型を示し、すなわち “ 文学 ” におけるテクニカル指標を露わにしてきた。そしてすなわち、人の死ほどに重大な出来事はない。
ミステリーが “ 文学 ”に突きつけるものは、この重大な出来事が必ずしも、と言うよりそもそもまったくテーマ性を帯びない、というそのことだ。ミステリーのテーマは人の死ではなく、その死をもたらした仕組みである。これは重大な出来事をそのまま、無意識的かつ無自覚にテーマと重ね合わせて疑わない “ 文学 ” への異議申立てとなり得る。そこで “ 文学 ” が考える重大性とは、感情の起伏の大きさでしかない、と。
つまり、こうである。感情の起伏は意思の力、テキスト的にはスタンスの取り方によって抑え込むことができる。そのときテーマはどうなるのか、と。スタンスの取り方ひとつで消えてなくなるものがテーマであるのか、と。そしてそうならば、“ 文学 ” 的テーマとはそもそも何なのか。
クリスティー作品はさらに抒情性への異議も唱えているように読める、というのが “ 現在 ” あるクリスティーかもしれない。他のミステリー作品同様、クリスティーも乾いているが、乾ききってはいない。抒情的に仕立てようとすればできるだろう、というとば口に立っている。
もちろんそこから先に進みはしないのだが、それは抒情という簡単な手段を当たり前に利用することへの立ち止まりのように映るのだ。場面の脇をちらりと横切っただけのメイドが犯人であったら、ずるい。読者と書き手との間の暗黙のお約束を破っている、という意味でフェアではないだろう。ならば適宜、抒情性を援用し、なんとなく読者を説得してしまうことはフェアなのかという問いが、いなくならずにある。
水野翼
■ アガサ・クリスティーの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




