 イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
早稲田文学新人賞受賞作家にして、趣味は女装の小説ジャンル越境作家、仙田学のラノベ小説!
by 仙田学
エピローグ 饅頭と髪の毛
まだところどころに雪の残る、春先の昼下がりだった。
陽射しは夏のように強く、駅に行き交うひとびとを照らしつけていた。
リュックを背負い、トートバッグを肩にかけ、両手に紙袋を提げた少女は、ひとの流れに何度もぶつかりながら、ホームとホームをつなぐ通路を歩いていた。
特急列車の出る時刻は迫っていた。
ひとりで電車に乗ったことなどそれまでなかった少女には、どこに行けば乗れるのかがわからなかった。
ぐちゃぐちゃになった切符をポケットから取り出し、あたりを見まわしていると、
「お嬢ちゃん、どうしました?」
と声をかけてくる者がいる。
真っ白い髪を刈りこんだ、初老の駅員だった。
目尻のシワの形が、数年前に亡くなった祖父を思い起こさせ、少女は知らず知らず笑顔になっていた。
「親戚の、おばさんの家にいく。あの。ここ」
「ん? ちょっといいかな」
初老の駅員は少女から切符を受け取ると、老眼なのか手をいっぱいに伸ばして顔をしかめた。
「はいはい。あそこの階段降りたところのホームで待ってたら、もうすぐ来るよ」
「ありがとう」
「転ばないでな」
ひょこんと頭をさげると、少女は教えられた方向へ歩きだす。
泣き出す寸前のように、胸いっぱいに詰まって喉のあたりまでこみあげかけていた不安が、少し薄まっていた。
少女は、父親とふたりで暮らしていた家を初めて出て、父親の姉の家に行くところだった。
父親が帰ってこなくなって、一ヶ月が経っていた。
おそらく、もう二度と父親に会えないだろうということが、少女にはわかっていた。

これから一緒に暮らすことになる、父親の姉と、電話口で何度も怒鳴りあっていた父親の声が耳から離れなかった。
――お土産、買うの忘れてた。
おそらく初老の駅員のおかげで気持ちに余裕ができたのか、少女はお土産の準備を忘れていたことを思い出していた。
特急列車の出る時刻までは、ほんの十分ほどしかなかった。
通路の両側には土産物を扱う売店が並んでいたが、どの店にも客がびっしりと集まっていた。
早足になりながら、すぐに買えそうな店を探して歩いていた少女は、とつぜんの衝撃を肩に受けてよろめいた。
「すっすいませんっ。ごめんなさい」
こちらを向いて何度も頭をさげているのは、少女と同じくらいの年恰好の少年だった。
「……大丈夫です」
あまりにも全力で謝ってくる少年が気の毒になり、軽く頭をさげて通りすぎようとすると、
「あの、よかったら、これ」
と少年は手に提げていたビニール袋をひとつ、差し出してきた。
ビニール袋のなかには、紙包みに包まれた箱が入っていた。
乗換駅になっているこの駅のある街の、土産物で有名な饅頭だった。
「いい。そんな」
少女は袋を返そうとしたが、少年は
「大丈夫。まだあるから」
ともう片方の手に提げたビニール袋を揺らしてみせ、またひとつ頭を下げると、慌てたように走っていった。
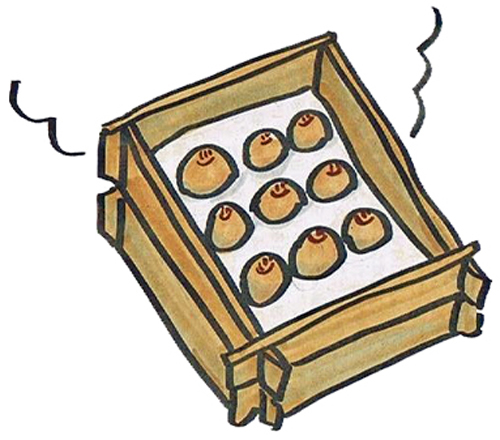
少年が駆け降りていったのは、さきほど初老の駅員に教えられた、少女が乗るのと同じホームへと続く階段だった。
「あ」
あとに続いて階段を降りかけた少女は、目を疑った。
乗るはずだった特急列車が、ちょうどホームから出て行くところだったのだ。
店を探して歩き、少年とやりとりしているうちに、思いのほか時間をとられていたらしい。
力が抜けて手すりにつかまった少女に、階段の下にいる少年の姿が見えた。
少年のそばには両親らしい大人の男女と、ベビーカーに乗った小さな女の子がいた。
すぐ近くにも別の大人の男女がいて、困ったように顔を見合わせている。
――こんだけしかないの? みんなのぶん買ってきなっていったじゃん!
――ごめん、未来、これが最後の一個だったんだよ。おまえが全部食っていいから。
――バカっ! 映一ってほんと使えない。あたしひとりで食べてたら、食い意地が張ってるみたいじゃん!
ものすごい剣幕で少年を責め立てているのは、白金色の髪をきれいに巻いた、フランス人形のような少女だった。
――あれ、先斗町未来じゃない?
――え、誰それ?
――ほら、こないだテレビに出てた。雑誌のモデルやってる小学生の女の子。
――ああ! かわいいな。顔ちっちゃい。でもなんか、性格きつそう……。
すれ違った大学生の男たちの話し声が耳に入ってくる。
少女は、トートバッグのなかからメガネケースを取り出した。
牛乳瓶の底のようなぐるぐるメガネをかける。
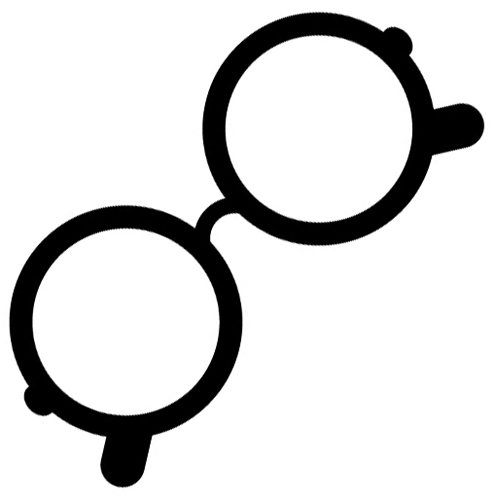
父親がいなくなる前に、一緒に買いにいって選んでくれたものだった。
ピントのあった視界のなかに、少女は少年の姿を焼きつけようと切れ長の目をこらす。
少女の乗り遅れた電車には、少年と白金色の髪の少女とその一行も乗りそびれた。
ホームの売店で売り切れていた饅頭がどうしても食べたいと、白金色の髪の少女がダダをこねたせいだった。
翌日のニュースを見て、少女と少年は、別々の場所でそれぞれ驚くことになる。
少女と少年たちの乗るはずだった特急列車が脱線事故を起こし、膨大な数の死傷者を出していたのだ。
――わたしが生きているのは、彼のおかげだ。彼が饅頭をくれて、電車に乗り遅れさせてくれたからだ。
少女の頭のなかで、その事実は真実になっていった。
――もういちど彼に会えば、きっと、わたしを救ってくれるはず。お父さんと一緒にいたときのような、幸せな暮らしに戻れるはず。でも、そのためには、彼にまた会うためには、わたしは不幸でいなければならない。わたしが彼に出会ったのは、お父さんが出て行ったからなんだから。大嫌いなおばさんと暮らさなければならなくなったからなんだから。
幸せになるためには、不幸でいなければならない。
少女は決意した。
望むものを手に入れようとは決してしないことを。
持てるものをすべて失うことを。
そう。
髪の毛さえも。
(第22回 最終回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 仙田学さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


