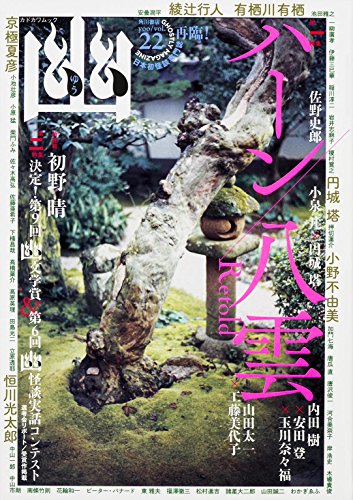小泉八雲ことラフカディオ・ハーンの特集。幽という雑誌であるから、日本文化の紹介者としてのラフカディオ・ハーンというよりは、怪談の小泉八雲について焦点を当てているというわけだが、さて、それはどのくらい違い、あるいは違わないことなのだろうか。
日本文化の紹介者として日本で名が知られた作家のうち、ハーンほど愛されている人はいないのではないか。このような特集を見るにつけ思うが、それはなぜなのだろう。ハーンの日本理解が深かったからなのか。しかし私たちは、自分たちのことをその醜い面や弱い面を含めて完全に把握しているような相手を、煙たく思うことはあっても、それほどには愛さないように思う。
私たちは本当のところ、わざわざ日本にやってきて、ちやほやされる外国人を必ずしも信用してはいない。皆で一緒になってちやほやはするものの、いずれ国に帰るまでの一時のことと思っていて、こんなところにやってくるには本人なりの事情もあるのだろうと考えている。少なくともその事情を知らされれば、なるほどね、と感じるわけだ。
私たちはファー・イースト、極東と呼ばれるところにいる。欧米人からすれば、島流しにでもあうようなものだろう。外国人を歓待し、親切であることにおいて世界でも例を見ない日本人であるが、そのことは心の底でわかっている。私たちがその死後もずっと忘れずに愛惜し続けるのは、私たちを理解し、あるいは理解したつもりで世界に紹介してくれた人ではなく、その彼が日本を切実に必要とした理由が腑に落ちる、そういう人なのではないか。
ハーンはアイルランド人の父とギリシャ人の母の間に生まれ、ダブリンで幼少期を過ごした。すなわちヨーロッパの中枢にいたわけではない彼が向かったところは、いずれも「島」だったという指摘がある。つまり自ら島流しを選んだ生涯であった、ともいえる。
辺境に行き、さらなる辺境を目指す心境が、異界を目指すことと重なり合うなら、それは切実なものとして納得はできる。一方、どんな辺境もそこに住む者たちには現世であるから、彼の見ている「日本」は幻影だ、とは言える。ならば幻滅する瞬間があるのは最初からわかっていて、至極当然である。それは日本の問題でも、彼が日本に抱く愛情の欠落の問題でもない。
また一方で、どんな現世にも異界は顔を覗かせる。小泉八雲にとって、日本における現世と異界のあり様が、生まれ育った場所のそれよりも自分を慰めると思い、それによって生まれ育った土地を離れるほどであったなら、私たちはそれで十分に納得する。彼の事情は事情としても、私たちすべての者にも通じる事情であるからだ。
小泉八雲の怪談は、異界であった日本が現世の生活の場となってからも異界として作用するものであった。それは彼の頭の中の日本であり続けたかもしれないが、必ずしも日本を誤解していたと言えまい。ある種の人間にとっては、異界を現世に近づけることは切実な問題である。たとえばキリスト教が制度として現世化している世界から逃げ出してきた者にとっては、特に。幽の特集、対談のパラダイムは、そのような異界の存在を必然としていたことに意義がある。
水野翼
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■