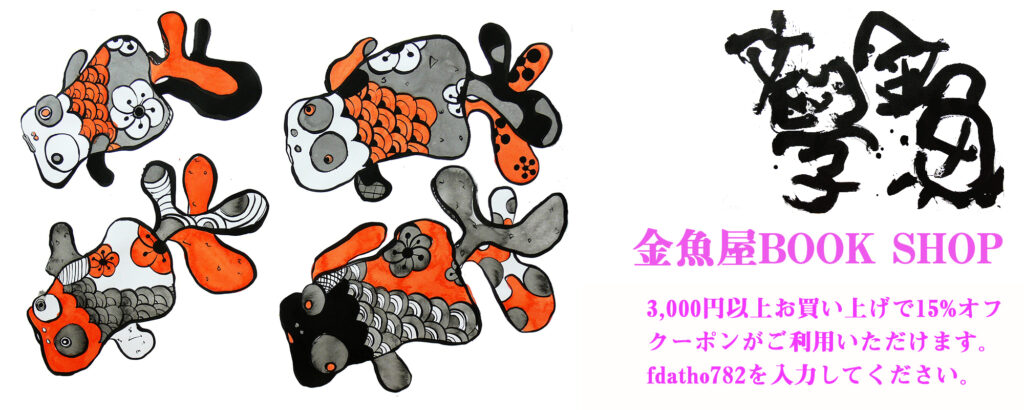日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
女たちの話は歌の講釈に及び、源氏が先だって一束の朝顔(牽牛花または西洋昼顔のことです)に添えて桃園(桃の果樹園のことです)の姫宮に贈った歌を取り沙汰して当障のないことを言うので、口吻に似合った当らず障らずの女振りであればいいけど、思い描いた通りの見た目に見えるとは限らないものだし、と源氏はすっかり興も醒め、元の座に引き返しました。
まもなくして紀伊守が入ってきました。果物を差し入れ、灯芯をかき立てて、ようやく主客相揃ってくつろげるようになりました。
「女房らはどうした。男所帯では華がない」と源氏は見回します。
「生憎うちにはお気に召すようなのは」と紀伊守は呟き、源氏が何を気にしているのかわかっていない様子です。
部屋には紀伊守の後に続いて入ってきた男子らも座していました。みな紀伊守の弟や子供です。そのうちの十二か三ばかりの子の顔立ちが目を惹きました。源氏にとっては当然見ず知らずの者たちなので一人ずつ紹介を求め、先の子の番となり、紀伊守が答えるには、
「これは亡き衛門督の末の子です、孤児となってからは姉の縁を頼む形で、うちに置いております。才に秀でた子で宮仕えを所望しておりますが、後ろ楯の宛てがないのです」
「難儀だな。ではその姉というのが継母の」
「さようです」
「良き母と縁づいたものだ。上様の仰るのを聞いたことがある、娘を宮に上げたいと亡き父君から伺いを立てられていたのだろうね、あの娘はどうしたかと気にかけておられた。来ているのだろう」そう問うなり源氏は声をひそめて、「世の中浮きつ沈みつでままならないものだ」
「かくして母ともなりましたが、元より望んだ形でなかったことはお察しいただけましょう。まことこの世の浮きつ沈みつでままならぬ、とりわけ女性というものは」
「伊予殿のご寵愛は。氏神様のように奉っておいでかな」
「さあ、どうだか、頭は上がらないようですが。父親が現を抜かすのを見て一等面白くないのは倅ですから」
「そうかね。しかし父親の真心には妻子の隔てもあるまいよ。良い父を持ったね。しかし姿が見えないな」
「みな部屋に下げておりますから」
そろそろ外してもらいたいと言いたそうな源氏の素ぶりを見て、紀伊守は子供らとともに部屋を出ました。お供はみな酒を聞召入れて夢見心地、ひやりと涼しい茣蓙筵に寝そべり、心地よく寝入っております。
源氏はついに一人きり。寝ようにも寝付けず、夜は更け、静まり返っておりました。身も心も冴え冴えとし、ここから一つ間を挟んだ部屋に人の気配を感じます、あるいはそこに件の奥方が寝ているのではないか。徐に立ち上がって部屋の端まで行き聞き耳を立てます。幼い声が聞こえたのは先ほどの子君のか、今しがた部屋を訪ねたらしい、

「おりますか」
この問いかけに女の声が答えました、ここに、どうしたの、お客様はお休みになったの、さらに言い加えて、
「こんなにお近づきになっても遠くにおられるのですもの」
「さようですね、たいそうな美丈夫でしたよ、噂に違わぬ」
「明るいうちなら一目見られたでしょうに」と眠たげな女の声。
「では休みます。頼りない灯りだ」と小君の声、灯をかき立てているらしい。
女は手を鳴らして侍女を呼び、「中将はどこ、なんだか寂しい、呼んでおいで」
「浴(ゆあみ)聞召にお出でです、じきに戻ります」と侍女。
部屋に行ってみようか、良くないか、いや却って、と独りごちつつ、源氏が襖の留め金を引き抜きますと、外からは掛かっていなかったので、開きました。女の臥している部屋の入り口は几帳が立ててあるだけで、燈がちらちらと漏れています。葛籠や懸守などの散らばるのが仄見えるのを手探りに押し分けて几帳のほうへ進みます。茵にもたれかかった小柄でかわいらしい女の姿が見えました、しかし女のほうは気がつきもせず、呼びにやった中将の気配と思っているようです。源氏は心細くなるのを堪えて口を開き、女をぎょっとさせました、
「中将を呼んでおられたので、我がことかと思い、御身に仕え奉らんと参りました」
思いもよらない出来事に、女はわけもわからぬといった顔。
「それはそうだ」と源氏が続けます、「厚かましいことと驚いておいででしょう、そこはどうかご勘弁を。これも偏に真の思いに駆られてのこと、こんな機でもなければ前々より抱いていた敬愛の情をお示しできないと」
いついかなる場でも何をどう話すべきかわかってしまう機転の持ち主です、かような文句を並べ立てる口吻のきわめて恭しく愛想も良く、鬼さえ手懐けてしまえるのではないかというほどで、女の怒りも引っ込んでしまいました。しかしそれでも源氏の遣り口を訝しみ、気を悪くしてもおりましたから、消え入るような声で言い返します、「思い違いをなさっておいでかと」
いや決して、と源氏が応じます、「思い違いではない。それに怖がらせるつもりもないのです。ただこんな嫌な夜ですから、話し相手になっていただければありがたいと思って」そして優しく女の手を取り、背中を押して独寝の客間へと踵を返すのでした。
(第17回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■