 世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
世の中には男と女がいて、愛のあるセックスと愛のないセックスを繰り返していて、セックスは秘め事で、でも俺とあんたはそんな日常に飽き飽きしながら毎日をやり過ごしているんだから、本当にあばかれるべきなのは恥ずかしいセックスではなくて俺、それともあんたの秘密、それとも俺とあんたの何も隠すことのない関係の残酷なのか・・・。辻原登奨励小説賞受賞作家寅間心閑の連載小説第四弾!。
by 寅間心閑
四十五、ブレーキ
確かにカチッと鳴ったその音をごまかそうと、目元口元に力を入れながら「何?」と尋ねてみる。何気ない風を装ったつもりだが、あまり自信はない。何しろ俺は、家から神保町まで歩いたばかり。久々にしてはキツめの運動のせいで疲れている。多分、表情をコントロールするほどの力は残っていない。
「店長の奥さん、別れるかもしれないって言ってました」
「店長と?」
「はい」
興味がないからあまり驚かない。目の前の安藤さんには「どの口が言ってんだよ」とツッコみたかったが、疲れているので神妙な顔をして軽く頷いた。
「あと」
「あと?」
「このお店なんですけど、しばらくは奥さんが店長の代わりをやるそうです」
それは聞き捨てならない話だ。仕事が、というか金が絡んでくる。でも今あの人、俺には何も言わなかったけど――。そんな感情のざわつきを見逃さない安藤さんは、何かの合図みたいに瞬きを繰り返す。でも思い当たることは、ない。単に俺の反応を待っているだけだろう。
「その話っていつ……」
「えーっと、それはちょっと長くなるんで、店が終わった後に話します。今日は忙しいですか?」
首を軽く横に振る。「すいませーん」と客がレジの前に立ち、安藤さんは「はい、お待たせいたしました」と眩しい笑顔で対応した。首振りは「忙しくないよ」という意味だったけどちゃんと伝わってるかな。
店を手伝ってあげたい気持ちはあるけど、今は少し休みたい。俺は神保町まで歩いただけでなく、美味しいオムライスも食べた。つまり眠い。できれば今すぐ横になりたい。一度家に帰ってから出直そうかと思ったが、安藤さんはそれも見逃さない。客にテキパキと試着室の位置を教えてから、バックヤードで休むことを提案してくれた。
「大丈夫ですよ、さっき掃除したばかりなんで」
比べるまでもなく寝心地がいいのは明らかに自分の家だが、今すぐに休めるというシンプルな魅力には抗えない。俺は本が入った袋を掬い上げ、昨日ひとりで宴を開いていたバックヤードへと舞い戻った。最初十分くらいは机に突っ伏していたが、どうにも眠りきれない。結局靴を脱いで床に寝そべることにした。やはり身体を伸ばすとずいぶん楽で、二、三度大きな欠伸をした後、ストンと眠ることが出来た。
深い睡眠のあと特有の身体が空っぽになる感覚と、蛍光灯の眩しさが居場所を分からなくしている。そんな寝ぼけっぷりを直したのは安藤さんの綺麗な顔だった。
「身体、痛くないですか?」
「うん、今何時?」
「もう店閉めました」
え、と大きな声が出る。それでは足りず安藤さんに「閉めたの?マジで?」と訊いてみると、「よく寝てましたからねえ」と笑われた。昨日も寝過ぎてしまったし、どうやらこのバックヤードは睡眠に最適な環境らしい。

「もう少し早く起きてくれたら中華街、連れてって欲しかったんですけど」
「ん?」
「ああ、もしかしたら覚えてないです? 店長たちが別れるかもって話」
少しずつ空っぽになったスペースが元に戻っていく。覚えてる覚えてる、と答えながらゆっくりと上半身を起こした。エアコンはつけていたのに額が汗ばんでいる。
「汗、かいてます?」
「うん、ここ来る前に結構歩いたしね」
「シャワー浴びに行きましょうか?」
すっと安藤さんが腰を落として顔が近くなる。まだ空っぽが完治しないから「シャワー?」と情けない返事しか出来ない。最後に俺の家でした時は、全然我慢出来なくてすぐに終わっちゃったんだよな。
「シャワー浴びたいですよね? ホテル行きましょうか? それか私の家でもいいですけど」
こういう時に平静を装うのは難しい。でもリセット、リフォーム、リフレッシュした俺はそんなことで悩んだりしない。ただ素のままに反応するだけ、今は小さな声で相槌を打つだけだ。
「……うん」
「家に帰るなら私も一緒に行きます」
「……」
「嘘です。でもその代わり、シャワーも浴びれません。私、汗の匂いとか嗅ぐの、好きなんですよ」
促されるまま服を脱ぎ、あっという間に下着だけになる。最後の方は前のめりだった。だからこうしてトランクスからはみ出ている。その先端にぺっとりと安藤さんが指先で触れる。そして軽く何度か押す。
「店の鍵は大丈夫? 閉めた?」
それには答えず、親指と人差し指の輪っかを先端にはめてゆっくり動かす安藤さん。馬鹿みたいに気持ちいい。ようやく「鍵、開いてますよ」と答えると、微笑みながら素早く指をしゃぶって輪っかを作り直した。はめ直して、しごき直して、また指をしゃぶり直す。それを何度も繰り返すからベトベトになるし、トランクスは用無しになって邪魔になって脚をバタつかせたら簡単に脱げた。
「この間、ずっとスマホをつないで音を聞いてたじゃないですか。あれ、ずっと聞いてたんじゃなくて、気が向いたらみたいな感じだったんですけど、それでもかなり聞いてたんです」
小声で喋りながら一枚一枚脱いで、すぐに俺よりも裸になる。目を合わせようとしないから返事はしない。こんなに明るい場所だから見たことのある形なのに、頭がおかしくなる程いやらしくて、本当にリセット、リフォーム、リフレッシュ出来たのかと不安になってくる。
「留守電もちゃんと聞きました」
「?」
「奥さんが連絡欲しがってる、ってヤツです。なんかいつもと声が違ったから、ちょっと……怖かったです」
照れ笑いで俺の身体を跨ぐ安藤さん。人差し指と中指でグイっと下着をずらし、露出した場所にベトベトを挿し込もうと腰を落とす。俺も体勢を微調整して協力するが突っかかる。向こうがまだ湿りきっていない。
「あれ……、もう、あれ……、ダメ……?」
無理にでも挿し込もうと、先の方を摘みながら腰をくねらせている姿はいやらしくて、じっと見ているとそれだけで暴発しそうになる。「あれ……、あれ……」と焦った顔で小刻みに動かし続けていたが、ようやく諦めたらしい。「ちょっと待って下さいね」と跨いだまま膝で後ずさりをして、俺の股間にその綺麗な顔をゆっくり埋めた。もちろん口いっぱいに頬張っている。その気持ち良さに流されないよう、軽く身体を仰け反らせて抵抗するがあまり効果は期待できない。
「ちょっとストップ……ねえ、ちょっと」
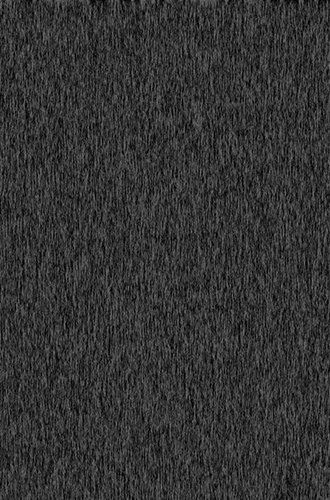
ぐっと右腕を伸ばし髪に触れると、頬張ったままの彼女と目が合った。そのアンバランスな眺めに思わず声が出る。目を逸らし天井を眺めてやり過ごそうとしても、ねっとり舌をまとわらせたり、軽く歯を立てたりして追ってくるから、思わず身体ごと逃げた。
肘を使ってじりじり逃げながら考えているのは、どこで捕まろうかということ。別に本気で逃げたいわけじゃない。最高のタイミングで挿し込んで、一ミリの隙間もないくらいギチギチにしてやるつもりだ。きっとそれは向こうも同じで、互いの呼吸を一致させるのに必要なのは身体だけ。頭や言葉はブレーキだから、こういう時に使ってもうまくはいかない。
気付けば安藤さんは頬張るのをやめていた。首を大袈裟に振りながら、ピンク色の舌で何度も形をなぞっている。俺も逃げるのは止めて、その必死な様子を凝視した。
この不自然な積極性には理由があるはずだ。心の底から愛している人は店長だと気付いて混乱しているのかもしれないし、その対象が俺だったというパターンかもしれない。長くスマホを繋いでいた時に思うことがあってもおかしくないし、店長の奥さんに対して共感し始めた可能性もある。でもこんな風に根元までベトベトにする理由は、そういう話とは遠く離れたところにある。本当はそんなもの、ないのかもしれない。
「そろそろ大丈夫じゃない?」と訊く代わりに、髪を乱暴に掴んで火照った身体を引っ張り上げる。左胸に思いきり吸いつきながら、親指以外の指で大丈夫かどうかを確認した。
「もういけるよ?」
返事がないから四本の指をもっと奥まで突っ込んでみる。「なあ?」と震わすと「しよっか」と虚ろな声が返ってくる。「なあ」「しよっか」「なあ」「しよっか」「なあ」「しよっか」。繰り返す中で俺たちは簡単に繋がった。最高のタイミングだったかどうかは分からないが、分からないならきっと良い線のはずだ。
何の抵抗もなく挿し込んで、少しでも動かす度に彼女は千切れんばかりに首を振り、ぐううと低く唸ったまま俺の腕に何度も噛みついた。変わったのかな、と思う。この間、家でした時もトウコさんの名前を呼ばなかった。理由があるなら知りたいが、自分から訊くほどではない。やめやめ、そんなこと考えてるとブレーキがかかっちまうぞ。
腰を振るように頼むと、安藤さんは背筋を伸ばして言う通りに動いてくれた。綺麗な腹筋と縦長のヘソを見ながら、俺はひとりで処理する時みたいに自分のペースで済まそうとしている。
「このままでいい?」
「え? え? 何?」
「そろそろヤバそうだけど、このままで大丈夫か?」
「もう終わり?」
ギリギリ大丈夫、と答えると彼女は目を閉じたまま「じゃあ、見ていたいから口にして」とせがんだ。俺の返事を待たずにさっきの姿勢に戻り、手の平で自分のべちゃべちゃを拭ってから口いっぱいに頬張ってみせる。その顔を見れるならいつでも大丈夫。そう告げると視線を合わせたまま照れ臭そうな表情を作り、数秒もしないうちに綺麗な顔は汚されていた。
指で集めて口に入れている安藤さんに「鍵、本当に開いてる?」と尋ねてみると、返事の代わりに舌を出し、濁った白を見せてくれた。大丈夫、この調子ならすぐに出来るようになる。柔らかいのはこの一瞬だけだ。

「あの人のことは本当?」
「あの人?」
「セラピストの」
ああ奥さんね、と笑ってもう一度舌を出す。そのままのピンク色。濁った白はもう残っていない。
「あれは半分嘘、かな」
起き上がった安藤さんは、俺の左肩に頭を置いて添い寝の形にした。
「半分?」
「嘘をついたのは私じゃないですよ。奥さんの方。まあ、本人は嘘をつくつもりはないと思うけど、結果的には嘘になっちゃう感じかな」
店長の代わりを務めるのは本当だろうけど、離婚をほのめかしていたのは自分に対しての当てつけではないかと安藤さんは思っていた。
「だって毎日病院に行ってるんですよ? 絶対別れないと思います」
ゆっくりと顔をこっちに向けた後、俺の脇の匂いを嗅いで「いい感じに臭いですね」と深く息を吸い込んだ。
「で、あの人が店長代理ってことは、これから毎日来るようになるの?」
「さあ、どうですかねえ。本業もあるから、毎日は来れないでしょう?」
「セラピストって忙しいのかな?」
「さあ……」
「っていうか、セラピストって何?」
うーん、と考え始めた安藤さんに覆い被さる。今度は俺が上。セラピストだか何だか知らないが、従来どおりにやらせてくれるなら何の問題もない。彼女の股間に顔を埋めながら同意を求めると、「退院してくるまでじゃないですか」と体をよじらせる。
「何か言われた? 店長とのこと」
「言われたっていうか……」
聞き出すために舌を尖らせてつついたり、前歯で軽く噛んで引っ張ったりしてみる。安藤さんは途切れ途切れの声で「謝られました」と答えた。
「謝る?」
「色々迷惑かけたって。もちろん本音じゃないから、何か変な感じで……。だってそもそも……」
それ以上聞くとダメになりそうだから、予定より早めに繋がった。やっぱり頭と言葉はブレーキだ。今は邪魔なだけ。そこからはただ裏返したり、立たせたり、言われるがままに嗅がせたりして、俺たちは互いの身体を確かめ続けた。
結局立ったまま二度目が済んだ。安藤さんは机に両腕をつけ、俺はそんな彼女の腰を持ったまましばらく動けなかった。長く歩いたこともあり、とにかく脚がつらい。そのまま膝を曲げて床に座ると、汗ばんだ顔で安藤さんが振り返る。
「大丈夫ですか?」
「ああ、ごめん。ちょっと脚が疲れちゃって」
そんな感じはしなかったんですけど、と笑ってからペットボトルのお茶を飲み「はい」と手渡してくれた。ぬるい液体が喉を潤し胃に落ちていく。
「この前、スマホをずっと繋いでた時、彼女さんとしてましたよね?」
「うん? ああ、そう……かな」
「全部じゃないけど聞いてました。あれ、私のこと忘れてんのかなあ、とか、私が聞いてるからあえてなのかなあ、とか色々考えながら」
安藤さんの顔を見上げると、さっきわざと乱暴に掴んだり叩いたりしたお尻がある。自分があの時、どんなつもりでナオとしていたかは思い出せない。覚えているのはしたことだけ。そして早めに終わったことだけだ。

「覚えてますか? お風呂に入った後に、私に向かって『もしもし』って言ってくれたでしょ? あの時、聞いてたんですよ。だからすごいびっくりして、思わず返事しちゃいそうでした」
すればよかったのに、という代わりに手を伸ばしてお尻を触る。冷たくて気持ちいい。
「あの後、誰か家に来ましたよね? あれ、私じゃないですからね?」
だいたい誰かは分かってるから大丈夫だよ、という思いを込めてお尻以外の場所も撫で回す。
「絶対疑われてるんだろうなあって思ってました」
よいしょ、と弾みをつけて立ち上がる。さっきと同じように大きく足を開かせてから宛てがい、腰を持ちながらじりじりと挿し入れる。
「本当は私のこと、疑ってたんでしょ? ねえ、私のこと、ねえ……!」
ねえねえ、と安藤さんは喘ぎ、俺は無言で華奢な背中に唇を這わせ続けた。お尻と同じで冷たくて気持ちいい。口の中がカラカラなのに止められない。そういえばさっきから、ちっとも時間を気にしてないけど大丈夫かな。まあ止めたくなったら頭や言葉を使えばいいんだ。それまでは安藤さんとこうしてていいんだ。
(第45回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『助平ども』は毎月07日に更新されます。
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■






