 イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
早稲田文学新人賞受賞作家にして、趣味は女装の小説ジャンル越境作家、仙田学のラノベ小説!
by 仙田学
第八章 俺の妹が救助犬で幼馴染みが千手観音で超絶美白天使がセスナをハイジャックしててスキンヘッドの美少女が掌底の名手で全体的にカオスすぎる件(前編)
どれほどの時間がかかったのか、覚えていない。
おれは羊歯をおぶって、ボロボロの橋げたを踏みしめ、吹雪に大きくたわむ吊り橋を、向こう岸まで渡りきったのだった。
「……見えた」
「えっ?」
「見えた!」
羊歯がおれの耳もとで声を張りあげた。
顔をあげると、さきほどの光が、さらに近く、大きく見えていた。
おれは羊歯を背負ったまま一歩一歩踏みしめるようにして光へ近づいていく。
やがて吹きつける雪の向こうにぼんやり浮かびあがってきたのは、灰色の建物だった。
「……どう見ても、ホテルじゃないよな」
「たぶん」
宿泊先のホテルとは似ても似つかない、簡素な二階建ての山小屋だ。
入り口を探して壁沿いに半周ほどしたところで、羊歯がおれの袖を引き、上のほうを指さした。二階の窓のひとつに、ぼんやりと明かりが灯っている。
「すいませ―――――ん!!! 助けてくださ――――い! ひとが遭難してま―――す!」
声を枯らしてしばらく叫んだが反応はなかった。

なおも小屋のまわりをうろついていると、また羊歯がおれの袖を引く。
裏口にあるガレージのシャッターの、下がわずかに開いていた。
「すいませ―――――ん!! すいませ―――――――んっ、誰かいませんか――――?!」
シャッターの隙間に向かっておれは怒鳴りまくったが、反応がない。
「おじゃまします」
ひとことつぶやいたかと思うと、羊歯がするりとシャッターの奥に消えた。
「お、おい勝手に」
繋いだままの手を引っぱられ、おれも一緒に滑りこむ。
なかは三センチ先も見えないほどの闇に覆われていた。
それでも風と雪から遮断されたおかげで体温が戻り、おれたちは息をついた。
「しばらくここで、雪が弱まるのを待つしかないな」
「弱まらなかったら?」
闇に慣れてきた目に、羊歯の白い顔が浮かびあがった。
携帯電話は持ってきていなかった。
誰かと連絡を取る手段はなかった。
「とにかく、待つしかない」
口にしたとたん、おれの腹が勢いよく鳴った。
そろそろ夕食の時間か。おれは腹時計から逆算した。
ホテルをでたのが午後の早い時間だったから、かれこれ数時間もさまよっていたことになる。
「待ってて」
羊歯はおれの手を握ったまま、中腰になり、そろそろと動きだした。
「おいおい、どこ行くんだ」
「おかしい」
「なにが」
「ここ、ガレージなのに、車がない」
いわれてみれば、どう見てもガレージスペースなのに、それらしきものはない。
慣れてきた目に入ってくるものは、雑多な箱や角材やタイヤや灯油の缶などばかり。
「物置に使ってんじゃないのか」
「じゃああのひとたち、どうやって来た?」
二階の明かりが点いていた部屋にいるひとたちのことを羊歯はいっているらしい。
さきほど小屋のまわりを一周したときにも、車の影はなかった。
たしかに、車なしに住むには不便極まりないところだ。
「池王子みたいにセスナで移動してたりして。ははは。それか、いま出かけてんじゃ……」
おれの発言をガン無視して、羊歯は壁沿いにガレージ内を進んでいく。
「あっ」
ギィ―――――――ッッ…………。
低い悲鳴のような音がたち、かび臭く生暖かい空気が頬をくすぐった。
ドアノブを握りながら、羊歯は黒い瞳をおれに向け、唾を飲みこむ。
小屋の裏口の扉らしかった。
「すいませぇ――――ん」
真っ暗な廊下の奥へ恐る恐る声をかけてみるが、声は闇のなかに吸いこまれていった。
一拍おいて、とつぜん明かりが点き、おれは叫びそうになる。
壁のスイッチを押していたのは羊歯だった。
「おい、勝手に点けて……」
羊歯の顔を見ておれは絶句した。
切れ長の目をいっぱいに見開き、顔は真っ赤に染まっている。
色を失った唇は細かく震えていた。
「どした? あ」
返事も返さず、羊歯は手を振り払った。
おれははじめて、ホテルをでてからずっと羊歯と手を繋ぎ続けていたことに思いあたった。
それにしても今日の羊歯はヘンだ。また赤い顔をして。やっぱり熱でもあんじゃ?
バッチ――――――ン!!
またもや掌底をくらったおれは、鼻血を吹き出す。
振り返りもせず、羊歯は廊下を進んでいった。
なんだあいつは。ひとの顔見るたび顔赤くして殴りかかってくるって。
おれの顔に放送禁止用語でも書いてあんのかよ。おれは顔をさすりながらついていく。
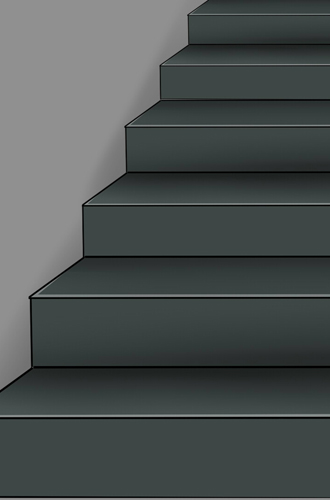
突きあたりの階段を昇ると、両側にいくつか扉が並んでいた。
そのうちのひとつから、くぐもった話し声が聞こえてきた。
――やった! 助かった。
これでおれらも、未来たちも助かる。
すぐに救助隊を呼んでもらって、チャッキーたちにも連絡してもらおう!
できればメシ的なものかなんか、施してもらったりなんかしちゃったりして……。
「近い! 近いってばイケチン!」
「しょうがねーだろ。おまえがやれっていったんじゃねーか」
「痛っ。なにすんの!」
ドアノブに手をかけたまま、おれは羊歯と顔を見あわせた。
未来と池王子の声だ!
安心感とともに、あんな奴らにも安心感を感じられる自分への驚きも感じる。
ドアを開けようとしたおれの手を、羊歯が押さえた。
軽く首を振ってみせると、羊歯は少し離れた柱の陰までおれを引っぱっていく。
――邪魔しちゃダメ。
けげんな顔をしたおれに、羊歯はいい放った。
邪魔って……いちおうおれらみんなまとめて遭難してるんじゃ……?
だがそんな疑問は、ふたりのやりとりに跡形もなく粉砕されていく。
「そーっとだよ。優しくしてね」
「ああ……こうか?」
「あっ。あぁーん。やっ」
「ここはどうだ?」
「あふっ。や、やめてイケチン」
「じゃあやめようか」
「あん。やめないで」
――……なっ……。
おれの目はおそらく、ビー玉のように真ん円になっていただろう。
なーにをやっとんじゃ、あいつらはっっ!
気がつけば、おれはドアの前に立ち、ふたたびノブを掴んでいた。
そのおれの手を、またもや羊歯が掴んでいる。
羊歯の手を振り切って、おれはドアを開けた。
「無理だって。こんな絡まってんだし」
「そこをなんとかするのが男でしょ。とくにあんたナル男なんだし」
「意味わかんねえし。おれナル男じゃねえし」
部屋の奥で、未来は床に座っていた。
その背後から覆いかぶさるように池王子は膝を突き、両手を伸ばして、未来の……髪をいじっていた。
未来の髪は。
「ぶふっっ」
勢いよく吹きだしかけたおれの口を、羊歯の小さな手がふさぐ。
もう片ほうの手の人さし指を、羊歯が自分の口の前で立てなければ、おれは大口を開けて笑い転げていただろう。
未来の髪は、ひとことでいうと、鳥の巣になっていた。

それも、オオワシの一群を数十羽は住まわせられそうな。
柔らかな白金色の髪はうねうねと大蛇のようにとぐろを巻き、四方八方へとその先端を伸ばし、千手観音の腕のように、後光のように、未来の頭をふちどっていたのだ。
その背後で、ブラシを手に右往左往しているのは池王子だった。
どうやら髪を梳かせと命じられたらしい。
おれにはすぐにわかった。
癖の強い未来の髪は、湿気を帯びるとうねりにうねりまくる。
そのたびにブラシやアイロンで整えてやるのはおれのミッションだった。
未来がモデル活動をはじめた小学生の頃から、髪の手入れは一任されてきたのだ。
――そうじゃねえって! そんな力任せにやっても……。
思わずおれが立ちあがりかけたとき。
ガタンッッッッッ!!!!!
「いまなんか音がしなかったか」
「えっわかんない。誰か帰ってきた?」
「気のせいか。そんなふうでもないな。ネズミかも」
「ちょっと! あんた見てきなよ!」
「やだよ。おれ虫だけは超苦手なんだって」
「ネズミは虫じゃないし。爬虫類だし」
爬虫類でもないぞ。
おれが動かしかけた口を、羊歯のひんやりとした手が覆う。
おれと羊歯が身をひそめているのは、ピアノの裏側だった。
ドアを開けてすぐのところに据えつけてあるグランドピアノの裏側は、ふたりのいる奥からだとちょうど死角にあたる。
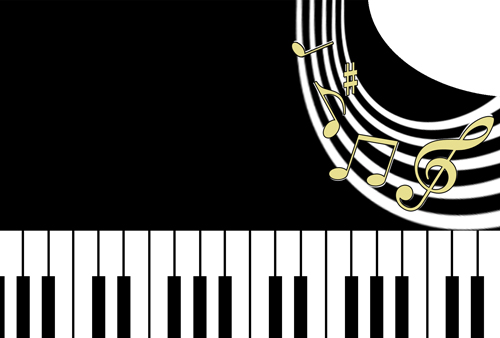
邪魔をしないように、との羊歯のいいつけに、とりあえずおれは従った。
そんなことを気にしてる場あいでもない気がするんだが。
「だいたいここ、ひと住んでんのかよ」
「だってこんなに家具あんだよ。電気だって通ってるし、鍵だって開いてたし」
「でも、ひとの気配がないんだよな。車もないし。車もなしに暮らせないぞ。こんなとこで」
「あんたみたいにセスナで移動してたりして。あはは」
「面白くねえし。こないだニュースで見たんだけどさ、このへんでヒグマが出たらしいぞ。もしかして、この家のひとたち……」
「ちょっとやめなさい! あんたそれ以上いったら」
ギ――――――ッ、ギ、ギ、ギ、ギ―――――ッ!!!
「ひえ―――――っっ」
「おわぁぁぁぁぁぁぁぁっっっ」
未来と池王子が声をそろえて絶叫した。
おれの横でも、羊歯が大きく息を飲み、腕にしがみついてくるのがわかった。
断末魔のようなふたりの絶叫のすさまじさに、おれの全身に鳥肌が立った。
羊歯の肩に手をまわしたまま、おれは立ちあがろうとするが、腰にちからが入らない。
グランドピアノの向こう側で、絶叫したはずのふたりは静まり返ってしまっている。
胸騒ぎと焦りから、おれはグランドピアノの陰から首を伸ばす。
窓べりでふたりは腰を落とし、左のほうを向いて固まっていた。
左の奥にも、もう一枚ドアがあるらしく、さきほどの音はそのドアの開いた音らしかった。
ドアのあるらしきあたりから、かすかに聞こえてきたのは、荒い息遣いだった。
まるで、飢えた獣のような。
――ヒグマ?
おれは未来のもとへ駆け寄ろうとするが、凍りついたように体が動かない。
十七年間、たいていのことからおまえを守ってきたけど、今回ばかりは。
それでも全力を振り絞ってピアノの陰から首を伸ばしてみると、荒い息遣いの主は、
真っ白い獣だった。
(第20回 了)
* 『ツルツルちゃん 2巻』は毎月04日と21日に更新されます。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 仙田学さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


