 イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
イケメンチンドン屋の、その名も池王子珍太郎がパラシュート使って空から俺の学校に転校してきた。クラスのアイドル兎実さんは秒殺でイケチンに夢中。俺の幼なじみの未来もイケチンに夢中、なのか? そんでイケチンの好みの女の子は? あ、俺は誰に恋してるんだっけ。そんでツルツルちゃんてだぁれ?。
早稲田文学新人賞受賞作家にして、趣味は女装の小説ジャンル越境作家、仙田学のラノベ小説!
by 仙田学
第七章 吊り橋の手塚様(中)
「ちょっとあんた、近い! 近いってば!」
「しょうがねえだろ、勝手に進んでくんだから。お。お」
「危ないって!」
池王子は、未来の前に倒れこんだ。
よけ損ねた未来も、スキー板を絡ませて派手に転ぶ。
「んも――――――っっっ! なんだよいったい!」
「すっすまん」
仰向けに雪に埋もれたまま両手をばたつかせている池王子を、おれは掘り起こしてやりにいく。
「ゃんぃけくん、いまの倒れかたなんてゅぅの? かっこよかったぁ★」
「いーしゃんいーしゃん、だいじょぶ? おのれイケチンめぇ~」
兎実さんとつなが、ふたりのほうへ駆け寄ろうとする。
両腕を広げて阻止したのは羊歯だった。
「起きあがるのも練習だから」
嫌がっていたはずなのに、池王子はおれの提案に乗り、わざわざ未来に頭をさげてまで、スキーの手ほどきを頼みにいったのだった。
鼻で笑ってとりあわなかった未来だが、おれがあいだに入り、ホテルのロビーで売っていたバター飴を差し入れするからと条件をだすと、しぶしぶ頷いた。
ふくれてみせる兎実さん。
プロレスの練習をしていると勘違いしているのか、ヤジを飛ばしまくるつな。
やきもきしながら見守るおれと羊歯。
ギャラリーを前に、かれこれ一時間以上も練習をしていたが、池王子はいっこうに上達しなかった。
「もお無理! ふらりんに教えてもらえばいいじゃん」
「マァマァマァ。とりあえず起きあがりかただけでも教えてやれよ」
「映一、あんたが面倒みなよ。もうやだ」
「いーしゃん!」
「つなちゃん、ちょっとお兄ちゃんと一緒にいて。すぐ戻ってくるからね」
羊歯の計画では、この特訓で未来と池王子を急接近させるはずだった。
だがどう控えめに見積もっても真逆の効果しか生んでいない。

おれたちの予想を大きく下まわって池王子のスキー技術が未熟すぎたことがその原因だった。
「落ち着け未来。こいつが滑れないと、おれらの班は大会でれなくなるかもなんだよ。午後から見てるだけなんてつまんないだろ。あははは。ウニの干物も差し入れるからさ」
おれは未来のスキーウェアの袖に取り縋る。
その手を未来は勢いよく振り払った。
「トイレ!! ホテルどっち?」
おれが口を開く前に、羊歯がずい、と一歩踏みだし、指さした。
「あっち」
「戻ってくるから。ホタテの干物もだよ!」
いい捨てると、未来は手早くスキー板を外し、歩きだした。
「……?」
おれは羊歯の顔を窺った。
羊歯の示したのは、ホテルとは正反対の方角だったのだ。
「ぃけくん雪遊びしてんの? ちっちゃぃ子みたぃでかわぃぃ♪」
にじり寄っていく兎実さんから逃れるように、池王子はよろめきながら立ちあがった。
「ま、円山、あとで覚えとけよ」
「おい、どこ行くんだ」
「服んなかまで雪と汗でびっしょりだ。着替えてくる」
池王子は、未来の歩き去った方角へ足を踏みだした。

「あ。そっちは」
逆方向だぞ、しかも未来と同じ……と忠告しかけ、おれは口を閉じる。
池王子にすりゃ、未来と一緒にいなければ羊歯に襲われることもないんだし、ここにいてもしょうがないよな。
結果的に未来と池王子がふたりきりになれたなら、おれらの狙いは達成したことになるんだし、まあいいか。
「ふぁ~~」
桜貝のような唇を開いて大あくびをしたのは兎実さんだ。
「ぃけくん行っちゃったぁ。こぅしてても時間もったぃなぃし、映一くん、つなちゃん、羊歯ちゃん、滑りぃこーょ★」
兎実さんがいきなり、おれの腕に手を添えてきた!
三日月形の目も弾けるような笑顔も、向けられているのはおれにだけ。
尾てい骨のあたりから脊髄にかけて、むず痒く甘ったるくうずいた。
心拍数がメーターを振り切って上昇していく。
あたりの空気も春の陽だまりのように暖かくなり、どこからともなく桃の香りが漂ってきた。

兎実さんに腕を引かれ、おれはてリフトのほうへ進んでいった。
肩越しに振り返ると、つなの手を引きながら歩いてくる羊歯の姿が見えた。
――ありがとうな、羊歯。
おれの笑いかけた表情が見えなかったのか。
羊歯の顔は、いまにも泣きだしそうに歪んでいた。
ロビーに集まった生徒たちのあいだから、いっせいにどよめきがあがった。
――午後からのクラス対抗スキー大会は、中止になりました。
丸い顔を汗でテカらせながら、校長が語った内容に、だが異をとなえる者は誰もいなかった。
窓の外には猛吹雪が吹き荒れていた。
晴れ渡っていた空が、午後になるやいなや、どす黒い雲に覆われだしたのだ。
スキー大会の三十分前には、大荒れの天候に変わっていた。
「ほひ―――――っ」
誰よりも大きなため息をついたのは、御殿場なたねだった。
頭のてっぺんから足の先まで真っピンクのスキーウェアにつつまれた、赤ちゃんのようないでたちだ。
「先生しかたない。こんな天気じゃ外にでた瞬間に雪ダルマだ」
なたねの肩を抱き、なぐさめているのはロドリゲスだった。
全開のチャックを隠してやりもしないところから、内心の動揺が窺える。

「ちぇー。網走まで軟禁されにきただけかよ」
「写真、刑務所の前でしか撮ってないじゃん」
ちらほらあがった不満の声も、すぐに沈静化した。
それほど、吹雪の勢いはすさまじかった。
窓ガラスはいまにも割れそうに激しく揺れている。
地鳴りのような風の音が真っ暗な空を引き裂いていた。
「ふら様!! 素晴らしい! 神です神っ」
ロビーの端であがったのは、蛸錦の叫び声だった。
間髪を入れずシャッター音が鳴り響く。
真っ赤なビロードのカーテンの前で、スポットライトを浴びているかのように輝いているのは。兎実さんの姿だった。
ツインテールに結ばれた、つやつやの長い黒髪。
大ぶりの猫耳ティアラ。
淡いピンク色のエプロン。
胸もとや裾はたっぷりとしたレースやフリルでふちどられている。
数ヶ月ぶりに見たメイド服姿の兎実さんは、以前より桁違いにゴージャスさを増していた。
観音さまやマリアさまや、その他もろもろの女神さまたちが束になってもかなわないほどの、神々しさを醸しだしていた。
一瞬にして、生徒たちの輪の中心は校長から兎実さんに移動した。
「うおおおおお! まさかのサプライズ!」
「ふらちゃんこっち向いてぇ!」
「やーん、ふらちゃん超かわいー!! 一緒に写メ撮ろーよっ」
野郎どものみならず、女子たちまでロビーの一角に殺到した。
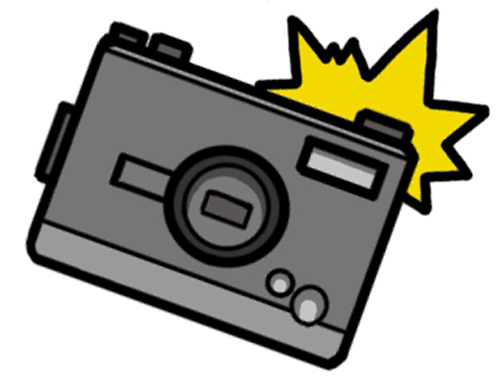
「ゃぁん恥ずかしぃ★そんな見なぃで」
わざわざ部屋でメイド服に着替えてきて、見ないで、もないもんだ。
だが、そんな辻褄を気にしているおれのほうがおかしく思えるほど、兎実さんの魅力は破壊的だった。
「これを眼福といわずして日本人たりえるや? ふら様! 目線を! 目線をくださいっ」
「タコくんったらぁ~ふら、撮影に来たんじゃなぃんだょ?」
兎実さんは、蛸錦自慢の一眼レフに向かって、上目遣いで顎ピースを決めてみせる。
「といいますと、ふら様?!」
蛸錦もまた、寸秒たりとも手を止めずにシャッターを切り続ける。
「さっき管理人さんに聞ぃたんだけど、ここにカラォケあんだょ★ぉ天気よくなぃし、こんな日はみんなで歌ぉぅょ♪」
壁のスイッチを兎実さんは押した。
コントの舞台のように壁が回転し、カラオケセットが出現した。
「修学旅行の思ぃ出作ろっ★」
小首をかしげながら、兎実さんはカラオケの装置をいじり、音量ツマミを最大へまわす。
爆音で流れだしたのは、先週のチャートで一位になったばかりのアイドルソングだった。
「ワン、ツー、スリー、渚の~♪」
満面の笑みで、兎実さんは近くの女子の手を引いた。
戸惑っていた女子も、兎実さんにつられて歌いだす。
完璧な振り付けでステップを踏む兎実さんを中心に、ひとり、またひとりと、からだを揺らしながら歌いはじめた。
たちまちロビーはクラブと化し、爆音と歌声と足音と笑い声が充満した。

兎実さんと目があったおれも、輪のなかへ飛びこもうとしたが、小さな手に引き止められた。
――なに遊んでんの! あたしはずーっとイケチンの相手して疲れたの!
「すまん未来っ、肩でも揉もうか」
愛想笑いを浮かべて振り向いたおれの顔の鼻先にあったのは、未来の顔ではなかった。
抜けるように白い肌の、華奢な体つきの美少女がそこにいた。
豊かな長い黒髪は、頭の高い位置でポニーテールに結ばれている。
切れ長の目が、こちらをまっすぐに見つめていた。
大きな黒い瞳は、ガラスのように透明だ。
白く滑らかな肌は、外国人の少女のもののようだった。
……美しすぎる。
高山植物のような気品に満ちた美しさだ。
話しかけるのもはばかられる、それ以前に目をあわせるのもためらわれるオーラを放っていた。おれの胸は一気に高鳴り、心臓から押しだされた血潮に顔が真っ赤に染まるのがわかった。
兎実さんを前にしたときとはまた違う、胸の高まりが感じられた。
同時に、胸が詰まるような懐かしさを掻きたてられた。
五年も前から知っている兎実さんよりも、十七年も一緒にいる未来よりも、はるかに懐かしい安心感に、おれはすっぽり包みこまれていたのだ。
「あのふたり、まだ戻ってきてない」
「あ、あの……えっ?」
おれは耳を疑った。
美少女の唇から発されたのは、聞き覚えのありすぎる声だったのだ。
「早く。こっち」
おれの手を引いたまま、少女は歩きだした。
大音声でシャウトしている兎実さんたちは、美少女の存在に気づいている様子がない。
ロビーの端からひと気のない廊下へでると、少女は引き結んでいた唇を緩め、ため息をついた。
「私のせいだ。探してくる」
「あ! 羊……歯……?」
並んで立つとちょうど肩のあたりにくる顔のほっそりとした輪郭は、見まがいようがなく羊歯のものだった。
ぐるぐるメガネを外して、ウィッグをつけ替えた羊歯?!
メガネ外して髪型変えたら美少女って! いつの時代のマンガだよ。
ってかなんで? なんでこのタイミングでメガネ外してんの?
おれの頭のなかでは数えきれないほどの疑問が竜巻のように渦巻きはじめた。
一緒にウィッグを買いにいったとき、別のウィッグをつけた羊歯を見たことを、おれはすっかり忘れていた。
「だから、待ってて。心配いらない」
羊歯は唇を歪めてみせると、おれに背を向けた。
おれの疑問にひとかけらのヒントも与えずに去っていこうとする羊歯の腕を、今度はおれが掴んでいた。
「ま、待てよ、わけわかんねえよ。なんだよいったい」
思えば、羊歯はいつだってそうだった。
兎実さんの手帳を書き換えろと未来に迫られたとき。
とつぜんおれに近づいてきて、本当の兎実さんの姿を暴くのを手伝ってくれた。
未来が兎実さんの髪を剃ろうとしたとき。
気がつけばそばにいて、すべてを知っていた。
兎実さんと未来が通り魔剃毛活動に乗りだしたとき。
みずからスキンヘッドになって活動を辞めさせた。
未来や兎実さんもかなりなもんだが、それを遥かに超えて読めないのが羊歯の言動だった。

「先斗町未来と池王子珍太郎が、まだ戻ってない」
顔を背けたまま、羊歯はつぶやいた。
「だから、なんで……えっ?」
「先斗町未来はともかく、池王子珍太郎まで方向音痴だったなんて」
「え。え―――――――っっ! あいつらまだ戻ってないの?」
「さっきからそういってる」
窓の外で、吹雪の音がいっそう激しくなった。
壁や天井も軋みだしている。
「えらいこっちゃ!! すぐ警察に。いや消防署か?」
「どっちも近くにはない。救助隊が来るまで時間がかかりすぎる。私が行ったほうが早い」
黒い瞳でほんの一瞬だけおれを見据えたかと思うと、羊歯はふたたび背を向けた。
おれはまた、自分が自分から抜けでていってしまうような、奇妙な感覚に襲われた。
いつだって、未来のそばにいて、未来のために動くのはおれだった。
これじゃまるで、羊歯がおれになったみたいじゃないか?
「待てよ。おれが行く」
おれの手は、羊歯の腕を強く掴み直していた。
(第18回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
* 『ツルツルちゃん 2巻』は毎月04日と21日に更新されます。
■ 仙田学さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■


