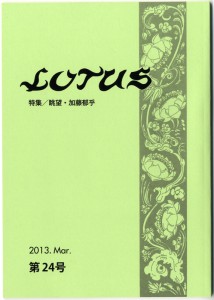金魚屋では新たに『金魚詩壇』というコンテンツを設け、短歌・俳句・自由詩の作品と批評を掲載していきます。その第一弾として、俳句同人誌『LOTUS』の皆さんに、『俳壇ってなに?』というテーマで討議をしていただきました。俳句界は外側から眺めているとなかなかわかりくにいところがあります。結社制など俳句特有の仕組みを、現実に即して理解するための参考にしていただければと思います。
文学金魚編集部
【出席者一覧】
[LOTUS同人]表健太郎/九堂夜想/酒卷英一郞/志賀康/鈴木純一/豊口陽子/吉村毬子
[外部参加者] 佐々木貴子(「陸」所属)/舟(しゅう)/山口可久實(「未定」所属)
[司会] 鶴山裕司
■はじめに■
――――今日はわざわざお集まりいただき大変ありがとうございます。文学金魚というインターネット上の総合文学サイトで、詩部門のアドバイザーをしている鶴山です。金魚屋が昨年十月に開催した『安井浩司『俳句と書』展』では、俳誌『LOTUS』同人の酒卷さん、豊口さん、志賀さん、吉村さんなどに大変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。文学金魚では引き続き俳句文学に注目していきたいのですが、その第一弾として、『俳壇ってなに?』というテーマで俳誌『LOTUS』の皆様にフリートークを行っていただきたいと思います。
簡単に申しますと、俳句の世界は外から見たときと内側から見たときではだいぶ様子が違います。外から見ると俳句は芭蕉や蕪村の文学の世界です。しかし長い目で見れば確かに文学的評価が出るとはいえ、いわゆる俳壇の実態は必ずしも文学そのものを中心には回っていないように思います。また俳句の世界には結社や師弟制度など、他の文学ジャンルには見られない特徴があります。俳人である皆さんには当たり前のことでも、外から見ていると、これはなかなかわかりにくい。そこで今日は、できるだけ俳壇外の人にもわかりやすいように、俳句の世界について語っていただきたいと思います。
酒卷 同人俳誌『豈』と『LOTUS』に所属しております酒卷英一郞です。三行行分け表記の俳句を書いています。それを貫きたいと思っています。
鈴木 鈴木純一です。酒卷さんと同じ『豈』と『LOTUS』に所属しています。
佐々木 佐々木貴子です。私は俳誌『陸』所属でして、『LOTUS』の方は、外部として今年から参加させていただいています。
志賀 『LOTUS』発行人をやっております志賀康です。『LOTUS』をやる前は『未定』にいました。
豊口 豊口陽子です。出発点は小倉緑村主宰の『山河』ですが、転勤族でしたので、引越すたびにその地の同人誌にも入れていただいておりました。東京に戻ってからは『未定』にお誘いいただき一人一派のきびしい現場を体験しました。その後『LOTUS』創刊同人として現在に至っています。安井浩司の弟子です。
表 表健太郎です。九堂さんと一緒に『LOTUS』の編集を担当させていただいています。
吉村 吉村毬子です。中村苑子に十年師事して、その後『未定』に入り、それから『LOTUS』同人になりました。
舟 『LOTUS』は、勉強させていただきたく、参加させていただいています。俳号は諸々ございますが、ここでは舟(しゆう)で参加しています。
山口 山口可久實と申します。俳句を初めて三十年と長いんですけれども、今は『未定』に所属しております。
九堂 『LOTUS』編集ならびに『海程』同人の九堂夜想です。
――――ありがとうございます。早速ですが、『LOTUS』がどういう経緯と理念でお集まりになった雑誌なのか、簡単にご説明いただけますでしょうか。
志賀 最初集まったのは『未定』にいた六人、『豈』から三人ですか。それから新たに九堂さん、表さんという若手が参加されました。創刊のいきさつはちょっと一口では説明しにくいですが、それまでいた結社や同人誌にあきたりない方々が集まったということですかね。今、同人は十三人です。私は十人くらいの同人数がちょうどいいと思っているんですが、経済的にはもう少し同人が増えてくれた方がいいですけれども(笑)。
――――『LOTUS』さんは同人誌でよろしいんですよね。
志賀 ええそうです。
――――俳壇には大きく分けて結社誌と同人誌があります。結社誌の方は主宰がいらっしゃる雑誌で、同人誌は基本的に対等な同人の集まりですよね。志賀さんは同人誌の方がいいですか。
『LOTUS』第24号(最新号)
特集/眺望・加藤郁乎
平成25年(2013年)3月印刷発行
発行人 志賀康
事務局 酒卷英一郞
編集部 表健太郎 九堂夜想
頒価 1000円
問い合わせ先
〒338-0003さいたま市中央区
本町東7-6-11 LOTUS事務局
酒卷英一郞宛
TEL&FAX 048-853-6558
E-mail sakamaki@s5.dion.ne.jp
志賀 いや、結社誌があることを知らなかったんです(笑)。私はまったく素人で俳句を始めましたから、どこにどんな結社があるのか、知らなかったんです。たまたま『未定』という同人誌を見て、そこに入っただけなんです。
――――『未定』さんも同人誌ですが、不思議な雑誌ですよね。どんどん同人の方が入れ替わる(笑)。
志賀 『豈』ができたときに、何人か抜けたのかな。
酒卷 『黄金海岸』が四号で終わっちゃって、『豈』が創刊される頃までにだいぶ同人が入れ替わったんじゃないですか。
志賀 『未定』は自己主張の強い同人の集まりだったからね。同人だけじゃなく、同人誌としての自己主張も強い雑誌だったと思います。ある種の仮想敵を作って闘いをのぞむといった感じでね。『LOTUS』はどうかというと、同人の皆さんの自己主張はかなり強いと思いますが、雑誌としての自己主張はあまりしていないですね。それは『豈』も同じなんじゃないですかね。
■結社誌と同人誌について■
――――詩や小説の同人誌は、ある一定の役割を終えたら解散することが多いですね。典型的なのは若い頃に出す同人誌で、切磋琢磨の期間が終われば空中分解したり、自然廃刊になったりします。ただ俳壇の場合は、ほとんどの方が結社に所属しておられる。同人誌の場合でも、『未定』さんを例にすると、同人が入れ替わりながら続いていく。それにはなにか理由があるんでしょうか。
酒巻 同人誌は本質的には文学運動ですよね。たとえば攝津幸彦さんや坪内稔典さんの『黄金海岸』だとか、加藤郁乎さんが中心になった『Unicorn』だとかありますが、『Unicorn』も四号で廃刊になってしまう。確かに厳密な文学運動として考えれば、同人誌は長続きしないものなのかもしれません。ただ結社と同人誌は全然違うものです。結社は宗匠を頂点とした三角形の構造ですから。結社では宗匠の文学理念――理念をお持ちならということですが――を全員が共有するわけです。同人誌は、宗匠的な求心力を持った同人に率いられている場合もまれにあるけれども、原則として同人は横並びなので、ヒエラルキーは発生しないわけです。
――――『LOTUS』の皆さんの中にも、かつて結社に参加されたり、師とあおぐ俳人の方がいらっしゃる方が多いと思います。結社の宗匠の理念は、どういう形で伝わって、共有されていくんでしょうか。
酒卷 句会や結社誌への投句を通じて、準同人になっていくとかね。
志賀 結社は主宰の方が選句をしますでしょう。しないところもありますが。たいていの結社誌は主宰の目にかなった作品が掲載されるわけです。
酒卷 ちなみに結社誌の同人自選欄というのは、『馬酔木』から始まったらしいですね。
佐々木 地方ですと、まず俳句会をやっていて、それに参加すると、そこで選句をされている方が中央の結社誌につながっていて、そこから自動的に結社に参加するということになることも多いようです。
表健太郎氏
九堂 極端なことを言うと、ある結社誌に投句したり、そこが主催する句会に参加した段階で、暗黙の裡に師弟関係が成り立っているという見方もできるわけですね。投句または句会へ出席する側の思惑とは別に、ある結社を選んでそこへアクションを起こすということが、その結社の人間から見れば、参加する意志があると取られることが多いと思います。たとえば、先ほど志賀さんが「結社誌があることを知らなかった」と仰いましたが、最近ではカルチャーセンターでの俳句教室などの存在で、一般の人でも容易に俳句(界)への参加が可能になりました。そこでの講師は、大体、主宰誌を持つベテラン俳人か、もしくはそこに属する有力同人です。俳句の世界について、何の情報も有していない初心者がそうしたところへ入会し、いろいろ学んでいく中で興味を深め、やがて、そこの講師が関連する俳誌へ参加するといった流れですね。俳句や結社の理念は、そうしたところから少しずつ伝わっていくわけですが、元々、俳句をいわゆる趣味程度にしか考えていない人は、〝理念〟といったお堅いモノを嫌う傾向があると思います。俳句に、そこまで求めてない、と…(笑)。逆に、勉強熱心な人は、自身でいろいろな俳句関連の本を買ったり、ネットで俳句情報を集めたりする、と―。私事ですが、僕の場合でいえば、やはりカルチャーセンターからの流れで俳句教室に入り、そこの講師が『海程』のベテラン同人だったことから『海程』への投句そして句会への参加が始まりました。初期の段階では、僕個人の中に師弟関係というものは希薄だったわけですが、すでに周囲からは、『海程』の会員、金子兜太の弟子と見られていたかも知れません。元々、ヒエラルキーとは無縁の人間ですが、今となっては、僕自身、そうした見られ方を否定しません。批判的ではありますが、今では自分は兜太の弟子だと思っています。師匠を、つまり兜太を認めない弟子っていうのもあり得ると思うんですよ(笑)。批判的継承という意味でね。私見ですが、先生を丸々認める忠実な弟子っていうのは、他でも案外少ないんじゃないでしょうか。それに、批判的継承という意味では、ここにいる方たちは、みな広い意味で子規や虚子、あるいは蕪村、芭蕉の弟子でもあるわけですから。
舟 私は結社誌に長くおりましたが、同人誌は執筆した作品のほぼすべてが活字化されます。でも結社誌は主宰の選がありますから、全部というわけにはいきません。そういうところから、主宰の主張する俳風に沿わないと、どんどん隅の方に追いやられていくということはあると思います。会社の社長さんとか、社会的名士とか、作品以外の力関係というものも、選に微妙な影を落としていたように感じます。
九堂夜想氏
吉村 一般的に言って、結社に入る方は、その主催の先生について俳句をやろうという方が多いと思います。私の場合は、教室に入ってから、中村苑子の句集を読み、彼女に師事した訳です。
基本を踏まえながらも、自由に俳句を作らせてくれましたし、苑子は結社を作らなかった為、三十人程度で和気あいあいとやっていました。
唯、先輩方に先生以外の選者や雑誌への投句はいけないと言われていて、『俳句空間』の同世代の作品を読んで、投句したいな、と、思ったことはありました。
その同世代と、十年後くらいに、そんな話もしたりもしましたが・・・十年間位は、籠の中の鳥だったのでしょう。でも、居心地は、佳かったのです。他の世界を知らないのだから。
十四年前に終刊しましたが、『女性俳句』という伝統ある女性俳誌がありました。昭和二十八年頃から、平成十一年まで続きました。現代では、主婦が自由に旅できますが、女性が家を空けられる時代ではない時に、東西の女流俳人達が集まり、交流し、時には加藤楸邨、山本健吉、西東三鬼などを講師に迎え、当時の女流俳人にとってはなによりの会だったと思います。
創刊当時は、細見綾子、殿村吐莵絲子、野澤節子、加藤千代子、柴田白葉女、等々・・・。私が参加していた頃も錚々たる女流俳人が名を連ねていました。
横山房子、桂信子、鈴木真砂女、等々。全国大会で、「苑子先生のお孫さん?」と言われました。弟子だと話すと、「うちの結社の貴方位の子は、まだこんな大会には連れてこれないわ。」と言われました。私は、一人、若かったのでした。そういった意味では、苑子に可愛がって頂いたと思っています。二十年前は、若手は、前へ出られなかったのです。年功序列でした。
最近は、「新選」シリーズの試みなどもあり、若手がTVや商業誌にも(二十代~四十代)出ていますが、結社に所属していない若手俳人も多いと思います。
九堂 結社誌の場合は、主宰ならびに運営委員が、俳誌や会合など諸々の決定権を担うわけですが、同人誌では、まず俳句に対しての個々の考えが強力(?)にあり、それを活かしつつ、グループとしての編集やイベントを共同でまとめていくといった違いがあると思います。それが悪い方向に転がると、同人一人ひとりの我が強くなって、同人誌の空中分解につながってしまうわけですが(笑)。
表 俳句を始めるにあたって、象徴というか、何か目安になるものがあった方が、それを批判的に見ることができるという面もあるかと思うんです。僕は十九歳の頃に俳句を始めたんですが、祖母が結社誌に所属していたので、そういうところから何となく俳句や俳壇について知るようになった気がします。でも最初は何も知らないので、俳句とは何かと考えたときに、まずは結社で先生と呼ばれる主宰の方の俳句が〝いわゆる俳句〟としてお手本になるわけです。しかしだんだん別の俳人や結社が目に入ってくると、最初に学んだ俳句を中心にして、この俳句の方が自分の好みに合ってるとか、あの結社は面白そうな俳句を書く俳人ばかりがいるとか、俳句を取り巻く環境そのものを批判的に見ることができるようになります。ですから結社誌を経験した後で同人誌を始められる方も大勢いらっしゃると思います。そういう意味では、結社誌や主宰という制度にもそれなりの意味はあると思いますね。
九堂 これは僕の意見ですが、結社誌や同人誌がイコール俳壇というわけではありません。それで今回、文学金魚さんから『俳壇ってなに?』という討議テーマの趣意書をいただいたときに思ったのが、まず『LOTUS』側から文学金魚さんに、俳壇ってどういうところだとお考えになっているのか、お聞きしたいということだったんです。
■俳壇ってなに?■
――――そうなんですね。俳壇の外にいる人間を含めて、誰一人『俳壇ってなに?』という問いに、責任を持って答えられる方はいらっしゃらないんじゃないでしょうか(笑)。事大主義的なことを言うと、明治維新以降の文学は、基本的に個人(インディヴィジュアル)文学です。自我意識文学になっていくわけです。結社は自由詩では北原白秋あたりで消え、小説では硯友社あたりで消滅しています。集団では創作は行わない姿勢が大正時代くらいで定まります。しかし俳句や短歌は、自由詩はもちろん、維新以降に刷新された近代小説よりも歴史が古いですから、違うセオリーを抱えたまま今日まで続いていると思います。『俳壇ってなに?』という問いに答えるのはなかなか難しいと思いますが、なぜ難しいのかを、できる限り明らかにしてみたいと思ったんですね。
佐々木 ツイッターなんかをやっていますと、情報が断片的に流れてきて、前に千野帽子さんという方が内と外ということをすごく主張されていました。内というのは結社に所属したり俳人と自認されている方たちの世界で、外は、俳句を外側から自由に楽しんでいる人たちの世界です。その内側の世界に俳壇というものが含まれるんじゃないですかね。外の人から見て、ちょっと理解できないようなルールとかのことですけど。
酒巻 今佐々木さんがおっしゃった内と外というのは、社会学でいうゲマインシャフトとかゲゼルシャフトに相当すると思います。結社は一見、閉じた世界に見え、同人誌は開かれた世界に見えますが、外から見れば、いずれも閉じた世界であるということになりかねません。結論から言うと、俳壇というのは共同幻想じゃないかと思うんだな。
九堂 そうですね。俳壇、歌壇、詩壇、文壇という言葉はありますが、それは実体的なものではないし、誰もそれを明確に定義付けることはできない。たとえば、どの分野にも〝精神的支柱〟といった存在があるかと思うんですが、それは大抵、カリスマ性のある一個人か少数精鋭の組織体といったもので、この場合は周囲の人たちが自らの要請としてそれを欲し、畏敬の念を向け、また信奉したりもしますよね。だから「壇」というのとはチョット違うかも知れない。個人的には「壇」というと、何となく権力的なキナ臭さが引っ掛かって、そうした存在とは極力関わりたくないんですが、まあコトバの綾ですけど「俳句界」というと、多少は権力臭も薄れて、また漠然とではあれ「壇」よりも具体的に受け取れる気はします。
酒卷英一郞氏
酒卷 ただ詩壇、文壇では、確かに結社は大正時代くらいで解体しています。でも俳句は座の文芸です。連歌、連句から来て、連衆によってになわれてきたジャンルです。そのあたりが詩壇、文壇とは違うでしょうね。
表 俳壇を厳密に定義しようとすると、詩壇、文壇というものが、はたして現在でも明確に存続しているのか、疑問な部分もありますよね。〝壇〟というものは、〝文学〟とイコールではないわけです。
――――蓮見重彦さんが、『文壇があるなら見せてくれ』とおっしゃったことがありましたね(笑)。まったくそのとおりですが、小説文壇ではマーケットを探りながら、売れる小説を出版していくというシステムが、かろうじて維持されていると思います。文芸誌の新人賞をもらって、何年も苦労して書き続けて、ようやく芥川賞の受賞にこぎ着けるという流れがあるわけです。それが文壇なのだと言えば、まさしくそうかもしれない。そういう苦労をされている作家さんたちから見れば、文壇が存在しないという言説は、もしかするとたわごとかもしれないわけです(笑)。俳壇に話を戻しますと、たとえばある結社が五百人、千人の同人を抱えているとします。それは明確なマーケットですよね。その数が主宰俳人の文学的評価に影響するということはないんでしょうか。
酒巻 当然ありますよ。出版社が句集のシリーズなんかを出す時に、当然、売れるかどうか、つまり背景にある結社同人数を考慮すると思います。そういった基準で、選句集などの収録俳人・収録句数が振り分けられているという面はあります。
志賀 俳壇を外から見たときに、一番わかりやすいのは商業雑誌だと思うんですね。でも俳句の商業雑誌は減ってきました。購買者がいなくなってきた。すると商業誌を成り立たせるためには、相当、裾野を拡げる努力をしなければならない。そこで商業誌が何をするかというと、大結社の主宰者や番頭さんなんかを集めて、彼らの言説で仮想の俳句概念を作り上げようとする。できるだけ多くの購買者を集めるために、仮想俳句概念を作ろうとするから大衆的なものになる。掲載されている原稿も、ハウツー物が非常に多いということになってくる。しかしそれだけではいけないんで、俳句とはもっと独自性のある、もっと主張するものがあると考える人は、同人誌なんかに集うんじゃないでしょうか。
吉村 以前は角川『俳句』のほかに、『俳句空間』などの商業誌も出版されていて、そこには明らかな違いがあったんですね。でも『俳句空間』がなくなってしまってから、今、本屋さんに並べられている商業俳句誌は、ほとんど違いのないものになってしまったんです。書いている作家も、内容も、作品も、みな同じようなものになってしまった。多分、同人誌をやってらっしゃる俳人の方で、今の俳句商業誌を毎号ちゃんと読んでいる人は少ないんじゃないでしょうか。
志賀康氏
九堂 ひとつ、決定的にいえるのは、商業的価値と文学的価値は別モノだということですね。他の芸術ジャンルでもそうですが、〝有名〟とか〝売れている〟いうのは、俗にいう一般受けに過ぎないのであって、その段階で、ベテランだろうが若手だろうが、その作家の作品の文学的価値なんぞはタカが知れてるわけです。…っと、少し言い過ぎた感が無きにしも非ずなので急いで付け加えますが(笑)、無論、誰にも知られていないよりは知られている方が良いわけで、問題は知られ方…つまり、どのような人たちにどのように読まれているか、または評価されているか、ということですね。だから、結社マーケットとなれば、何をか言わんやですよ。そこにあるのは、所詮、ひとつの共同体内部における共犯システムに過ぎないんだから。とはいえ、僕はそれを否定はしません。作品の文学的内実と切り離して考える分においては。ただ、各々が属している結社関連の本を買った(買わされた?)ところで、どれほどの人が真面目にそれを読んでいるか…想像しただけで目まいがしますね(笑)。そして、これは、作家(主宰)本人以上に、むしろ読者・鑑賞者側の、あるいは〝取り巻き〟の問題だと思います。
■俳句形式について■
表 これを言うとかなり根幹的な話になってしまうんですが、俳句形式自体の問題が大きく影響しているんじゃないでしょうか。俳句とそれ以外の芸術ジャンルは、そもそも形式的にまったく異なっているように思うんです。短歌、詩、小説、美術なんかは、拡散的な要素をその形式の中に持っている気がします。時代や流行の変化に応じて新たなものを取り込もうとすれば、ある程度は取り込んでいける。じゃあ俳句で、たとえば絵文字がはやっているからそれを使ってみたら上手くいくかというと、なかなか難しい。可能性がゼロとまでは断言できないとしても、あのストイックな型のなかで無理に斬新さを衒おうとすることが果たして俳句にとって有効なのか、僕自身は疑問に思っています。俳句の本質を探る試みとして、あえて新しい方法を採用するということはあるかと思いますが、それもあくまで実験的なもので一時的なものだと思うんですね。つまり色々試してみたとしても、結局そういう種類の新奇さのなかには、俳句の本質は探れない気がしています。だからそういうことをやるなら無理して俳句を選ばずに、もっと可能性のありそうな形式で試せばいいじゃないかということになってしまう。もちろん新しさを取り込むことにはそれなりの意味があります。ただ、それを実験と認識して行うか、そのまま通用すると信じて行うかとでは大きな差があります。俳句の場合、型という抜き差しならぬものがありますから、言ってしまえば自由ではないんですね。なんでもかんでもできるわけではない。何と言ったらいいか、俳句はこの自由に対する劣等感というか不安みたいなものを隠し持っていって、実験しているつもりでもどこかで反発意識のようなものが働き、自ずと型の方へ落とし込まれていく。そう考えていくと、俳句は拡散的な志向よりも、求心的な芸術ジャンルなんじゃないか。先ほど志賀さんがおっしゃっていたように、仮想の俳壇というものは、裾野を拡げるために拡散していく傾向にあるんだけども、そこには俳句形式への問いはないと思うんですね。だから同人誌をやっている方たちなんかは、俳句形式とはなにかという問いを抱えて、求心的になっていかざるを得ない面があるんじゃないでしょうか。
――――そのとおりだと思います。今回、『俳壇ってなに?』という討議をお願いしたのは、俳壇にまだ力があるからです。歌壇、詩壇でこういう討議をやりたいとは、今のところ思いません。俳句人口が増えているのか減っているのかわかりませんが、とにかく詩のジャンルの中では一番活気があります。歌壇、詩壇では、それぞれの形式自体のアイデンティティが、どうも見えにくくなっている状況があります。しかし俳句の形式は固い。皆さん、それぞれのやり方で、一度俳句形式の問題を潜ってから、創作に赴いていらっしゃるように見えるわけです。で、この俳句形式ですが、基盤にあるのは有季定型に見えます。それはどうお考えですか?。
表 少なくとも今の有季定型は表層的な俳句形式だと思うんですね。歳時記があり、季語があるわけですが、多くの季語が、現在では機能していないように思います。つまり俳句形式が有季定型であるということが疑わしくなってくる。じゃあなにが俳句形式なのか、それを議論し合う場が同人誌にはあると思います。そういった過去の有季定型を引きずっているのが、仮想された俳壇なのかな、という気がします。もちろん無季俳句をやっている結社誌もたくさんありますが。
豊口陽子氏
志賀 でも、今、俳壇はほとんど有季定型ですよ。括弧つきの俳壇ですが、そのほとんどが有季定型俳句だと言っていいと思います。有季定型以外の俳句は排除されつつある。しかし有季定型というのは、俳句形式においては一次レベルの形式ですね。そうではなくて、現代詩などにも接点がある、もっとクリエイティブな形式として、表さんは俳句形式を捉えておられるのだと思います。
九堂 伝統的な有季定型で書かれている人たちの多くは、その可能性を突き詰めて考えていないということがあると思いますね。僕は、有季定型もしくは花鳥諷詠を必ずしも表層的な形式とは思わないんですが、世間に流布しているモノを見るとやはり暗澹たる思いにならざるを得ない。まあ〝暗澹〟というよりは〝アクビ〟といった方が正しいですが(笑)。それは作り手と読み手双方の批評精神に関わると思うんです。誰しも、初学の頃は、基本的な有季定型から入ると思うんですが、それなりに批評意識を持っている人は、作句していく中で自ずと何らかのカベや引っ掛かりに突き当たると思うんですね。やはり、そうしたところから徐々にでも自分なりの疑問や批判を差し込んでいかないと…たとえば「季語」にしても、過去には、その前提に疑問を抱いた人たちが「無季俳句」を書いたりしたわけです。今はまた有季定型が大方になってますが、別にそれでもいいんです。作品が良ければ。ただ、見ていると、どうも「季語」の使い方が…「季題諷詠」もいいんですが、ほとんど季語の〝抹殺〟に近いですね(笑)。おおよそ、作品としてはたんに季語の説明に終わっていたり、またはフレーズの有するポエジーを季語でフタするような場合が多いような気がします。志賀さんにしても表さんにしても、それに『LOTUS』の他の作家にしても有季定型俳句を書くんですよ。ただ、句法としてはそれがすべてではないし、さらに言えば、伝統派の方たちの書く上っ面(失礼!)の有季定型俳句とはぜんぜん違うという意識、つまり批評精神はそれぞれ持っているんじゃないでしょうか、一応ね(笑)。
酒巻 さっき志賀さんが商業俳句誌が減ってきているとおっしゃいましたが、実際にはそれなりに新雑誌が創刊されています。しかしかつてのようには発行部数を確保できていません。インターネットは別にして、いわゆる紙媒体の旧来の俳壇ジャーナリズムは弱体化しているんじゃないでしょうか。で、どういうわけか、俳壇ジャーナリズムの弱体化が俳壇全体の弱体化につながっているところがあって、志賀さんが商業俳句誌は有季定型一色になりつつあるとおっしゃいましたが、そういうことも弱体化と連動しているように思います。かつては角川の『俳句』に対して『俳句研究』があって――『俳句研究』自体は戦前からありますから、高柳重信が編集長をつとめていた『俳句研究』ですが――その時代が一番活気があったと思います。重信が『俳句研究』の編集を担当したのは昭和四十三年から亡くなる昭和五十八年までの十五年間、全百八十五册ですが、その目次を見るだけで、いかに『俳句研究』が考え抜かれて刊行されていた雑誌かということがよくわかります。いま『俳句研究』のような雑誌がなくなってしまって、どの雑誌を見ても同じようなものだという状況があります。こういう色分けは非常に片寄っているかもしれませんが、言ってみれば角川『俳句』が俳人協会であり、当時の『俳句研究』が現代俳句協会であるという面があると思います。もちろん財政的バックボーンがあったというわけではないですけどね。ただそういった対立構造が、現在は崩壊してしまっていると思います。崩壊して、すべてが有季定型一色に染まりつつある。逆に言えば、非伝統派が力不足だということでしょうね。
吉村毬子氏
九堂 一部の同人誌を除いては、確かに紙媒体での俳壇ジャーナリズムは衰えてるでしょうね。ただ、刺激的な論なんかは、商業俳句誌ではなく、おもにネット上で書かれているという感じがしますね。ネットの方が個人的な意見を述べやすいですし、突っ込んだ議論もしやすい。まあ、その分、他愛もないネタで盛り上がったり口論になったりすることもあるわけですが…(笑)。ただネットで面白い文章を書いている人でも、商業俳句誌に書くと、編集者サイドからわかりやすい文章を求められるのか、非常につまらないものになってしまう傾向はあります。
佐々木 俳壇の「壇」という言葉に思いを馳せて、なかば私の希望として述べたいことがあります。
それは、俳壇は表現上の討議・討論が正常かつ公正に行われる場所であって欲しい、逆に言うと、そういうことの実現する場所が俳壇と名付けられるものであって欲しい、ということです。
九堂さんも述べたとおり近年、ネットの普及によって個人レベルでの発信が一層容易、可能になり、伴って論が活発になっている現状があると思います。が、一方で、あくまで俳句のうえ、文芸表現としての討議ではなく、個人の人格そのものを巻き込んだ論争、人間的な好き嫌いという低レベルな事態に陥っていることもままあるように見受けられます。
「壇」とは、発言をし、意見を闘わせるために設けられた一段高い場を指すように思われます。イメージとして例えを出しますと、裁判場というのは、双方が立場、席を与えられ、私生活や人格とは一歩離れて、争点についての意見の折衝をやるわけです。
日常生活と混濁してやったらただの諍い、しかし「壇」というのはもっと特別な場であるべきだと思います。
そういった「壇」としての機能を重視し、またそうあって欲しいという希望を込めて、私は「俳壇」とは、大規模であれ小規模であれ、俳句表現について公正にやりとりの成される場のことである、と思います。
九堂 今の佐々木さんの提言は、まさに希望であり、もっと言えば理想論ですよね(笑)。正常かつ公正な〝場〟としての「俳壇」…それが実現されていれば、あるいは文学金魚さんから今回の『俳壇ってなに?』のような討議テーマは出なかったかも知れません。個人的には、「壇」というとやはり何となく円卓を囲んだ〝オエラ方〟の集まりのような幾分古~いイメージを思い浮かべるわけですが(笑)…まあ、それはともかく、やや冷徹な言い方をすると、昔も今もそうした「壇」のような〝場〟というのは言わば〈大きな物語〉に過ぎないんじゃないか…酒卷さんも言われてましたけど、早い話が、幻想ですよね。先ほど文学金魚さんからマーケットの話が出ましたが、マーケットはたんに〝システム〟のひとつであって、マーケット=「壇」であるなら今回のディスカッションはそもそも無意味なわけです。おそらく、そうは思われていないからこそ、今回の問題提起があり、佐々木さんの〝ココロの叫び〟があるわけですが(笑)、さっきの私論に繋げれば、「壇」という〈大きな物語〉が崩壊した後、その役割を引き継ごうとさまざまな「結社誌」や「同人誌」があらわれる。ただ、これも、さらに冷酷な物言いをすれば所詮はそれぞれに〈小さな物語〉であって、やがて同じ崩壊の憂き目にあうわけですね。なので、まあ、できることと言えば、そうですね…まぼろしの「壇」であれ「誌」であれ、または俳句形式であれ自分自身であれ、徹頭徹尾そうした諸々に対して個としての批評的態度を崩さないこと、ですかね。それも、負け戦を覚悟で…(笑)。
佐々木貴子氏
――――「俳壇」でも「俳句界」と呼んでもいいと思いますが、人間の集団である限り、特定個人の意見や思想が無条件で受け入れられることはまずありません。さまざまな批判にさらされるわけです。でもそういった意見の対立が、よりよい文学の表現や探究に結びつくだろうという共通理解があった方がいいですね。俳壇の現実も同じだと思います。たとえば俳句商業誌には驚くほどの数の結社広告が掲載されています。広告代は新聞やファッション誌より安いと思いますが、二百本近いこともあるのでそうとうなものです。当然大クライアント、つまり大結社のなにがしかが多少なりとも雑誌の内容に影響を及ぼすと思います。しかしそのようなシステムはどのジャンルにも存在します。またそういったシステムには功罪あります。日本各地での俳句啓蒙から商業誌の経済基盤に至るまで、大結社の努力がなければ俳句ジャンルへの注目度はグッと下がるでしょうね。俳句界全体が大結社の恩恵を受けているわけです。ただ俳句を愛する多くの人たちが、全肯定でも全否定でもなく、そこまで含めて俳壇というものはある、作家や作品に対する評価が形作られることがあるという現実を直視した方が、より〝公正〟になれるんじゃないでしょうか。大結社が群雄割拠しているのが俳句の世界の特徴であり特殊なところですが、結社や座の意義を文学理論として説明してくださる方がいらっしゃったら、是非お話をお聞きしてみたいなぁ。
酒卷 どの商業俳句雑誌も、雑誌の売り上げだけでは黒字にはなってないんじゃないかな。そこで注目を集め、書き手を集わせて、そこから句集の自費出版につなげるという形で、かろうじて雑誌を維持していると思いますよ。
――――それは詩壇も同じですね。
酒卷 文壇にはまだ重鎮がいるのかもしれませんが、詩壇にはもういませんよね。鮎川信夫あたりが最後かな。俳壇も同じで、かつては高浜虚子のような物凄い人がいたわけだけど、彼がいなくなってから、俳壇そのものの力も弱まっていると思いますけどね。もちろん、虚子以降、何人も重鎮と呼ばれる人の入れ替わりはあったんだけど、虚子ほどではなかったと思います。虚子は最初に結社なんかのシステムを作った人で、功罪はありますが、彼を越えるような業績を残した人はいないかな。
志賀 僕なんかから見ると、高柳重信がいたときといないときでは、大きく違うと思います。政治力を含め、重信が『ホトトギス』に代表される伝統派に対抗する俳壇の要になっていたと思います。その後、重信のやったことを引き継いだ人がいなかったですよね。
酒卷 重信の『俳句評論』、『俳句研究』は、今見てもすごい書き手が書いていますね。
志賀 中身もね。
酒巻 それは『未定』もそうだと思うんですよ。志賀さんは当事者だから、どうかなって仰るかもしれませんが(笑)。メンバーが替わっていますから、第何期とかに分けなければならないと思いますが、志賀さんが参加されていた当時、あるいはその直前当たりが『未定』のピークだったでしょ?。
志賀 わかりません(笑)。僕はピークは最初の十年くらいだと思っていますけどね。僕はいかなったわけだけど。
吉村 山口さんはずっと『未定』ですよね。
山口 そうですね。もう二十年くらいになります。『未定』の創刊は昭和四十三年くらいじゃないでしょうかね。今は九十五号まで出ていますが私は第五十六号くらいからの参加です。当時は、夏石番矢さん、林桂さん、高原耕治さんらがいて。泊まりがけの総会では三人が夜を徹して激しい俳論を戦わせていました。やがて三派に分かれ高原耕治が未定に残り『第二次未定』として高柳重信らの研究会を開催したり・・・多行形式限定の同人誌となっているわけです。
舟氏
■俳句の根幹とは何か■
――――皆さんの中で、有季定型派という方はいらっしゃらないんですか?。
佐々木 私は十代の頃に、人の紹介で自動的に結社に入り、無判断、無批判の状態で俳句を始めました。最初有季定型でしたが、それだけではつまらないので、最近は違いますね。自分の表現したいことを盛る器として俳句に向かうと、有季という概念は非常に疑わしいものなんです。疑いながらもずっと有季という縛りに従っていましたが、有季でない俳句を受け入れる場所がみつかったので、始めてみたわけです。
九堂 有季定型〝派〟―つまり、それを目指して俳句を書いている人は、『LOTUS』にはいないんじゃないかな。
豊口 私がいくつかの雑誌を転々としていた時に、ある方が、「日本語は季語です」とおっしゃった。それを今ちょっと思い出したんですが、日本で生まれている言葉は、何を使っても季語、季を背負っている。そういう発想もあり得るなぁと思ったんです。だから別に有季定型俳句を書こうと思っていなくても、書いたものが有季定型になることはありますよね。ですから、これは季語である、季語でないといった発想は、これから先の人間は外していっていいんじゃないでしょうかね。
酒卷 日本語の言葉はすべて季語だということですか。
豊口 ええ、情緒的な言い方ですけれどね。その時は多分季語の話をしていたんでしょうね。日本語は日本の季を背負っている。「世界は一つ」的発想に逆行しますが、「ことば」は発生した場の土壌を抱えているのではないかと思うのです。この間、句会の折に「言葉にはうぶ毛が生えているでしょう!」と思わず叫んだのも、そういうことにつながります。記号ではないのです。
山口 現代俳句協会の前会長金子兜太氏はシンポジュウムの質問に対し「有季定形以外の句は俳句とは認めない」と一刀両断的なお返事でした。高柳重信は昭和二十八年に現代俳句協会の会員となりそれ以前から、多行形式の無季俳句『蕗子』等があります。『未定』にいると有季定形を忘れてその枠から自分をいかに開放して、独自の世界を作っていくのかが課題であると思うようになります。これはいわゆる「俳壇」から大きく外れていることです。
――――いわゆる前衛派の方たちの中には、仮想敵としての俳句の姿があって、それが権威(オーソリティ)になっているような気がします。このオーソリティを変えようとすると、どうしても前衛俳句になるんですが、一方で、このオーソリティとそれを変えようとする前衛双方に力がないと、俳壇というものは活気がなくなっていく気がするんですね。逆に言えば、外から見ると、オーソリティはあるだろうということにもなる。それを簡単に言うと、有季定型になるんじゃないでしょうか。
酒卷 前衛派にとって有季定型というのは仮想敵かもしれませんが、基本的には相似形で俳句の中に組み込まれているというのが、俳壇だと思うんですよ。自分は俳壇の人間ではないと思っていても、外から見れば、典型的な俳壇の人間だということはあるでしょうね。オーソリティがあって、それに揺さぶりをかけるのが前衛ということになる。また一方で『ホトトギス』系の俳句で言えば、有季定型俳句の深化もあると思います。それがまた、有季定型というか、俳句のオーソリティの根幹を太くしていると思います。前衛にはそういう機能はないような気がするなぁ。反はあくまで反でしかあり得ないようなね。それは前衛の宿命かもしれない。
表 オーソリティに揺さぶりをかけるのが前衛かどうかについては疑問があって、俳句形式の根幹的なものを考えることは、前衛ではなくて、俳句そのものについて考えることだと思います。
酒巻 たとえば俳壇史で不思議なのは、水原秋櫻子が「『自然の真』と『文芸上の真』」を発表して、虚子の『ホトトギス』を離脱し新興俳句の濫觴となるわけだけど、秋櫻子は最終的には俳人協会の会長をつとめるわけでしょう。今、『馬酔木』を前衛俳句だって言う人は誰もいないよね。むしろ『ホトトギス』に並ぶくらいの伝統俳句です。
山口可久實氏
――――俳壇において前衛は一種の差別用語で、メインストリームを外れた変わり者という意味があるかもしれない(笑)。でも前衛を突き詰めていけば、俳句の根幹にたどりつくのは伝統俳句となんら変わらなくて、むしろ新たな視点で俳句の根幹を問うので、俳句に関する思考と表現を押し広げる役割も持っていると思います。
先ほどから俳壇とか有季定型、オーソリティとかいろいろな言葉を使っていますが、それは俳句の根幹の、現実世界と表現世界、思想世界の言い換えとも考えられます。では俳句の根幹とは何かということになる。
たとえば自由詩の詩人が俳句を書くと、非常にオーソドックスなものになります。詩は形式的にも思想的にもなんら制約がない表現ですから、行を切るなら詩を書けばいいので、一行棒書き形式を選ぶことが多い。内容的にも、俳句の根幹的なオーソリティに沿おうとする。問題はやっぱり俳句の根幹とは何かということでしょうね。
表 前衛表現は、俳句が深化していく過程で必要だと思うんですね。一度そういう前衛表現を試して、もう一度中心の方に戻っていくとなったときに、膨らんで収縮する、そういった機能が俳句の中にあると思います。でも詩人の方が書かれる俳句は、どうも拡がっていく方向ばかりに目が向いているという感じがします。
酒卷 僕はその逆で、詩人の書く俳句は、非常に保守的だと思いますね。詩人の作る俳句は、ダメなものが多いです(笑)。
九堂 その場合の保守的というのは、とくに定型慣れしていない書き手が、いわゆる〝俳句的〟なものを目指そうとした時に陥るパターンですよね(笑)。数年前、某中堅俳人が若手俳人を評した言葉に「俳句想望俳句」というのがあるんですが、或る意味、それに相応するんじゃないかと思います。しかし、定型慣れしているはずの作家や詩人、歌人も、いざ俳句となると、どうも、ね…漱石、龍之介は言うに及ばず、たとえば吉岡実や塚本邦雄の句にしても、内容的にフォークソングだったり、或る単語の強調が浮き上がっていたりと、いずれにおいてもあまり感心しません。管見ですが、他ジャンルの殊に不用意な作家は、どうも俳句というものを〝文体〟や〝意味〟でしか考えていないんじゃないか。あと、内容的には近代文学以降の大きな流れである自己表白的なものがほとんどですね。なまじ、コトバを知ってるだけに、ヘタな読者は綺語のハッタリに幻惑されがちですが、よくよく読めば日記レベルのたんなる私事で終わっているものが多いですよ。
吉村 表さんがおっしゃった、膨らんでいく、拡がっていくというのは、俳句として凝縮されていないということでしょう。
表 はい。俳句自体が伸縮するということです。それが、詩を書く方が俳句を作ると、言葉は拡がることだけを目指しているような印象を受けるんです。ただ並べられていくばかりというか。
酒卷 詩人の書く俳句って、言葉が死んでるんだよね。日本語の膠着性をテニオハでせき止めてしまっているような感じね。僕はものすごく現代詩に対するコンプレックスが強いんだけど、やっぱり俳人の書く俳句は違うと思うのは、言語が流動しているんです。詩人の書く俳句は、一個一個の固有名詞は強烈なんだけど、それをテニオハで止めて、べたりと壁に貼り付けた感じなんだな。
表 読んでいて、止まっちゃうんですよね。
酒卷 そうそう。言葉が動いてないんですよ。この決定的な違いってなんなんだろうって、ほんと、昔から不思議に思っています。ところがそれとは別に、文人俳句っていう領域があります。たとえば高橋睦郎さんとか安東次男さんなんかの作品は、立派な文人俳句だと思います。彼らの作品では、言葉がちゃんと動いています。
――――そのとおりですね。なかなか難しい問題だと思いますが、このへんでちょっとお話をまとめていただきたいと思います。志賀さん、どうでしょう。
志賀 まとめる話じゃないよ(笑)。
吉村 じゃあ超前衛俳句を書いておられる鈴木さんに(笑)。
鈴木 僕は俳句は文学だと思っていません。芸能だと思います。芸能の場合は、お三味線でも長唄でも、師匠から習うわけです。でも俳句はそれをしなくてもできちゃう。だからみんな、ヨーロッパの詩なんかと同じだと勘違いしちゃうんだけど、根底にあるのは、古代から続いている芸能の流れがあると思います。だからそこから常に沸いてくるものは、物凄く古いものだと思います。時代遅れだけど、個人の力ではどうしようもないものが、そこに残っちゃっている。そういうふうに思います。
九堂 今の鈴木さんの話に少し絡めれば、以前には「俳句は〝文学〟か〝文芸〟か」というテーマにこだわった時もあったんですが、今はそうした呼称はどうでもよいと思ってますね。むしろ、見るべきは「〈詩〉があるか否か」と。ここでいう〈詩〉も、老子のいう〝道〟のように「コレ!」というふうに指し示せないのが遺憾ですが、少なくとも書き手/読み手の双方の或る固定観念を穿つようなものでないと、僕自身としては納得しかねるものがあります。鈴木さんが、どのレベルで「芸能」を語っておられるかわかりませんが、たんに見るものを予定調和的に楽しませるというだけなら、(その高い技術は認めるにしても)それだけのことですよね。かつて、岡本太郎が縄文土器の持つポテンシャルを見出したように、ときに古拙なモノに見張るべきものを覚えることがあるわけですが、その意味では、古代から続く舞踊や歌謡などの「芸能」には、たしかに根源的なエナジーが秘められていると思います。そして、私的には、〝人間〟という観念に激しく対立するもの―あえて、誤解を恐れず言えば、「戦争」や「天災」あるいは「宇宙」に匹敵するものをこそ〈詩〉と呼びたいわけです。ただ、そうなると、いわゆる人間的な意味での〝楽しみ〟という範疇ではなくなるだろうし、それを“楽しみ”と受け取るには、人間はまだ精神的に幼すぎるでしょう。「幼年期の終わり」を迎えるころには、幾分楽しめる〝オトナ〟になっているかも知れませんが…(笑)。
――――今日は長時間、ありがとうございました。
(2012/12/22)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■