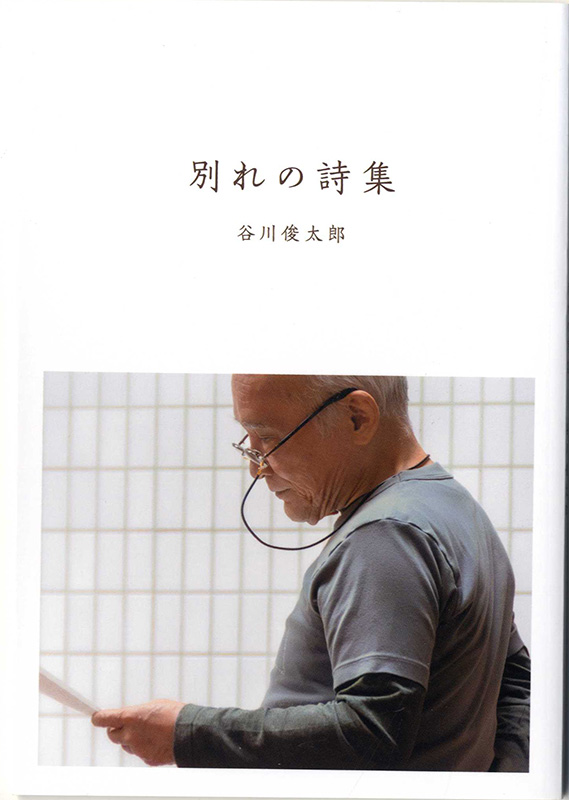
早いもので谷川俊太郎さんがお亡くなりになってから一年が経とうとしている。この間に多くの追悼文が書かれ追悼対談も行われたがどーも気に入らない。お亡くなりになった直後で致し方ない面はあるが薄っぺらい美辞麗句のオンパレードだ。これほど美辞麗句が並んだ詩人がほかにいるだろうか。
俊太郎さんは「悪口言われるの大好き」とおっしゃっていたがそれは本当だったと思う。ただ同人誌「櫂」の仲間で俊太郎さんと最も親しかった詩人たち、茨木のり子さんや大岡信、川崎洋さんらはみなお亡くなりになってしまった。時にボロクソに批判しながら奇妙に仲のよかった寺山修司もとっくに鬼籍に入っている。長寿は大変目出度いことだが儀礼を超えた愛憎入り混じる追悼文を書ける同世代詩人がいないのだ。
文学者は亡くなった時点からその仕事の総括が始まる。テキストは固定されそれを引き継ぐ生者の時間が始まる。その第一歩となるのが追悼文だ。死者の仕事も生者の仕事もそれによって試される。素晴らしい詩人でしたでは何も言ったことにならない。
お亡くなりになったのは二〇二四年十一月十三日だが翌二五年五月十二日に帝国ホテルで「お別れの会」が開かれた。その際、列席者に『別れの詩集』が配られた。死去の間際まで詩を書き続けた詩人にまことに相応しい記念品だった。手元に一冊あるがこれはご子息の谷川賢作さんが金魚屋に贈ってくださったものである。
『別れの詩集』は六十四ページの薄い本で二十篇が収録(再録)されている。詩のセレクトは『谷川俊太郎 絵本★百貨典』などを出版しておられる刈谷政則さん。ご子息の谷川賢作さんによる追悼詩集でもある。この詩集が最も優れた谷川俊太郎追悼だったかもしれない。
そのあと
そのあとがある
大切なひとを失ったあと
もうあとはないと思ったあと
すべて終わったと知ったあとにも
終わらないそのあとがある
そのあとは一筋に
霧の中へ消えている
そのあとは限りなく
青くひろがっている
そのあとがある
世界に そして
ひとりひとりの心に
『心』(朝日新聞出版/2013・6)所収
巻頭に置かれた詩だが正調俊太郎節である。大切な人を亡くした経験を持つ読者は「そのあとがある」という詩行を我が事として受けとめるだろう。「終わらないそのあとがある」という詩行に救われた気持ちになるだろう。それが俊太郎詩が多くの人に愛される理由である。
ただこの詩の「ひとりひとり」、もっと言えばこの詩を書いた谷川俊太郎という「ひとり」は読者が思っているより遙かに剣呑で孤独だ。谷川さんの第一詩集のタイトルは『二十億光年の孤独』だった。俊太郎は宇宙人のようだとも言われた。「孤独」といっても従来的なそれとは何かが決定的に違っていた。青年期に恐ろしいほどの孤独を味わった人だからその向こう側に抜けるような、万人の孤独に届くような詩が書けた。俊太郎さんはぬるい孤独の代弁者ではない。
誰にもせかされずに
誰にもせかされずに私は死にたい
そよかぜが窓から草木の香りを運んでくる
大気がなんでもない日々の物音を包んでいる 出来たらそんな場所で
もう鼻はその香りをかげないとしても
もう耳はもっと身近な者の嘆きしか聞けないとしても
誰にもせかされずに私は死にたい
愛し続けた音楽のように心臓をリタルダンドさせてやりたい
宴のあとのまどろみのようにゆっくり夜へと入ってゆきたい
もう脳が考えることをやめたあとも
考える以上のことがまだ私のどこかにとどまっているかもしれないから
それは私が自分を惜しむからではない
死のひんやりとした指に手首をつかまれた人々の
あのはらわたのよじれるような不安とあがきを感じないからではない
私はただこころとからだをひとつに運命に従いたいだけ
野生の生きものたちの教えにならって ひとりで
誰にもせかされずに死にたいから
誰もせかさずに私は死にたい
丸ごとのただひとつのいのちのままで私は死にたい
限りあるいのちを信じるから 限りあるいのちを慈しむから
今も そして死のときも
誰にもせかされずに私は死にたい
扉の外で待つ者が私をどこへ連れ去るとしても
それはもうこの地上ではないだろう
生きている人々のうちにひそやかに私は残りたい
目に見えぬものとして 手で触れることの出来るものとして
1994年10月8日「脳死・臓器移植」を考えるシンポジウムで朗読
のちハルキ文庫(1998)、岩波文庫に収録
俊太郎さんらしい詩だ。「誰にもせかされずに私は死にたい」という言葉は俊太郎さんの願望ではない。彼は文字通りそれを実践した。ある意味徹底して他者を排除した個の孤独だ。一方で俊太郎さんは死後の生のようなものを信じている。自己の何ごとかが受け継がれると確信している。ではそれを受け継ぐ者は誰なのか。「生きている人々のうちにひそやかに私は残りたい」の「生きている人々」は誰を指すのか。俊太郎詩を読んで茫漠と〝わたしの俊太郎さん〟といったイメージを抱く心優しい読者ではないのは確実だと思う。死後まで俊太郎さんの精神に「手で触れることの出来る」者は選ばれたほんの数人だけだろう。
下世話なことを言えば谷川俊太郎は死後に国民栄誉賞を授与されてもいい詩人だ。しかし政府系の栄誉をまったく受けていない。打診はあったろうが断ったのだろう。それは抒情詩を書くために必要だったからでもあると思う。抒情詩は嬉しい、悲しい、寂しいといった人間の原初的感情を表現する詩である。先生と持て囃されたのでは詩が堕落する。俊太郎さんが「悪口言われるの大好き」と言った意味もそこにある。そこまで含めて抒情詩のプロだった。死後までひたすらな讃辞にまみれるのは不幸なことだ。俊太郎詩についてはまだまだ考えなければならないことがある。
しんでもね
ゆうぜんと
んまであるいて
たくさんのしをかいて
ろうろうと
さりげなく
らくに
ばいばい
――谷川賢作
『別れの詩集』の巻末にご子息の谷川賢作さんが短詩を書いておられる。面白いことに賢作さんは根っからのミュージシャンだ。父親が言葉の人とすれば100パーセントの音の人だ。しかし谷川俊太郎を最もよく知る人はもはや賢作さん以外にはいないだろう。
『別れの詩集』の詩集を通読して改めて痛感したのは俊太郎さんの〈個〉の強さだ。強靱で孤独な個でなければ俊太郎さんのような抒情詩は書けない。その意味で谷川俊太郎は戦後詩人の一人である。ただそのような強固な個を戦後詩以降の詩人は持っていない。持つ必要もない。新たな時代に対応した個の在り方を探り、現代に対応した詩を書けばよい。俊太郎詩は後続世代にとって乗り越えられるべき作品群だということである。喪は明ける。詩人なら真正面から俊太郎詩に取り組まなければならない。
鶴山裕司
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


