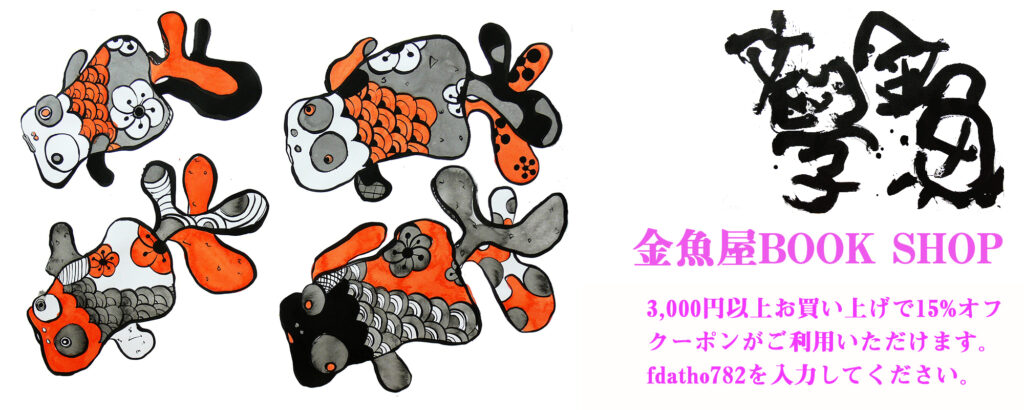日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
日本文学の古典中の古典、小説文学の不動の古典は紫式部の『源氏物語』。現在に至るまで欧米人による各種英訳が出版されているが、世界初の英訳は明治15年(1882年)刊の日本人・末松謙澄の手によるもの。欧米文化が怒濤のように流入していた時代に末松はどのような翻訳を行ったのか。気鋭の英文学者・星隆弘が、末松版『源氏物語』英訳の戻し訳によって当時の文化状況と日本文学と英語文化の差異に迫る!
by 金魚屋編集部
箒木
まだ若く頼りない身空、こんなときにはどうしたらと惑う心を半ば引きずり、半ば諦め、女は手引きされるがまま。
そこに折よく入ってきたのは先刻呼び出された中将、鉢合わせとなった源氏の口から「うわ」と声が漏れました。
中将は目を丸くして呆気に取られておりましたが、立ち上る衣香を嗅ぎ取ってすぐに例の皇子だと勘づきました。
いかがなものか、と訝しむも、中将は呆然としたままでした。相手が尋常一様な男ならすぐさま取っ捉まえていたところだけれど。しかし、此度の相手とて、少々手荒に止め立てして何故いけない、却って御家の擾乱の元となるといったって。中将は思い惑うばかりで詮方なく、ただただ二人の後についていくのでした。
そんな連れの目など意に介さぬ源氏の太々しいこと、貴人とは往々にしてそんなものでございましょうが、「すぐにお返しする」と言ったきりぴしゃりと障子を閉じてしまわれました。
こうなっては遣る瀬ないのは女です、中将の心中も思い量れぬまま、うろたえるばかりでございました。そんな女を宥めすかそうと調子よくおもねる源氏の、その口をついて出る殺し文句のどこで覚えてきましたものか。女はついに堪りかね、「そんなにへりくだられては身に余ります。有難う存じますが、まずはこなた様がどなた様か聞きとうございます」
「お分かりになりませんか」と、源氏はややまごつくも気を取り直し、「どなた様ともわからぬことこそ初な出来心の証。当初から承知尽くであったらこんなこと気が咎めてなりません。世慣れぬ身なのです、それはきっとご承知のはず。それだけにいっそう怪しまれるのも道理。私とて分別を無くした我が心の度し難さを怪しんでいるのですから」
源氏は沁み入るように語ります。これ以上甘い口説き文句で優しく言い寄られたらきっと絆されてしまう。そこで女は、頑な女と思れようとかまわない、情け知らずで通して、つれなく振る舞おうと決めました。こうしておとなしい性質に固い芯が通ると、強さと柔らかさが合わさって宛らなよ竹の如く折り難し。それでも女の胸の悶えは締め付けられるようで、目には涙が溢れました。
源氏も心を動かさずにはいられませんでした。どうしたらこの女の心を和らげられるのかわからないままに言葉を継いで、「どうしてそんなにつれないのです。たしかにまだ知り合って間もない、しかしそれが親交の入り口を閉ざすわけではない。世の中に不知顔をするのはおよしよ。胸が痛みます」
源氏の言葉が胸を打ち、頑な心が揺らぎ始めました。

今も昔と変わらぬ身の上で、と女は切り出しました、「かようなお心を頂戴しましたなら、取るに足らぬこの身でも、情け深く感じ入ったことでしょうけれど。こうして新たな身の上で今生を過ごしておりますので、足らぬ思いにつけ入って望むべくもない幸いがいくら夢見に立とうとも」ここまで言って女は口を噤みました、でなければ頭を離れぬ歌のくだりが口をついてしまいそうなのです、
ゆめいうなかれわがたくのさま
この束の間の無言が女の操の澄み渡る水面をかき乱したかと思うと、老いた夫の面影がふと胸をよぎりきました。日頃はさほど気にもかけていないのに、懐かしく思い出されてくるのです。すると、たとえ夢の中でも二心を抱く自分を夫に見咎められているような気がして身震いし、女は一言もなく部屋へと逃げ帰ってしまいました。源氏は一人になりました。
雄鶏が夜明けを告げ、お供連中も臥所から起き出してきました、「いやはやよく寝た」「さあ車の支度だ」
紀伊守も出てきたようで、「なにもこんな朝早くから、ご主人は何も急いでおらんでしょう」
源氏も床を出て直衣を身につけ、南庇の濡縁に出ると、欄干に寄りかかって辺りを見渡し、物思いに耽っておいででした。
西庇の窓には噂の皇子を一目見ようという物見高い連中がこぞっておりました。が、格子の奥に立てた衝立越しではよく見えないようで。そんな見物のうちには源氏を見つめながらぞくりと背筋の慄える思いをしたのが一人混じっておりました。暁の光の柱に照らされて空が色づきはじめ、なおも遠い空の端には月の白い影が引っかかっている、そんな時分のことでございました。明るく照るようにも陰を濃くするようにも見える熱気のない空模様はそれを見上げる者の心模様を映したか。昨夜の出来事に囚われたまま誰にも明かすことのない胸の内に、朝の景色は悲しみばかりを催しました。
いつか時宜を得て女に遣いを出せないものか、二度三度と振り返っては案じつつ、源氏は紀伊守を出でて舅の屋敷へと引き返しました。
それからの幾日かは屋敷で御新室と過ごされました。しかし、心は始終中河のほとりの女を思い遣り、ついに紀伊守を召し出して、こう語ったのでした。
「あの子を預けてもらえないか、先日会った中納言*1の孤児の。気に入ったので手近に置いておきたい。いずれ上様の御目にかけよう」
「御意。姉君が承知するかどうか掛け合ってみましょう」と紀伊守は頭を垂れて答えました。
胸を去りやらぬ面影を言い当てた答えに源氏ははっとしましたが、落ち着きを装って続けます、
「その姉君のために君の弟妹は増えたのかい」
「いえ、それがまだ。もう二年になりますが、父母の望んだ道からは外れてしまったと思い詰めているようで、今の身の上では堪らないのでしょう」
「哀れな。じつに佳い女と聞いていたが」
「ええ、それは確かかと。私としましては、ずっと別々に暮らしていたものですから、あまり打ち解けたものではございませんが。まあ、こんな義理は珍しくもない、世の習いというものです」
【註】
*1 子君の父は衛門督と中納言を兼任していたらしい。
(第18回 了)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■