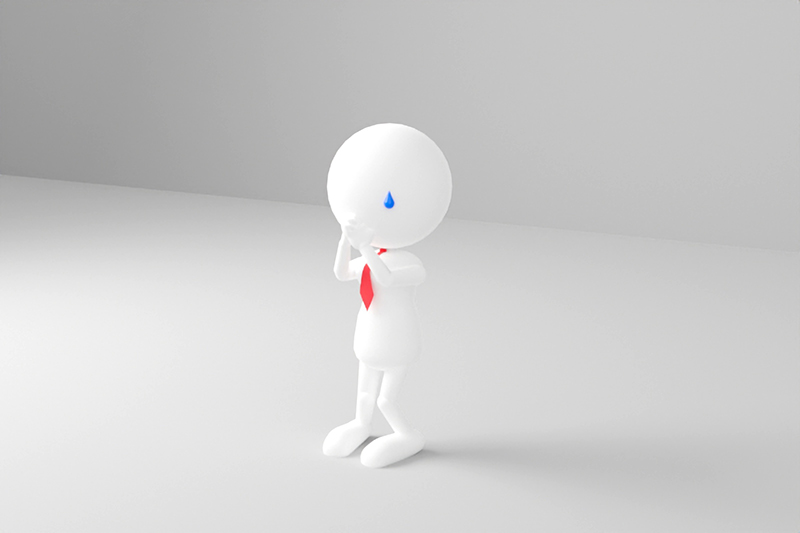
こんちわーわんわん。りょんさんですー。
この連載もいよいよ最終回になりました。今回は特に、文学金魚にとって大事なテーマを取り上げたいな。漫画家の芦原妃名子さんが亡くなったのは、前回のこの連載をアップした頃だったから、あれから1ヵ月近く経っている。騒ぎはちょっとおさまったように見えるけど、じゃあ終熄しているかっていうと、そんな気配はないよね。むしろ、この問題の根の深さがどんどん露呈してる感じ。
知らない人はいないと思うけど、問題の発端は、芦原さん原作の漫画『セクシー田中さん』がドラマ化されたこと。結構、評判がよかったみたいなんだよね。りょんさんとこテレビないから見てなかったけど、広告画像は印象的でよく覚えてるよ。ところがドラマの制作は、だいぶ揉めてたみたいなんだ。ドラマの脚本担当の相沢友子さんが、自分のSNSに内情をばらす投稿をして、それがわかったんだけど。そこには「最後の2話に関しては自分が書いたんじゃない。原作者がどうしてもドラマの脚本も手がけたいって言うから、しょうがなくて降りた」というような内容が書かれていた。相沢さんは不満でとても残念、あってはならないことだった、って。
相沢さんがそんな投稿をしたのは、ドラマの第8話までは評判が良かったのに、9話10話でちょっと普通じゃない終わり方をした、と言う周囲の人たちに言い訳したかったみたい。相沢さんの投稿だけ読むと、原作者のワガママでせっかくのドラマが台無しになった、ということかと思ってしまうけど、実際はそうではなかったらしい。
相沢さんの投稿を受けるかたちで、原作者の芦原さんが自分のブログやTwitterで説明をしたことから、経緯が明らかになった。漫画『セクシー田中さん』には(タイトルの雰囲気に反して)独特の深いメッセージがある。そのため芦原さんは、原作に忠実なテレビドラマにする、という確約をもらってドラマ化を了承したという。ところが第1話から8話までの脚本はすべて、原作者の意に反してヒドい改変がなされていた。芦原さんは自分の時間を削り、それを手直ししていた。
だからさ、第1話から8話までが好評だったのも、芦原さんの手がさんざん入った結果、ということなんだよね。脚本家の相沢さんがそれを隠して、8話までは自分の手柄だった、みたいに言うのもどうなんだろう。で、難しかったのは最後の9話10話で、芦原さんとしては漫画がまだ連載中でもあるため、ドラマの完結の仕方に大変ナーバスになっていたという。これは創作者として当然のことで、同様のケースでは、ドラマが先に変なふうに完結してしまったせいで続きを執筆できなくなった漫画家もいる。それで、このままではやばい、9話と10話については脚本家を変えるか、いや時間もないし急遽、原作者が自分で書きます、ということになった。原作者のワガママで、ぜひやってみたいと言い出した、ってのとはまるっきり違うよね。
この辺のところが芦原さんから丁寧に説明されたんだけど、そのすぐ後、芦原さんは自分の投稿を削除し、「ごめんなさい。攻撃したかったわけではなくて」という言葉を残して行方不明になってしまった。そして数日後、ダムに身投げして亡くなった姿で発見された。遺書も見つかっているという。
このことは映像・漫画業界はもちろん、ジャンルを超えてクリエイターたちに与えたショックがすごく大きかった。直接関係する日テレと小学館は、とりあえず自分たちの保身、事態を矮小化することに一生懸命だったように見える。ただ、テレビの報道局では女性アナウンサーらが絶句したり泣いたりして、ちょっと尋常じゃなかった。それはテレビ局というものの体質をよく知っているぶん、ドラマ制作で何が起きたか想像がついたからじゃないかな。そしてジャンルを問わず、クリエイターは皆、多かれ少なかれ覚えがあって、とても他人事とは思えない。芦原さんがかわいそうだ、という人たちがあちこちで声を上げ始めた。
ただ、声を上げるにも立場によって、かなりの勇気を奮い起こさなきゃならないんだ。だからこそこういう問題が起きてる、という構造が徐々に明らかになってきた。で、よりいっそう本質を露わにするには、芦原さんが亡くなった前後に起きたことを、もっと具体的かつ詳細に調べる必要があるよね。
脚本家の相沢さんがアップしたSNSは、とっくに消されてしまっているけれど、スクショをとっていた人たちがいて、非難にさらされた。相沢さんの投稿は、テレビ局の組織や脚本家仲間を味方につけて強気になっている雰囲気があって、よってたかって芦原さんを追い詰めた印象があった。芦原さんはそれで病んでしまい、自ら命を断ったという解釈が、最初は有力だった。
だけど、そうだろうか。芦原さんが自分の立場を説明してから自死するまでが、あまりに急展開、かつ唐突ではないか。まるで出来の悪いドラマ脚本みたいだ。それに芦原さんの説明は具体的、かつ明快で説得力があった。文章の雰囲気も、相沢さんのSNSが原作者への非難感情に溢れていたのに対し、芦原さんのものは冷静で客観的、ごく穏やかだった。
だから「ごめんなさい。攻撃するつもりじゃなくて」と、最後に残した芦原さんの言葉が引っかかるんだよね。「ごめんなさい」と、いったい誰に謝ったのか。格別に攻撃的ではない文章を書いただけなのに、「あなたが攻撃したから、こんなことになった」と誰かに責められたのではないか。ましてやその後、亡くなってしまうなんて、何かしらの大きな圧力がかかったのではないかと、どうしても思われる。少なくとも、ここまでの経緯には明らかに空白があるよね。
脚本家の相沢さんの投稿は大勢にサポートされていたけれど、それこそ組織の一員という立場ならではで、内情を暴露すること自体がコンプライアンス違反のはずなんだよね。なのに日テレはそれを諫めるどころか、相沢さんの肩を持つ投稿に「いいね」を付けるなど、けしかけた疑いすらある。まぁ、組織の力で原作者個人を黙らせようという動きがあったんじゃないかとは思う。
それでもね、漫画家は繊細であるというものの、芦原さんは50歳にもなったベテランだ。実力十分で、もっともっと描きたいことがあったろう。その創作活動そのものが行き詰まる何かが生じないかぎり、いきなり自責の念に駆られて自死してしまうとは考えにくい。また相沢さんが組織や仲間の力を使って優位に立つことを画策したのだとしても、それだけで負けを認めてしまうとも思えない。芦原さんにも多くのファンがいて、その投稿にもかなりの共感者がいたのだし、何より説得力のある説明ができた手ごたえは、芦原さんほどのクリエイターなら絶対に感じたはずなんだ。
もちろん、脚本家の相沢さんの投稿がきっかけで一連のトラブルが発生したのだから、相沢さんさえあんな真似をしなければ、と思うのは、やむなし。だけど同時に、相沢さんにそんな投稿を促すような組織的な雰囲気、過剰なバックアップがあったのではないかとも思える。そうすると、芦原さんを追い詰めたのは相沢さん個人ではなくて、そういった組織の力だということになるよね。最近、言われているのは、この辺のところなんだよ。
そもそも芦原さんの作品がドラマ化されるのは今回が初めてじゃない。だからこそ作品の行く末を慮って、いろいろと条件を出したんだよね。逆に言えば、芦原さんはテレビ局の正体をある程度は知っている。だから期待もしてなかったと思う。そのテレビ局の周りのクズどもと敵対したところで、予想の範囲ではないか。もちろん傷つくだろうし、鬱っぽくなるかもしれないけれども、死ぬほど絶望するとは思えないんだ。
漫画家にとって一番ショックなのは、自分を見出し、ずっと伴走し、味方と信じ、特にテレビ局など外部と関わるときにエージェント代わりに窓口になってくれていた出版社の裏切りではないかと思う。現状では何も決めつけられないけど、小学館の最初の対応は日テレに負けず劣らず冷たく、お役所的なヒドいものだった。まぁ、もともと小学館ってそういうとこなんだけどさ。
そういえば、芦原さんが亡くなった直後、まだバタバタしていた頃なんだけど、小学館が「『セクシー田中さん』は、どっちみち以前から休載が決まっていた」って言ってたよね。その「以前から」って、いつから? ドラマが終わってから? 相沢さんと揉めてから? それとも亡くなる直前の話? 「休載」ってのは芦原さんが言い出したことなの? 描けなくなったなら原因は? それとも小学館の方から持ちかけたんですか? それは懲罰的に? 亡くなって早々に「遺された作品を読んでください」とか言っちゃって、準備万端な感じだったけど。まさか連載の打ち切りを匂わせたりしてないよね? それなら作家の生死は出版社に関係ないよね、まさに「どっちみち」。出版社は作家を二束三文でテレビ局に売ってんの? 手塩にかけた娘を女郎屋に売るみたいに?
今回の件で、一番悪いのは日テレのプロデューサーだ、という説を見かける。ドラマに関して起こったことだし、その最高責任者はプロデューサーなんだから異論はない。一方、芦原さんの要望が通らなかったことが直接原因なわけで、それはいったいどのように伝わっていたのか。小学館は「もちろん、伝えた」と言っているけれど、言外のニュアンスはわからない。「原作者はこう言ってるけど〜まァまァ(笑)」みたいな馴れ合い、暗黙の了解、共犯の目くばせはなかったのか。だって大企業同士って、いっつもそんなことやってんじゃん。でなければ第1話の脚本に手直しが必要になった段階で、小学館から日テレに厳重抗議があったはずだけど?
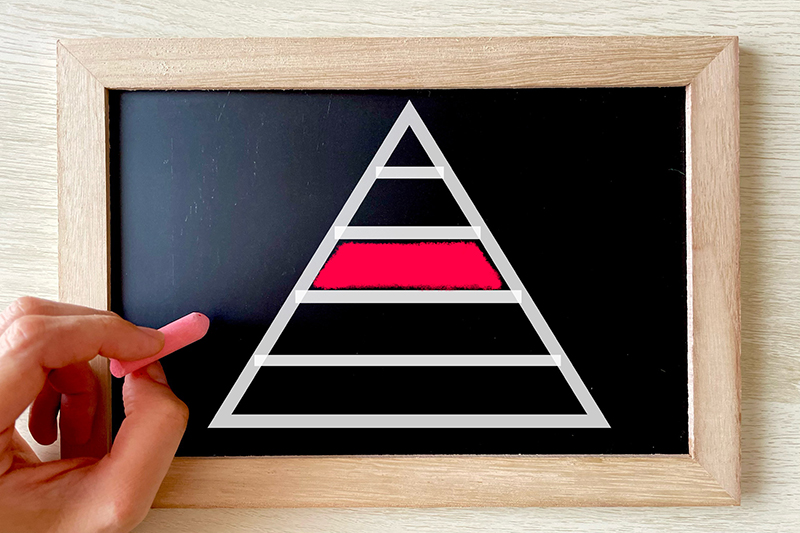
さすがに批判を受けて、小学館の漫画雑誌の編集部がちょっとだけ人間味のあるコメントを出した。「先生、寂しいです」とか。えーと、その主語は誰? って感じ。そりゃ出版社だからさ、そのぐらいの作文はできるんだろうね。寂しくなっちゃう前に、あんたたちは何をしてたの? って話じゃないか。
ていうか、芦原さんには特定の担当編集者がいたはずだよね。芦原さんのあの投稿は担当編集者のチェック済みだったそうだし。つまり彼女と話をしていたのは、テレビ局のプロデューサーでもなければ、会ったこともない脚本家の相沢さんでもない。この件で最後にやりとりしたのは、芦原さんの担当編集者、小学館の正社員の一人であるはずだ。なぜその人が、その最後のやりとりを公表しないのか。彼女を死に追いやったのは、そこでの言葉が直接のきっかけだと考えるのが普通なんじゃないのかしら。
漫画家の里中満智子さん(子供心に、すごーく安定した漫画家さんだな、と思ってたのを覚えてるよ。今は業界の重鎮みたい)が、「脅してくるような人の言うことを信用しないで」と発信している。里中さんとしては、たぶんそれが精一杯の許される表現なんだろうな。一人のクリエイターの、文字通り命を奪うような脅しをかけられる存在って、他の業界の人ではない、と推察する。やっぱり世話になった大手出版社そのものじゃないのかな。もしそうなら、そのリアルな脅しの言葉をぜひ聞いてみたいよ。
想像する通りだとしても、それを伝えた担当編集者個人を責めようとは誰も考えない。きっとショックで寝込んでいることだろうし、担当者は組織の中で求められた対応をしたに過ぎない。そして、それが作家を絶望させるほどの言葉なら、一人の編集者の言葉尻などではなくて、出版社とテレビ局という巨大組織の揺るがない関係性がうかがえるもの、ということだ。その関係性はおそらく、芦原さんが耳にした最後の言葉からしかわからない。社内調査でなく、第三者委員会の立ち上げが求められている、というのは、そういうことなんだよね。
その他の漫画家の声としては、『海猿』の原作者である佐藤秀峰さんの発信が話題になっている。『海猿』が、佐藤さんが言う通りクズドラマであったとしても、海をバックにしたかっこいい番宣ポスターやなんかは誰の印象にも残ってるよね。で、佐藤さんは原作者として撮影現場を訪れたとき、主演の伊藤英明さんに紹介された。それは本番前で、伊藤さんはピリピリしていたのか、「原作者? 話さなきゃダメ?」と言い捨てたと言う。「嫌な奴だと思った」と佐藤さんは言っていて、要するに撮影周辺なんて、そんな連中ばかりってことだよね。
伊藤英明さんはそれに対してはコメントせず、ただ、佐藤さんからもらったというサインの画像を投稿した。かっこいい、とかいう意の応援メッセージも書かれている。つまり、それによって佐藤さんの苦情をなし崩しにしようとしているわけね。佐藤さんは、「大人の対応に恥入りました」などと言いつつ、「ところでこのサインの日付は、僕が現場を訪れた日より何年も前なんだけど、いったいこれは誰にもらったもんなんでしょうね」と、嫌味たっぷりにコメントした。いや、創作者らしいな〜。ネット記事では「大人の対応に恥入ります」ってのを真に受けていたのもあったけどさ、ばっかじゃないの。これはね、「王手!」もしくは「ウラが取れたぞ」っていう雄叫びなんだよ。
だけどね、伊藤英明さんが主演だからって大威張りで勘違いしてたとは、りょんさんは全然思わない。本番前なんかに紹介した奴もどうかしてるよね。撮影現場なんてさ、そういう使えない奴らの吹き溜まりで、たいていはわけのわからんうちにレベルの低いものを適当に作ってるだけなんよ。そんな中で俳優さんこそ組織の歯車の1つでしかなくてさ、心優しいからこそ周りに迷惑かけちゃいけない、クズドラマをさらにクズにしちゃいけないって、マジでピリピリしてるわけよ。
それに伊藤英明さんといえば、ものすごく印象に残っているシーンがある。あの『白い巨塔』の研修医役。大学病院で小突き回されたあげく、財前教授(唐沢寿明)のための嘘を吐き通せなくなって、裁判の証言席でついにブチキレてしまう。危機迫る名場面だった。あのときの伊藤さんは本当によかった。伊藤英明さんって、そういう組織の中で追い詰められるとか、自責の念に駆られた心の弱い男、というのがハマり役なんだからさ、今回の対応は正しくイメージにぴったりだったと思うよ。
そんで、その『白い巨塔』を初め、小説の映像化作品には素晴らしいものがいくつもあるよね。それに比べて、やっぱり漫画の実写化っていうのは無理があるんじゃないかな。昔は漫画のイメージに近づくために、俳優さんが必死になってたものなんだけど、だんだん面倒くさくなっちゃったんだろうね。てか、組織の力で、あっちサイドを黙らせて、原作なんてなかったも同然みたいにすればいいんじゃね、って気がついたってこと。
いや実際、俳優さんっていうのはホン次第なんだよね。それは原作ではなくて、確かに脚本。でも脚本っていうからには、本当はオリジナルなものじゃなくちゃいけない。今回、問題になったのは正確には脚色なんで、脚色担当が権利のある原作者に楯突くなんて、どう考えてもあり得ないよね、そもそも。そしたら原作者には、脚本のチェックの他に、スタッフやキャストの拒絶権、人事権も最初から当然のように与えたらどうだろう。結局、誰しも人事権のある者には逆らえないんだからさ。
「時代の寵児」とか「時代と寝た女」とか、ときどき聞くけど。何のことはない、その時代に力のあった大組織に重用された、という以上のもんじゃないことが多い。で、その組織ってのは結局のところ、名もなきサラリーマンたちの集団なんでさ。彼らは定年になったらいなくなるわけなんだけど、だからこそ無責任に、できる間に権力を奮っておこうとするだけの連中だよね。そんな凡庸な輩が、結局のところ創作者を追い詰めていく。まるで自分たちに与えられなかった才能の代わりに、そうする権利があるとでもいうふうに。出版やドラマ制作に関わる以上、若い頃に何かの小説に感動したり、創作に関心を持ったりしたはずなんだけれど、大きな組織に入ってしまうと、自分たちに都合のいい価値観を信じたくなって、目の前の人々に権力を奮い始める。でもそれは本当は、ある種のあきらめと引き換えなんだよね。
この最悪のタイミングで、脚本家を自称する人たちの座談会の内容も公表されたね。それも非難の的になったんだけど、彼らもまたテレビ局という大組織のサラリーマンたちにおもねることで、似たような人種になっていっている。オリジナルを作り出す力を幻として笑いものにすることで、自分たちこそがインサイダーの利口者だと思い込み、クリエイターを僭称することに恥を感じなくなる。
大組織の凡庸なサラリーマンと、その外部受注者たちに共通して言えるのは、誰もが知る大物や著名人と表面的に仲良くする一方、自分たちがそれと認めない大半のクリエイターを足蹴にしたり、馬鹿にしたりすることで、自らがその中間の立場に割り込めていると錯覚することだ。それこそ幻想なんだけど、自分たちの人生から、なんとかして自分に与えられなかったものを取り戻そうとしているので、哀れだとも言える。
でも実際のところ、いわゆる創作の喜び、自身の世界の実現に比べれば、どーでもいいような組織での地位やら高給やらはちっぽけな慰めだって、彼らのヨワい頭でも感じている。だからこそ無作為かつ無意識的な悪意で創作者を取り囲み、じわじわと追い詰めるんだ。センセー、好きなことやってんだから、イイじゃないっすかー、って。会社がウルサイんすよー。そんで僕もうすぐ定年だし、年金生活になったらぁ、立派な本棚に、これまでのボーナスで買った本を並べて執筆の真似事でもしてみよっかなー、みたいな? まぁ、悪人ではないよね。誰も彼も、別に悪くはないんだ。ただ無責任で凡庸なだけ。
本来、創作者を守る権利はいくつも定められている。だけどその法すら骨抜きにしてしまう、漠然とした集団的悪意と嫉妬が創作者の寿命を縮め、力を奪っていく。創作に関わる者。あるいは個の力を十全に発揮して生きようと心に決めた者は、この悪意を常に警戒し、身を守っていかなくてはならないんだ。と、自らにも言い聞かせつつ、りょんさんはこの連載を終えます。また会おうね!
りょん
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


