
前回で示唆したように、テクニカルとファンダメンタルという立場の違いは、そんなにすっぱり分かれるものではない。最近思うのは、むしろそのちょうど波打ち際というか、接点のようなところ、互いに侵食しあってる部分こそが最も興味深く、重要なのではないか。それは〈言語派〉と〈人生派〉という文学的な仕分けにももちろん通じるが。
文学よりも、また投資手法よりも。もっと根源的なところにさかのぼって考えてみよう。たとえば言葉を幼児期から身につけるときのことを考えると、それは意味から理解していくのか、それとも音から理解していくのか、という問いに行き着く。外国語を学ぶときはある意味、幼児のように一から学んでいくわけだから、それを追体験できる。赤ん坊とは違うのだから大人なりの勉強の仕方がある、というのも確かに一理あるけれども、そこに寄っていくと結局、歪んだものしか身につかないだろう。子供はどうやって学んでいるのか、遠回りして子供のやることをもう一度繰り返すことを厭わないと、思わぬ発見があるのではないか。
『不思議の国のアリス』だったか『鏡の国』だったかに、「音が先で、意味は後からついてくる」といった一節があったように記憶している。何やらそれは単なる誤訳で、そんな意味深長なものではなかったと聞いた気もするが、あえて誤解したままでいたい。そう、音が先で、意味は後からついてくる。それは確かに、真実ではないだろうか。
つまり音を単なる物理的な空気の振動として捉えるのではなく、音に込められた多くの、そして古からの、その音に込められた想い、その音を発するときの人の気持ち、あるいは気合が存在すると考える。それが、その意味を必ずしも知識として持たない者に対しても、無意識を通して伝わってくるというような。なんとなく宗教的にも感じるけれど、そもそも言葉とは、そういう無数の人々の共同幻想によって初めて成り立つものではないか。
すなわち言葉とは〈誰かに何かを伝えるためのもの〉である。物理的な音と、そして辞書的な意味が結びついた〈知識〉ではなく、あくまでも誰かに何かを伝えたいという思念、そしてそれを受けた者が、相手が何かを伝えたがっていると感知する、そこにしか言葉は成立しない。
「詩とは何か」という問いに関しては、いくつかの書籍がある。萩原朔太郎の『詩の原理』は、その問題をめぐる朔太郎の真剣な思考の痕跡を辿れるという以上の意味はない。つまりそれを読んでも「詩とは何か」は、ちっともわからないのである。「詩とは何か」ということについて最も建設的な意見を述べたのは、詩人の岩成達也氏だと思う。岩成氏は「詩とは(これは詩であるという)宣言である」という定義を提唱した。すなわち詩は、「これは詩ですよ」という態度やスタンス、それによって〈詩〉になるのだということである。
岩成達也氏は東大の数学科出身だ。変わり種のようだが、詩人には結構、理科系の人が多い。私自身もそうだが、理科系の人間の特徴は、原理的な考え方をすることである。この岩也氏の「詩は、これは詩だという宣言によって成立する」という定義は、禅問答のように感じる人もいるかもしれないが、私にはよく納得できる。一見とっつきにくく抽象的な言い方だが、よくよく考えてみるとまさに矛盾のない、その通りとしか言いようのない、美しい定義だ。

この岩成氏の定義をもとに、わたしは自分の大学での授業で、学生が詩の読解を発表をする際、何でも好きな作品を取り上げてよい、と言う。こんなのでもいいんですか、あんなのでもいいんですかと質問が来るが、自分自身が詩として読解できるのならば何でもよい、と答える。電話帳の1ページでもよいのだ。自分がそれを詩として宣言し、読解できる自信さえあれば、それが詩ではない、と反論するのは困難を極める。
逆に言えば、それを通して「詩とは何か」の輪郭が微かに露わになってくるわけである。教科書に載ってるような、「いわゆる詩」というものがあって、それをなぞるように読むことが勉強だと思っているうちは、教養は身につくかもしれないが「詩とは何か」の根源に触れることはできない。
外国語の学習もおそらくそうだろう。わたしは受験のために、短い時間で長文の意味を把握するトレーニングぐらいしかまともにやってないのだけれど、その場合でも、またわたしたちが苦手とする英会話の場合でも、要するに相手が何を言おうとしているのかということに真剣にフォーカスすることが最も重要だろう。書かれている通りに発音されていようといまいと、あるいは何ごとか省略されていようといまいと、その言いたいことの中心は何なのか。相手も人間だから、その中心だけに意識が向いて、他の部分は早口でやり過ごす。それは当然のことではないか。それが英語を難しくしている、というような考え方をしていると、いつまでもそれは教養であり、「学習」すべき代物にしか過ぎなくなる。
今回は最終回ということで、投資術から離れた本質論から説き起こすようになってしまったけれど、チャートを読むこともやはり、そのチャートが何かを伝えようとしているという観点から考えると、一つの言語の読解と近いと感じる。ではそれは誰の意思で、誰の考えを読み解こうとしているのだろうか。
初心者向けによく言われるのは、たくさんの人が買っている東証一部上場だとか、あるいはNYゴールドだとか、そういったチャートを中心に見るように、そしてまたそういったもの以外はトレードしないように、という注意だ。なぜならチャートがすべてを表しているという、その「すべて」の範囲が広ければ広いほどチャートは規則的になり、いわゆるきれいなチャートに近づくからだ。
たとえば、ごく数人のキーマンが売買に関わっているだけの株式の場合、その中の何人かの意向によって価格は大きく左右される。その様子もまたチャートには現れるが、次の展開を予想することは誰にもできない。チャーチストが手法を活用できず、強いて言えば人生をかけてそれらキーマンと関わり、その意向をうかがうことができる場合のみインサイダーとして価格の予想が可能になる。しかしそれは現在、違法行為であり、いずれにしてもこういった銘柄には関わらない方がよい、ということになる。
それこそ世界中の無数の人々が投資をしている対象では、チャートはそれぞれ固有の思惑では左右されず、現れているのは集団的無意識とも言える。そしてさらに多くの人がそのチャートを見て、集団的無意識がどのように動くかを意識的に読み、その結果として新たなチャートが形成されるわけだから、まさに無意識を意識化し、意識を無意識化することが行われている。
そう考えると、チャートというのは本当に不思議な、ある意味で言葉そのもののようなものだ。様々な人生を意識的におくる、多くの人の無意識によって形成されるチャートの意味するところのものは意識的に読み取ることができ、あるいは読み取ることができないとしても、そこには意識的な人々がいて、その存在は無意識そのものだ。そのことだけは確かである。
小原眞紀子
* 『詩人のための投資術』は毎月月末に更新されます。
■株は技術だ、一生モノ!■
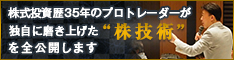
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








