『わがテスト氏航海日誌』はB5版ノートに記された安井氏の創作ノート。巻頭に「1971.5.30→」とあるので昭和四十六年中に書かれた創作メモのようだ。高山時代の創作メモである。
物故なさり文学史上の作家になってしまわれたので書いてしまうと、安井氏は昭和三十五年(一九六〇年)に日本歯科大学を卒業してから足かけ十年勤務していた赤羽第一歯科を昭和四十四年(一九六九年)二月に退職し、岐阜県の飛驒高山に転居した。ある女性を伴っての出奔だった。昭和四十七年(一九七二年)十一月三十日に高山を去り、秋田市で歯科医院を開業するまでの三年弱を高山で過ごした。安井氏三十三歲から三十六歳のことである。
この高山時代に第三句集『中止観』を刊行した。また秋田帰郷後の昭和四十九年(一九七四年)に第四句集『阿父学』と初の俳句評論集『もどき招魂』を同時刊行している。両著が高山滞在中に構想が練られた作品集であるのは言うまでもない。『わがテスト氏航海日誌』には安井氏らしい俳句を巡る哲学的思考が綴られているが、当時の苦しくも研ぎ澄まされた心境が色濃く反映されている。
なお安井氏の未発表原稿はダンボール箱十箱近くあり、それらをあらかじめ精査した上で「安井浩司研究」として未発表原稿を明らかにしてゆく時間がない。従ってランダムにダンボール箱を開けその都度原稿を整理して発表してゆくことにする。最終的に俳句や俳論別に原稿をまとめ、時系列に沿って並べ替えて本にできればよいと思っている。なお判読不明文字は■で表記した。
鶴山裕司

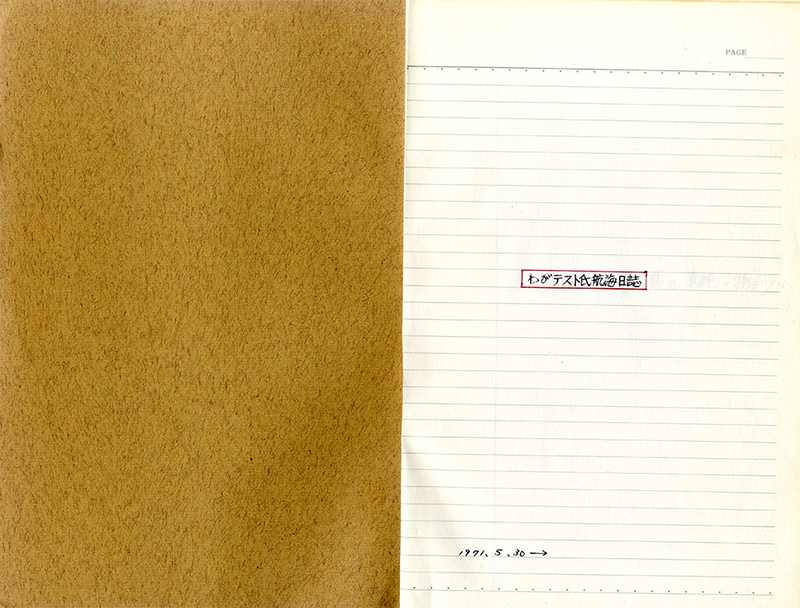
わがテスト氏航海日誌
1971.5.30→
安井浩司
俳句ノ生涯ハ最モ単純ナ物デアル
某日
〈追伸〉
テスト大兄。あなたは私をにがにがしく思っていることでしょう。不本意でした。私は大兄に下心をおこし、弓をひこうなどとは露思っていなかったのです。この心は今もかわりがありません。勿論、聡明な大兄は、私の弱心を百も承知のはずです。いやそれを承知していればこそ大兄は、私の成すがままを、憐みをもって眺めていたのでした。
私だって知っていました。大兄が私を憐れみ、ふびんに思っていて下さることを。
あなたは何一ツ云わない。云わないから、それだけに私は反抗し、いらだち、不義を犯してしまうのです。私も、いくらか大人になり、大兄の詐術を見破る智恵がついてきたのかもしれません。過日のように激しく酒乱状態に落入ることもないようです。
しかし、大兄はそれがどうやら最近不満らしい。餌サは餌サらしく暴れ回ったらどうだと大兄は側近に漏らしていたそうですね。
勿論大兄はあざわらいつつも、その日を楽しみにしている〈あの約束〉を忘れていないでしょう。
あの約束――つまり、私がいつか公衆の目前で手袋を脱ぎ大兄へなげうつときです。そう、大兄があざわらい、モノともしなかったあの〈決闘〉のことです。私は決闘を楽しみに生きていたのです。私は死んでいません。だから、あざ笑われるのでしょう。多くの友は、美しく死んだが、私は醜く、その日を待ちつつ生きているのです。テスト大兄。いずれの日に。
掌中詩論。
掌編詩論。
掌上詩論。
海は重かった。
私は、何時からこの船に乗せられて海上の旅に出ていたのか、どうもわからない。気が附いたとき、ただ海面の重たい波に揺れていたのである。
テスト氏が、いつどんなふうに出現するのか、それは全くわかっていない。しかし、必ず出現するような気がした。海上の落日に向って一匹の極楽トンボがとんでゆく。
「言葉」に対して
思いを抱けば抱くほど言葉は応えてくれる。
・・・・・・という考えを捨てたくない。
「形式」だってそうである。
言葉が痩せるときは、思いが薄くなってきたときである。
これを勿論単なる楽観主義と取られてはこまる。
枇杷男によれば愛は最高の認識の形式なりとtelがあった。(倉田百三あたりか。)
巣鴨村をよぎり、小高い丘の峠の茶店で障子を閉めて女と居る。
ぶ厚い一冊の書物をひらいたが、どこまでも白紙である。だが案の定、三百二十七頁に至って
有季定型
と出てきた。この船の愛称にしようと思いノートに記す。
船の中で、船をもやした。
もしかしたら、テスト氏は永久に逢えぬ人かもしれない。彼は病気なのだ。
船を表現するに就き、表現などという結構な船はない。
タンタロス
ぼくがここで描くということは「模写」すると呼ぶ方がよいかもしれない。
ぼくの行為は〈模倣〉なのだ。
秋田→(東京)江戸→(高山)
故郷脱出とは、即江戸放蕩にちがいなかった。
江戸こそ、目ざすわが幻想的宇宙であり、たましい(魂)を心おきなく蕩尽できる理想郷であった。
しかし、
それは、あくまで不在郷としての江戸でなくてはならない。
この瞬間に、私は江戸を超えねばならないと悟った。
ここに、不在郷を確乎ならしめるための江戸脱出、いや、江戸を突き抜けるためのわが地理論を構築することになる。私は「高山」を選び、ここに立てこもる。しかし、高山を超江戸として選んだのではない。ある媒体として選んだのだ。
すなわち、ネハン幻想へ。
古代史への回帰としてではない。これは、はっきり明言したい。
むしろ、高山の〈高さ〉を愛した。すなわち、わが風景論における眺望的位置において応うからである。
カオスの思想―――――『青年経』
↓
失敗の思想――――――『赤内楽』
(完敗)
↓
間の思想―――――――『間の喘ぎ』
↓
もどきの思想―――――『もどき招魂』
・
・
・
↓
有季定型の思想――――と成るか。
「有季定型」とは
あくまで俳句定型に所属せしむる思想としてではなく、私自身の、俳人作家主体の場に呼び起したわが宇宙論としてである、のは云うまでもない。
カオスの思想に於て
私は〈幼年形式〉を祀るべく腐心していたようだ。幼年形式といえば、あくまで退嬰の彼方にむかう退行願望として見出されようとしたのであり、個体発生的な、進行的なそれではない。窮極的には胎内形式と呼ばれてよい、あの胎児の睡りにちかいものを求めていた。しかし、それはスタティックな静世観とはちがう。始源としてのカオスへ向かわせたのであった。
・「赤内楽」後記の
――わが失敗の城にかけあがる――
という表明を大岡頌司が〝云いわけ〟と解釈したのは、彼の読み不足である。
私は、そこに失敗の思想を込めておいたのだ。失敗とは、ある有機的投企が前提として語られる言葉であり、単なる結果を指して云っているのではない。
俳句とは、悲しい哉、近代の形式である。
悲しい哉!と思えない人間はその志の程度がすぐ知れる人間である。
俳句とは俳諧である。
彼はイロニイ
ニヒリズム を内蔵する以外に成立できない。
(一度、中世の「禅」を知った日本人が近世的に勃起せしめた時代的な形式なのだ)
(俳句は禅ではないが、禅の形式と近似的に隣接している)
いうなれば、俳句は、サンボリズム以後の形式である。
フェティシズム(物神崇拝)
節片淫乱症などと大時代的な訳語を与えられることもある(岡田隆彦)
↓
僕の〈季語〉論に近いのではないか。
こゝで
「のぞき趣味」が考えられる。
のぞき趣味はフェティシズムでろう。
竹の中より関八州を覗くように、まさに季語的である。
眼の方法をかえることによって、世界をかえる幻想行為のひとつ。
あの「もの」論とは、結局、現代人の季語論であったのではなかろうか。
「もの」に凝ることによって(フェティシズム)世界はトウゼンと変わる。
季語はリアリズムではない。
その秋雨、その茄子、そのトマトではない。
↓
のぞき場(孔)のごときものであった。
それは、今日フェティシズムと呼ばれるものにちかい自己原則(原理)を果しつつある。
歌は本来
呪詛を併せもつ
それは音楽、古代祭祀の儀式をふるい立たせる〈発声〉とか〈音〉とかに依る。
短歌は声調を通してなければ、救われない。
俳諧は本来
禅をもつ。
それは〈発声〉を否定する。
↓
という否定構造の文学ではあるまいか。否定によって現成する世界を求める文体。つまり、歌以後の、サンボリズムの世界ではないか。
古代祭祀というよりも、近代に通ずる命脈を保持していたとも思えよう。むしろ〝遊び〟と〝虚白〟を宇宙的に内蔵していたと思える。
二十代には二十代の
三十代には三十代の
四十代には四十代の
「割引」がある
二十代の〈学割文学〉に対して三十五才における文学の「割引」とは何か。
◎
「顕」という言葉がある。
これは、わが即身論と切り離すことの出来ない本質的な意味を負っている言葉だ。
我々俳人は「顕」を悲願しつつ生きていると云ってよい。
「顕」が立ちあらわれる先は無数にあろう。
近代の俳人において、
「即身」において「顕」をみちびき出したのは西東三鬼ただひとりであった。
西東三鬼に哲学(メタフィジック)
現実(フィジック)
日常次元 等々
すべてあてはまらぬ。
彼の美学の正鵠を射る一語はこの「即身」の思想をおいて外はない。
されば安井浩司こそ西東三鬼に外ならないのではないか。
安井浩司の思想とは何か。
それはまさしく〈即身〉の思想にこそちがいないのだ。
この一点において、わたしは三鬼と烈しく腸管で交わしうる者だ。
その他に安井浩司の原像を求むるとして誰が居よう。(遡って其角に即身の匂いを嗅ぎとれるが、それは定かではない)
私
体質といえば確かに永田耕衣に似て非なる者だ。
美質といえば確かに西東三鬼に似て非なる者だ。
三鬼を論ずる場合、
俳句即生活論も、この即身思想の上塗りにすぎないと思う。
なぜなら即身思想の板子一枚の下には俳句即生活が卑俗的に密着しているからである。
安井浩司の世界とは何か。
それは、
・一本の倫理をたのむ哲門でもなく(例えば耕衣、[河原]枇杷男等)
・反倫理でもなく([加藤]郁乎等)
・西洋の価値観でもなく
・社会性なる代物でもなく
・花鳥風月にもあらず
盡くるところ
即身宇宙論である。
それは安井浩司のユートピアと称しておくしかない独得の世界である。
・大岡は〈赤内楽〉を通してリビドウの世界と称した。
これは半分当っている。
しかし、フロイドのいうリビドウを上塗りしただけでは、〈赤内楽〉を出現しなかったはずだ。
・永田耕衣は、「〈形而下的〉であるまいか」と遠まわしに云った。
これも半分当っている。
しかし、即身の思想において形而下的であることにより最高の形而上を獲得している。この独自の宇宙論を認めていない。
・まして、
・社会性がない
・思想がない
・テーマがない
などと称する輩が居たならチャンチャラおかしい。


金子兜太に就いて(1200字小稿を求められる。)
兜太の濁り
・同世代の俳人が、かつては多少とも濁りの世界を持っていたが、あらかた透明水となった。しかし、兜太だけは、まだまだ濁りを持続している。
・兜太と同行した人たち、(鈴木)六林男、(佐藤)鬼房、(原子)公平、(林田)紀音夫、(堀)葦男、(島津)亮etc.の俳人は、もう濁りがない。すなわち、戦後作家としてその才能を尽くした後の、一寸の新世界は拓かれていない。
・勿論、兜太が、どれほど新世界を拓きつつあるか、といえば、すでに初老として、昔日のごとき未知への挑戦者としての光時はうすい。しかし、作家の成長というか、変貌というか、このような流行への意欲はズバ抜けており、一線の作家存在として光時をつないでいる。
・金子兜太という存在は
〈アプリオリの法則〉というものを教訓させられる。すなわち、俳句大の覚性というものがそなわっている人間のみが、俳人らしい俳人である、ということだ。金子はまさしくその一人であって、俳句の適切なる具現者である。
近業として金子
・遊び
暗黒や関東平野に火事一つ
・素材の変化
都市→土俗
・斎藤茂吉の「赤光」「「あらたま」「白き山」が好きであるという。
・動き。
・有季定型の解剖
金子兜太を比喩の一言でいえば、たとえば自動車の中でトラックである。
・金子兜太の精神の世界は〝救済〟されている、ということに今、気附いた。
どんな作品でも、救済感があるのである。モダニズムの、あの絶望的な、被害者の意識はない。ニヒリズムもない。
その作品世界の当面の最初から救済される方向に書かれている。
これは、金子の意識構造の問題だと思うが、百姓の思想があると思う。土俗と云ってもよい一種の原始論の思想があり、農本主義があるようだ。
人間への楽観的協調があり・・・・・・。
金子兜太をみていると
わたしは次第に〝原日本人〟の典型的人格(むしろ体現)をみてしまう。少くとも彼に、異邦人とか旅人とか宇宙人とかいったキザな人格のイメージは当てはまらない。
彼は今もって、昔なつかしいニホン人であり、ニホンに生まれ、ニホンに土着し、少しニホンを嫌いながらも、反面ニホンを愛す。
ニホン人であることによって、すべからく救済される。ニホン的思想が結局は、ニホン人としての自身を救済する。
・有季定型は
わが俳句の逆選択であること。
・私は俳句の本質が、かくかくの如くに在るべしという教条主義を信じない。
・はっきり云って、俳句の本質などと断定することは愚かしいことである。
・俳句の本質とは、それを追求し断定することはすべからく虚妄の上にあることを、前提として知らねばならない。
・金子氏のような最短定型が俳句の本質であるなどと、こんな断定の仕方は、嘘っぱちに思えてしょうがない。
・季語は属性であり、十七音定型は本質であるなどという言い方は、アジテーション以外に何の含みもないと思う。
・さて、私は、俳句の本質を、正面切って言うことは出来ないし、そんなことを、ちっとも証明する必要もないと思う。
・俳句とは何か――これを証明することは愚行である。
・更に、
・俳句性を維持したいために――これは気持ちとしてよく分かるが――俳句らしさの「らしさ」という意匠を要求する人間も居るが、この「らしさ」も嫌いである。
・問題を継ぐならば、俳句の構造は、本質と考えられる項目がすべて否定されたところに立てる幻想としてあるのではないか。
・幻想としての17音
有季
切字
三句断続
連衆発句性etc.
・おそらく虚妄の上に逆選択していくところに幻想としての本質があるのではないか。
・誰も俳句の本質を云い当てることは出来ない。
・誰も俳句形式の絶対様式を断ずることは出来ない。
・しかし誰でも、俳句の本質と思われる〝思想〟を逆選択できるチャンスはあるはずだ。
・だいたいにおいて、俳句は〝試行錯誤〟の文学である。
これは真新しい発言ではない。
加藤郁乎ではないが〝反性〟としてあるわけで、倒錯を㐧一の美学とみなす。
なぜなら、沈黙の世界、あの拈華微笑に通ずる無時間の思想において成立つものだという假説が、そうでないという假説よりいくらか・・・・・・。
安井浩司の世界
・作品の中において「我」の存在が無いということ(中村苑子)
これは、作品の埒内においても埒外においても即自論としての〈我〉は無い。
〈我〉は、作家・安井浩司として在るだけで〝作中の人格〟はない。
即身即空無である。
・無人称の俳句である。
他者の俳句ですらあるといえる。
哲学、精神の秩序、体系、人生観、観念論etc.を排す。
いわば現論なこの作品自身において樹たしめる世界を求めている。
天沢(退二郎)式によれば作品行為ということであろうか。
・だが単に、これだけの一面的に過ぎぬものはない。
安井浩司の〝二重構造〟を見破らねばならない。
すなわち、作者は作品にあやつられる形として作品の影として存在しているということだ。
作品が実存であり、哲学は虚存である、ということだ。
・虚像の世界
虚の鏡にうつる諸々の世界。
・作品のもつ精神構造は(作家の・・・・・・ではなく)
①〝逆行〟の美学である。
実存→幼年→土着→密教→ウパニシャド、〝退行の思想〟か。
今日から昨日、昨日から昨年、昨年から未生以前へと。
②そのために〝幼年〟がフルに活用される。
③安井に於る幼年形式とは、
挽歌でも賛歌でもない。
即身のエロスとしてあるだけだ。
④まさに一度見た夢を、白昼において再び見んとする文学である。
⑤虚の世界の現成。
⑥逆算の世界。
・逆選択
・逆リアリズム
⑦無意味性の世界。
無意味性の中に世界が出現することを無意味の意味という。
⑧迷いの美学――耕衣
上手いことを云う。
⑨中止観とははっきり云えば〈中止(エポケ)〉の世界である。
しかしこれは身の中のエポケとして、即身成仏となるミイラを思えばよい。
おかげまいり、ミイラ、断食、補陀落渡海etc.はすべて汎世界論への〈中止〉を加えたものである。
ここに〈立川流〉が顕現するのも止むをえない。
中止 エポケ
クセジュ〈ギリシャ哲学〉より
・・・・・・・しかしながら、判断の中心([ギリシャ語]epokhế)の原則をはじめていい表したのは彼である(彼――ピュロン)。
私はなにものをも規定(定義)しない。把握しうるものは存在しない。見かけ(現われ)こそ万物の主である。
イエスでも、ノーでもない。賛成にも、反対にも等しい〝根拠〟が見出される。
・彼は、プラトンのイデアのようなあいまいなもの、かくされたものを疑うべきだといっている。
だから、われわれは、〝善〟についても〝悪〟についても見解を持つことが出来ない。
アパシア([ギリシャ語]aphasia 沈黙、無発言)とアタラクシア(無憂無碍)のみが、法律と習慣を尊重すべきことを要求する無感動にまで人を導くことができる。
・判断の中止と無関心は、人間がとらえることのできないものの不確定性に基ずく無感動の帰結を示すものである。
・乳切木――両端を太く、中央を少し細く削った棒
元来、物を担うためのものであるが、喧嘩などにも用いた。
・自分の精神の様相(あるは状態)よりも一歩先に詩を置く。これは私の方法なのだが、時として詩より精神を後退させて書くことだってある。
・俳句の世界で、まだそれほど〝書き残されているもの〟があるとは思えない。だから、全てを〝書き切ってしまわぬように〟書く。
・赤内楽のときは、言葉はどれほどしごかれて言語表現に耐えうるか、という試みがある。
・モチーフはあっても、主題はない。モチーフに就いては、いくらも語り継ぐことはできるが、唯一の主題すら語ることはできない。それは無主題なのだから。
・中止観をエロチシズムで断罪することは見当違いであろう。エロチシズムということは、マトがそれているわけでは決してないのだが、それでは中止観の虚相の拡がりはモトもコも無くなる。エロチシズムという限り、一種の相乗的伴奏にすぎないのであって、少くとも私達の誰でもが書いている世界に共通している、そんな程度のものである。
むしろ、内的形象感にエロスがあって、それが虚の方向に表われてくるから、その形象感を単なる形象として読むので錯誤するわけだ。
↑
・これは弁解のし過ぎである。何もその他大勢と一緒にする必要はない。安井のエロチシズムは、涅槃深喜によって発想されるものだから、生の根源にかかわっている。
・安井氏のモチーフは(補遺)
・涅槃幻想である。
・即身入寂の幻想である。
・褻と翁媼。
・ヨーガの世界である。
・もう一つの哲学的言葉で語ることが出来ない。パラフレーズが効かない(西東三鬼の世界はパラフレーズが効かない)。
・実存がドカンとすわっているらしい。
・これ假作の戯言である。
・無時間――時間魔境を含んでいる。
プルースト
カフカ
・精神の体系(秩序)を成ずるのは嫌いである。
・もどきの思想
三段論法で云い切ってしまえば俳句内リアリズムということである。これは、俳句内というカッコ附きである。勿論、リアリズムから追いかけても何も開かれるものではない。ヒョウタンからコマが出たように、何かをいぢっていたら、リアリズムが出てきたという不思議な話なのである。
すなわち、もどきとは、
俳句に対して、俳句を対てることである。
俳句に対して、俳句でもどくことである。
にせの俳句の城
にせの城 を樹てることである。
さて、俳句とは何か。
諸君は高柳重信にならって、俳句形式という言葉を使っている。何の疑いもなく俳句形式といっているが、
俳句は俳句形式であろうか。
俳句は俳句形式と、さらに肉体があると思う。
肉体は假に俳句性という言葉で云いのがれておこう。
さて、俳句は、形式と肉体をもちつつ、それ自身、本質を拒否しつつなを幻想の彼方に俳句と思われる本質がある。それは「時間」の物差しでしか。
(ここには、高柳重信の理論の導入があるが)
不在を不在で証明する――虚数の導入
↓
俳句を俳句で証明する。
つまりもう一つの俳句をつくることである。
もう一つの俳句とは、
それはあのものどきを演ずは老人でなくてはならない。
老人という倒錯されたリアリズムを必要とする。
高柳の場合、
俳句をあざむくことによって自己の詩を立て(㐧一段)、
自己の詩をあざむくことによって俳句につながる(㐧二段)
高柳の二段構造がある。
不在を不在で証明する。
高柳が自己の作品を俳句でないと云い切ってしまえば、神の不在を実存で証明して終る。
しかし俳句と繋がるわけですよ。
俳句と繋がらないと、自分はすぐ消えるわけです。
何処か、繋がっていないといけないわけだ。
従って、㐧2の犯罪を犯すわけですよ。
しかし利工ですから、犯罪でなく、不在を2回証明することによって、俳人証明となっているわけです。
某月某日
・主語の移動
主語がたえず移動することによって、それはもはや主語ではない。
・主格の黙示
ただ主語の移動によって、主格が黙示されるのみである。先験的に、いや言語内経験によって黙示が与えられるのみである。
・詩は述語によって、
ある先験的な存在が書かれるにすぎない。それは、言語の中に假象として生起するだけである。
・〝瞬走〟という言葉は辞書にはない。
・俳句は〝相対性理論〟の中で書かれるものである。
俳句自身が、俳句絶対として存在することはない。つねに〝二つの故郷〟にまたがって存在しており、それは幻想としての俳句と、私有性の俳句として歪曲しあいながら〝経験〟の中に生きるのである。
安井浩司という個人にとって、方法論とは有季定型であろう。
「父がいま百人塚の気がして帰る」を書いたとき予感があったことを思い起こす。しかしそれが、
阿父学は、私、安井浩司がそういう題をネツゾウしたのではない、安井一族が、
停止の世界
中止の世界
和的観想であり
観念的レアリズムであり。
「阿父学」においては、どの句もそれぞれが実存あると執って強調したいような。
「中止観」「阿父学」へと書き続つてきた私の構図は、一つの窮極の形式を追いつづけるだけで、連続的なものであった。
「瑞加師地論」によれば、実の十の、虚の十の完成されたものとして三段に分析するが、しかし私は生成拮抗の美学になえし実存の停止、存在者の停止を考えたのである。
だから我は、我の村の僻者として、あのランボオのボワイヤンに通ずる別次元の人格をもつことであった。
しかし人間とは距離である。
私は耕衣論に似て、あらゆるものを集合するのが好きである。
生涯胃弱であるくせに、それは大酒をくらい肉食をよくし。
新しみは俳諧の華なり、とたいへん青年を嬉ばせてくれる言葉に酔っていた時から私も老いた。
かつて、俺はもう駄目だ、言葉が中年になるという事が不可解である。
朔太郎が(老いた、これからは青年を欲する)という言葉がよく判らずにいたが、しかし次第に判ってきた。いや判るような実感がある。
このよう■を光にとかがげる朔太郎の心理のニヒリズムにひかれる。■ぼやくのはよいが、■を祈文に掲げるのである。
(続く)
■ 鶴山裕司さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■








