 社会は激変しつつある。2020年に向けて不動産は、通貨は、株価は、雇用はどうなってゆくのか。そして文学は昔も今も、世界の変容を捉えるものだ。文学者だからこそ感知する。現代社会を生きるための人々の営みについて。人のサガを、そのオモシロさもカナシさも露わにするための「投資術」を漲る好奇心で、全身で試みるのだ。
社会は激変しつつある。2020年に向けて不動産は、通貨は、株価は、雇用はどうなってゆくのか。そして文学は昔も今も、世界の変容を捉えるものだ。文学者だからこそ感知する。現代社会を生きるための人々の営みについて。人のサガを、そのオモシロさもカナシさも露わにするための「投資術」を漲る好奇心で、全身で試みるのだ。
小原眞紀子
第十一回 オプションⅡ――雪豹の空売り
二人の友人と出会うきっかけになったオプションについて、なのだけど。
以前にも書いたが、大家さんの友達がとても多い。そうするとフェイスブックを通して、新しい友達申請がくる。もちろんフェイスブックの友達は友達ではないのだけれど、繋がりを承認すると、すぐにこちらの身辺調査を始める人がいる。たいてい営業目的で、いちいち目くじら立てないが、「メンター」がいるか、と聞かれる場合がある。
メンターとは「師」で、ようするに自身が言いなりになる人、という意味合いだ。不動産投資のメンターだったら、ほんとに「師」ならうるわしいけれど、その人の言いなりに土地建物を買うことになる。逆に言えばメンターになれば、営業的にはひどく効率がいいわけだ。いつだったか新しく知り合った人に、あるプロの不動産投資家の噂話をしたら、「その人があなたのメンターですか?」と訊かれてショックだった。わたしは物書きですよ。物書きが認知症を疑われたようなものだ。まあ、すでに他にメンターがいるなら用はない、ということだろう。昔なら「彼氏いる?」と訊かれたものだったが。
金融関係のセミナーを開催している人たちは、常に生徒さんを募集しているので、やはりメンターのいない(ウブ出しの)初心者を求めているようだ。わたしはと言えば『株塾』というその名の通り「しゅくだい」が出たり、「おともだちとツアー」に行ったりする学校みたいなところにすでに在籍していて、子供に返った気分で楽しい。そちらの先生はいつも毅然として、一発のトレードで30億円も張られるし、メンターとして信奉する生徒さん(と言っても結構な高齢者…)は多い。いずれも熱心なぶん、成果を上げている大先輩なのだけれど、メンターとかいうのは、やっぱり違う気がする。わたしは物書きなので、そういうのは絶対ダメという教育を若い頃から受けてきた(誰からだ?)せいなのだが。ただ、一発30億張る人もやっぱり二本足で、(成城学園前の)吉野家でときどき牛丼食べるというのを目の当たりにするのは、とてもいいことだと思う。
さてメンターのいないわたしだが、理想や憧れの対象はある。メンターでなく、アイドルと言うべきか。もちろん誰を見ても、すごいなー偉いもんだなーとは漠と思うわけだが、まじカッコイイと心酔するのは、映画にもなった例の有名な『世紀の空売り』だ。リーマンショックを予見したごく数人だけが周囲の非難をものともせず、やがて崩壊するサブプライム関連デリバティブの空売りを溜め、ついに巨額の利益を得たというノンフィクションだ。
まあ他人が儲けた話に感動することはなくて、自分の頭できちんと考えた者だけが真実にたどり着く、という正当性、清々しさにこそである。サブプライムローンとは格付けの低い住宅ローン、すなわち返済の焦げ付きが懸念されるものだった。その債権を集め、切り刻んで別の運用商品にすると、不思議なことに格付けが上がった。集めて切り刻むことでリスクが分散されたからだという。しかしそんなことはあり得ないのは、小学生だってわかる。当たりの目が6分の1しか出ないサイコロを集め、またそのサイコロをもっと小さな立方体のサイコロに切り刻んだところで、期待値は変わらないではないか。
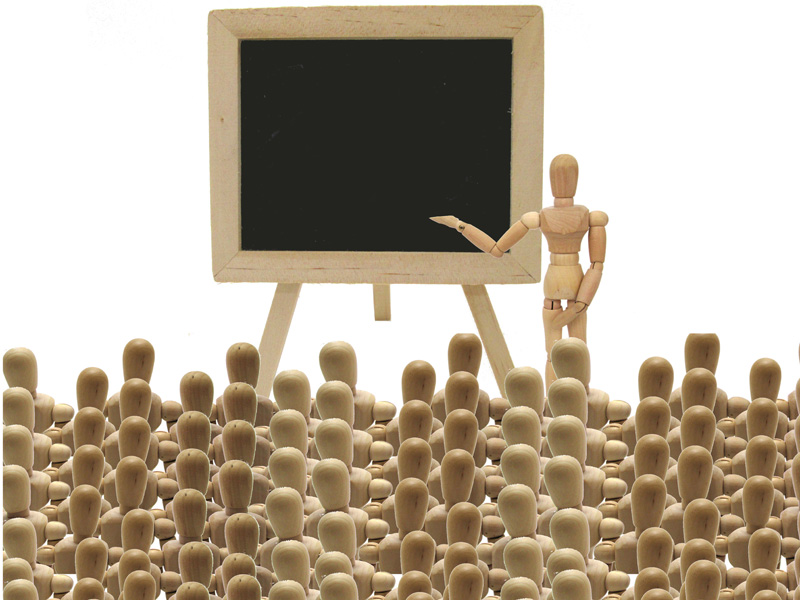
小学生だってわかることを、小学生のように率直に口に出したのは、弛緩した大人の世界のしがらみと無縁な変わり者だけだった。サブプライムローンを組み込んだ運用商品は、上場した株式ではなかったから、まずは「空売り」ではなく、CDSという保険商品を作らせて買い込んだ。わたしのイメージするところ、これがオプションに近い。わたしが初心者向けのオプションセミナーに惹かれたゆえんだ。単なる憧れである 笑。
『世紀の空売り』に登場する変人たちの格闘は、しかしそう容易くはなかった。掛け捨ての保険でも大量に買い込めば相当な出費である。それから崩壊するまでの期間は1年や2年ではない。サブプライムローンの欺瞞を見抜くのが早すぎたのだろう。自ら運営するファンドの顧客から浴びせられる非難は激しくなる一方で、ゴールドマン・サックスなどの金融マンたちのこの世の春は続く。しかし彼らの誰も、行政機関や経済学者らも誰一人として事態を正確に把握していなかった。いや、把握することから目を背けていたのだ。
このエッセイの読者のなかには、どの世界も同じだな、と思われる方がいるだろう。まったくである。ちゃんと頭で考えればそうなるに決まっているのに、目の前の状況が変わるまで、絶対に直視しようとしない。世間の大半はそんなもので、大半がそうだから、それに従うのが正しいと思っている。文学状況などは突きつけられるものが遅れて来るだけに、なお一層そうである。
かつてナチスドイツ政権下で『アインシュタインに反対する100人の著者』という本が出版された。アインシュタイン博士は「わたしが間違っているなら、1人が反証すれば事足りる。100人は必要ない」と言われた。科学者らしい、これもカッコイイ言説だ。ただ、世の人は100人もいるから確からしい、と思うものだ。それがあらゆる欺瞞をギリギリまで包み隠す。その100人の誰一人として、最後に責任をとることはない。
昨今の大学の授業は、文科省の指導でアクティブ・ラーニングが推奨されている。わたしの授業は文科省に言われる前からアクティブ・ラーニングで、学生の発表に対して1人ずつコメントを求めることもある。そうなると頭で考えない、その場の空気を読んだだけで、発表者の間違った解釈を褒め称える学生が続くことがある。頭にきたわたしは「帰って風呂入って、飯食ってもう一回、考えろ。しゅくだい!」と言う。すると翌週の出席率は半分だ。
当てられたって死にはしないのに、情けない。出席した学生たちに、わたしは『12人の怒れる男たち』という映画の話をする。アメリカの裁判で、ある少年が殺人の容疑者であった。12人の陪審員のうち11人が有罪と認めるが、たった1人が納得しない。多数決は認められず、早く帰りたい11人は苛々を募らせる。そのたった1人は、ほんの些末なことが矛盾していると、いつまでもグズグズ言うのだ。が、そのうち1人、また1人とそれに耳を傾けはじめる。あり得ない。その矛盾があるかぎり、少年は物理的に殺人は犯せないのだ…。
「もしこのとき、この1人の変人がいなかったら、少年はどうなってましたか」と、わたしは学生に問う。ちなみにこの映画はモノクロで、当時の日本に陪審員制度はなく、この映画のパロディ『12人の優しい日本人』(三谷幸喜)が海外でも人気を博した。空気読むなって、我々には無理か。無理なのか…。
世間の空気を読みたくないので、うちにテレビはない。たまたま実家に帰ったとき、ユキヒョウの狩りを見た。獲物を追いかけて崖際に追い詰めると、まったく躊躇なく飛びかかる。もろともに宙に浮かび、崖を転がり落ちてゆく。唖然とした。崖下で獲物は息絶え、ユキヒョウは傷ひとつなく獲物を引きずっていく。岩に何度も打ち付けられていたのは獲物の方で、ユキヒョウは身体のバランスをとりながら、いわば重力を味方に、岩肌を武器として地面に降り立った。
このようでありたい。実家で煮魚の箸をくわえたまま強く思った。距離感とバランスですべてを力に。めったに撮れない映像だそうで、もしかしてテレビって素晴らしいのか。なにしろアイドルはテレビで見い出すものらしく、今のわたしにはユキヒョウである。
小原眞紀子
* 『詩人のための投資術』は毎月月末に更新されます。
株は技術だ、一生モノ!
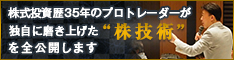
■ 小原眞紀子さんの本 ■
■ 金魚屋の本 ■







