
『恋する日曜日』第10話『ロンリィザウルス』(2003年6月8日BS-iで放送 主演 内山理名 北村一輝 脚本 福田裕子)より
ずいぶん以前、メル友(って死語。どんだけ昔なんだ)になった編集者と、何で泣けたか、というやりとりで盛り上がったことがある。盛り上がったといっても、あるある、と共感し合ったわけではまったくなく、互いの理解できなさかげんに驚いたのだ。確かに昔の話で、きっかけは中国の映画『初恋のきた道』だった。主演のチャン・ツィイーが可愛いくて大人気となった出世作だ。
田舎の教師だった父が死んだという知らせを受け、青年は村へ帰る。父は校舎の建て替えの陳情に出かけた町で倒れ、遺体を車で運んでこようとするが、母が反対する。昔ながらの儀式にのっとって村人たちが葬列を組み、柩を担いで運んでほしいと言う。担ぎ手となる若者たちは皆、出稼ぎで村にいないというのに。年寄りのわがままに青年は困り果てる。
父は若い頃、教師として村に赴任してきた。初めて小学校が建つことになったのだ。彼に憧れた母だったが、学のない村娘に過ぎず、できることは他の女たちとともに料理を作り、建設現場に運ぶことだけだった。やがて文化大革命の嵐が吹き、若い教師は町に連れ戻される。何も告げずに去った彼を追い、食べてほしかった手料理を持って山道を走る娘の姿に、映画館は若い女性のすすり泣きでいっぱいだった、と(メールで)聞いた。
この泣きどころが私にはまったく理解できず、ひとつにはチャン・ツィイーは可愛かったけれど、若い教師の方がなんか襟足をカリアゲにしちゃって、いまいちタイプでなかったせいもある。そんないい男かあ、とか、一時の気の迷いちゃうか、と思ったら泣けない。泣けないのは楽しめないということでもあるから、損した気分でもある。
ようするに恋愛というのは、そのチョイスが唯一無二というわけではなかろう、と他人には思えてしまうものなのだ。村には他にインテリの若い男はおらず、という説明になれば、そこに計算や都合も匂ってくる。他の若い教師ではだめなのかもしれないけれど、そこは説得力がない。

村娘は町へ続く道に立ち、来る日も来る日も待っている。それもすごい。忠犬ハチ公みたいだ。やがて文化大革命の嵐が吹き止んで、彼がその道を帰ってきて結ばれる。めでたしめでたし。
それで、かつて村娘だった年老いた母は、町で倒れた父を運んでくるのに車ではだめだ、と言い募るのだ。まあ、そりゃそうだろう。車じゃだめだ。だめに決まってる。かつてその道を歩いて帰ってきたのだから、と思った瞬間に泣けてきた。年寄りのわがままには理由がある。若い娘の思いのたけは気の迷いかもしれないが、連れ添った長い年月は、それを唯一無二のものにする。と、自分では理屈がつくし、制作の意図だって泣きどころはここだろうと思うけれど、映画館の大多数からしたら私の方が変なやつだ。
だいたい、そういうのは他人には理解し難いので、それがわかんないなんてニブい、と決めつけるのはよろしくない。サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』に「あんなインチキ映画で泣けるやつなんて、そいつもインチキに決まってる」とかいうくだりがあって、確かにそんなふうに思う瞬間もあるけれど、そもそも人がそのシーンのどこに感応しているのかもわからない。画面の隅でチンチンしてる犬が死んだ愛犬にそっくりだと思って泣いてるのかもしれない。昔、友人に「安全地帯のヒット曲『悲しみにさよなら』のタイトルはサガンの小説『悲しみよこんにちは』からとったんだと気づいたら、泣けて泣けてしかたなかった」と真顔で言われ、困惑したことがある。
それでも、そこが理解できないのはやっぱりおかしい、少なくともプロがわからないってことないだろ、と言いたくなる瞬間はある。文学金魚に連載していた「文学とセクシュアリティ」でも書いたし、サスペンス小説のネタバレになるので詳しく繰り返さないが、パトリシア・ハイスミスの『殺意の迷宮』のラストは衝撃以外の何ものでもなかった。ほんの一、二行でそれまでの思い込み、大前提が崩れ去ってしまったのだ。
最後にひっくり返る、というかたちは典型的なミステリーだけれど、それが人間の無意識、感情の根本にかかわるので、びっくりすると同時に滂沱の涙にもなる。一方で、見い出されるのは目に見えない深い感情で「犯人」などではないから、そこをスルーしてしまう人も多い。最初は出版を断られたそうで、プロの編集者までも、ということだ。ある出版社の社主は「ハイスミスの小説は二度と私に読ませるな」と言ったそうだし、実際、ラストの意味に気づかなければ退屈きわまりない大作だ。私も「ハイスミスにはめずらしい失敗作だなあ」と飛ばし読みをしていて、最後のページに仰天して頭から読み返した。そういうことだったのか、と思いながら読み返したときの面白さといったら。大きな賞を獲っているから、その審査員は少なくともわかったはずだ。
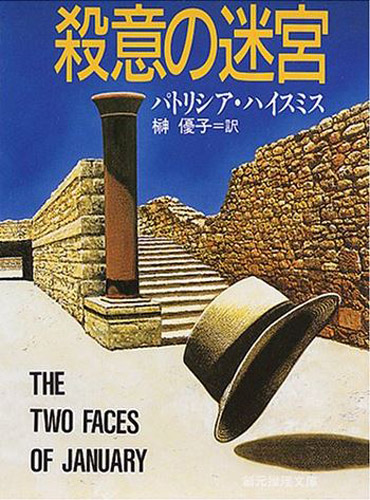
こうやって考えると、どうやら私の涙腺に触れるのは「気がつかなかった」というところなのかと思う。自分がウカツにも気がつかなかったということに気づかされると、いきなり涙腺が緩む。申し訳なさ、みたいな感情もあるかもしれない。これは普段、何でもわかってるつもりの人間にありがちなのではないだろうか。もちろんそれ自体、大いにウカツなのだが、でもやっぱりどこかで気づいていた、ただ意識に上らせなかったのだ、という気もする。無意識というものが立ち上がってくることに対して、すごくヨワいのだ。
デュラスの『愛人』のラストに近いところに「愛していたのだが彼女には見えなかった愛、水が砂に吸い込まれて消えてしまうように、その愛が物語のなかに吸い込まれて消えていたからだ、そしていまようやく、彼女はその愛を見出したのだった、はるばると海を横切るように音楽の投げかけられたこの瞬間に。」というところがあって、ここでもちょっとおかしいほど泣けた。『愛人』は中国人の愛人と少女との恋愛小説ではなく、母親や兄をも含め、少女が見い出す愛の観念そのものの物語だ。引用部は「ちょうどのちに、死を横切って、下の兄の永世を見出したように。」と続く。
デュラスの愛の観念は、メタファーとしては「海」そのものだ。無意識としてのその立ち上がりは、説明のつかない恐怖にもなる。それについての考察は、また別にすることにして。
いつも人と違うところで泣ける、という感受性自慢みたいなもので終わればいいのだが、実はそうでもない。なかなか恥ずかしくて言えないような、ごく凡庸な涙腺の記憶もある。それはそれで、自分はマトモな人間だとアピールするようで気がひけるが、意外に子供にまつわるものが多い。子供というのが何も考えてない、無邪気というより無意識の象徴だとしたら、それをブロックする大人の意識的なタテマエみたいなものがあって、その制度が崩れ去る瞬間に泣ける、みたいな。
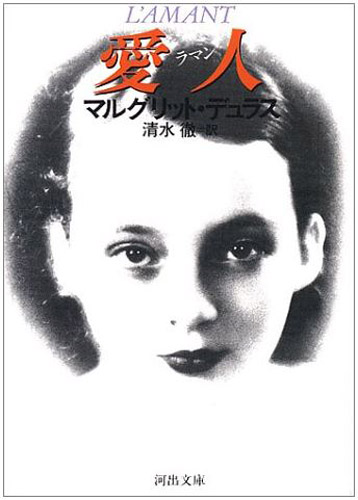
椎名誠さんのエッセイだったと思うけれど、ネパールかどこかを探検していた男たちが山村の少年に、ビールを買ってきてくれと頼んだ。いつまでも戻らない少年に、その辺では見たこともないはずの大金を渡したのだから、持って逃げても無理はない、と言い合って忘れてしまう。何日もたって少年が泥だらけでビールを引きずって現われ、目当ての町になかったから山を越えて先まで買いに行った、と言う。大の男たちは人目も憚らずわんわん泣いた。私たちもまた、この男たちの涙を通して涙することができるので、少年は何のことやらと思っているだろうし、そうでなくてはならない。
思い出すだけで泣けてきてしまうのだけれど、あの池田小事件で無差別に刺殺された子供たちのうち、一人の男の子が救急車の中で息を引きとった。そのいまわの際の言葉が「今夜お父さんが帰ったら、いっしょにお風呂に入る約束をした」。こんな悲しい話はないが、裁判でその調書を読み上げた検察官が思わず声を詰まらせたと聞くと、さらに涙を誘う。
これは私が名付けるところの「勧進帳効果」というものでもあろうか。山伏を装い、関を越えようとした義経と弁慶が関守に見咎められる。弁慶は、主君ではないと示すために義経を激しく打つ。関守は納得がいったと二人を通してやるが、彼らが義経と弁慶であることはわかっている。関守がわかっていることを、弁慶もわかっている。
この話が日本人の琴線に触れるのは、義経の打たれる痛みのためでも、命を捧げて守る主君を打たねばならない弁慶の辛さのためでもない。弁慶の内心の涙に感応した関守が、関守としての建前を形骸化し、わかっていて彼らを逃してやる。その心が弁慶にも、少なくとも無意識下では伝わっている、というところである。プリミティヴな感情が、裁判や検察、あるいは封建制といった制度のど真ん中にふと、しかし決定的に現われる瞬間に、私たちはめっぽうヨワいのである。
それと、これは恥ずかしくて、今まで誰にも話したことはないのだが、なんということもないの深夜の完結ドラマを観て、終わってからずっと大泣きしていたことがある。
平凡なOL(内山理名)のところにヤクザの抗争で傷ついたチンピラ(北村一輝)が転がり込む。何もしないから、という彼は部屋の中でおとなしく、大きな動物をかくまっているかのようだ。吉野家の牛丼が好きで、ソースなんかかけない、と気どるOLの丼に勝手にかけてやったりする。
やがて彼は、警察に自首するという。待っててくれる人がいると思えるから、そういう気になったと。そこはファンタジーなのだが、二人は互いに名前も知らない。何もしない、という当初の約束のままの雰囲気で、男女というより、やはり動物と暮らしてるようだ。実のところ内山理名という女優さんはあまり好きではなかったが、 孤独に浸り、平穏を優雅さとして過ごす普通のOL感がよかった。恋人ができたというより、部屋に動物を飼いはじめただけ、という動じない感じも。

『恋する日曜日』第10話『ロンリィザウルス』より
自首を決心した直後、彼女の誕生日にケーキを買いに出た彼は、敵のヤクザに見つかって撃たれる。川原の土手に転がり、携帯で彼女に電話する。今、外に出てるから、帰るまで待っててくれ、 と、繰り返し念を押して絶命する。彼女は何も知らないまま、呑気に家路につく。
それでこの、なんてことないVシネ(?)みたいな深夜ドラマのどこが琴線に触れたかといえば、このひたすらな「待っててくれ」だったろう。恋愛ものでは泣けないのだから、名も知らぬ普通のOLに執着する男の話として観たのではないと思う。『ロンリィザウルス』というタイトルで、異形の恐竜じみて、それがとにかく誰かに待っててほしい、死をも超えて、ただ待っていてほしい、という切なさがたまらなかった。
物書きだから、ドラマも映画も所詮は脚本次第、俳優がどうこういうのは好み以上のものではない、とどこかで思っていた。(それにだいたい、病的なほど人の顔が覚えられないタチなのだ。)だがこのときたまたま観た“淋しい恐竜”は忘れられなかった。北村一輝という名を知ったのはずいぶん後で、やはり偶然観た単発のサスペンスドラマでは犯人役をやっていた。その脚本も素晴らしかったが、なんといういい俳優だろうと、ほとんど呆れた。好みなどではない(好きなタイプの男性とか、そういうのでない)、確かに演技というものの価値はあって、恥ずかしくて人に言えないか言えるかは別として、それでハイスミスの傑作と同じくらい泣かされることもある、ということを初めて認識したのだった。
小原眞紀子
新企画
泣けたコンテンツを Twitter で大募集! なぜかこれが泣けた! あるいはなんでこれに泣けない? など。『#あなたが泣けるもの』まで!。
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![初恋のきた道 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ygyiNUXwL._SX250_.jpg)


