 「日本が世界に誇れる真にオリジナルな文学は俳句である。一方で俳句は前衛的試みを失った途端に凪のような有季定型写生の停滞に沈み込んでしまう。しかも直近の前衛俳句の総括すら正確にできていない」(鶴山裕司)。池上晴之氏との対話「日本の詩の原理」、「安井浩司研究」の鶴山氏が、安井氏旧蔵の「俳句研究」誌などを元に前衛俳句の時代、即ち『高柳重信とその時代』を詳細に読み解く!
「日本が世界に誇れる真にオリジナルな文学は俳句である。一方で俳句は前衛的試みを失った途端に凪のような有季定型写生の停滞に沈み込んでしまう。しかも直近の前衛俳句の総括すら正確にできていない」(鶴山裕司)。池上晴之氏との対話「日本の詩の原理」、「安井浩司研究」の鶴山氏が、安井氏旧蔵の「俳句研究」誌などを元に前衛俳句の時代、即ち『高柳重信とその時代』を詳細に読み解く!
by 金魚屋編集部
はじめに(二)
桑原武夫は第二次世界大戦後に「俳句第二芸術論」を発表して俳句を厳しく批判した。「第二芸術」という用語からわかるように桑原は明治維新後に日本文学の主流となった自由詩や小説、戯曲など、作家の唯一無二の思想や感情が表現された欧米的自我意識文学を「第一芸術」と措定していた。実質的世界標準文学である。
この自我意識文学と比較すれば俳句には異質な要素が多い。俳句は原則五七五に季語の定型文学である。短い文字数に季語を入れ込めば必然的に写生的風物描写になる。俳人はそれぞれ全部違うと言うだろうが大局的に見れば似たような句が大量に生まれる。俳人は生涯に一万句、二万句を詠むことも珍しくない。が、そんな作品数自体自我意識文学ではあり得ない。俳句は型が生み出す文学である。
結社制度や句会についても同様のことが言える。自我意識文学で必要なのは絶え間ない自問自答である。私的にある作家に師事することはあっても結社制度はもちろん句会での相互批評も必要ない。
では桑原「俳句第二芸術論」に俳人たちはどう反応したのか。典型的なのはまたしても虚子だ。虚子は「第二芸術であっても第三芸術であっても致し方ない。(中略)俳句の性質はかえることができない」と言った。二流、三流文学でもいっこうにかまわないと開き直ったのだった。ただ「俳句の性質はかえることができない」というのは直観真理である。
維新以降の近・現代人、つまりわたしたちは欧米的自我意識文学を文学の定義にしている。それ以外の文学定義は存在しない。実際江戸時代の芭蕉や蕪村作品も現代文学定義に沿って読解され評価される。誰もが結局は作家独自の表現だと論じる。優れた個性の天才神話がまかり通る。しかし芭蕉「古池」や蕪村「菜の花」はもちろん、明治の子規代表句「柿くへば」にもまったく作家の思想・感情が表現されていない。純客観写生句であり単純極まりない風物描写である。究極を言えば誰が書いてもいいようなアノニマスな句だ。その文学性は自我意識文学の批評方法では明らかにできない。
俳句のアポリアはここから始まる。このアポリアに真っ向から挑んだのが前衛俳句運動の俳人たちである。それは富澤赤黄男から始まり高柳重信によって継承され加藤郁乎と安井浩司に至って終熄した。今でも重信代名詞である多行俳句を書く俳人はいる。従来的俳句を嫌って結社無所属で郁乎や浩司風の前衛的俳句を書く作家もそれなりの数いる。しかし彼らは前衛俳句の継承者ではない。多行俳句は既に無季無韻俳句などと同様に形骸化している。前衛風の俳句を書く俳人たちも同様だ。前衛俳句運動が有していた作品と理論の密接なせめぎ合いが失われてしまっている。俳人の習い性で優れた先人の型をなぞっているだけだ。
虚子は子規文学の実感把握によって〝俳句はどう足掻いても五七五に季語の定型であり写生表現にならざるを得ない〟という直観真理を得た。しかしそれ以上俳句について探求しなかった。「俳句は国民文学である」と言ったがそこに〝俳句定義〟はない。五七五に季語定型を守れば最低限の〝文学要件〟を満たすとどんどんその敷居を下げていった。そして大多数の俳人が虚子の形式的俳句定義に右へ倣えした。それが現在にまで至る俳句の現世的賑わいをもたらしている。虚子大先生の俳句文学定義に従えばお遊び習い事芸だと批判されてもすべては崇高な俳句文学のためと無視することができる。だがそれはいかにも日本的ななあなあ主義だ。文学でありかつ現代文学定義では捉えきれない日本独自の特徴を持っているならなおのこと、俳句の原理は厳密に解明されなければならない。
前衛俳句の俳人たちは言ってみれば秋櫻子が提唱し新興俳句まで続いた主観俳句を極限まで探求した。俳句を現代文学と比肩し得る自我意識文学にまで高めたのである。しかしそれは現代文学と同質の文学にはならなかった。俳人たちが闘う相手は自己や他者(社会)ではなく究極を言えば俳句形式だったからである。ただし強烈な自我意識を行使しなければ俳句形式の本質は露わにならない。
前衛俳句最大の功績はそれまでの前衛的試みのように俳句定型に足し算・引き算するのではなく、俳句形式の原理を探って定型の中で自由を得る方途を明らかにしたことにある。俳句が原則五七五に季語定型であるのは今後も変わらない。誰にも変えられない。しかし俳句が五七五と季語定型で何を表現しようとしているのか、その原理を正確に把握すれば自在な表現は可能である。
戞々とゆき戞々と征くばかり
網膜にはりついてゐる泥濘なり
蛇よぎる戰にあれしわがまなこ
一本の絶望の木に月あがるや
新興俳句俳人であり前衛俳句の礎となった富澤赤黄男は明治三十五年(一九〇二年)に愛媛県で生まれた。明治末から大正時代に生まれた青年たちの多くが徴兵されたが赤黄男は昭和十二年(三七年)十一月、三十六歳(数え年)の時に日中戦争で華中に出征した。盧溝橋事件に端を発した日中戦争勃発は十二年七月七日であり激戦最中の召集だった。以後十五年(四十年)五月にマラリアに罹患して応召解除となるまで約二年半戦地を転戦した。
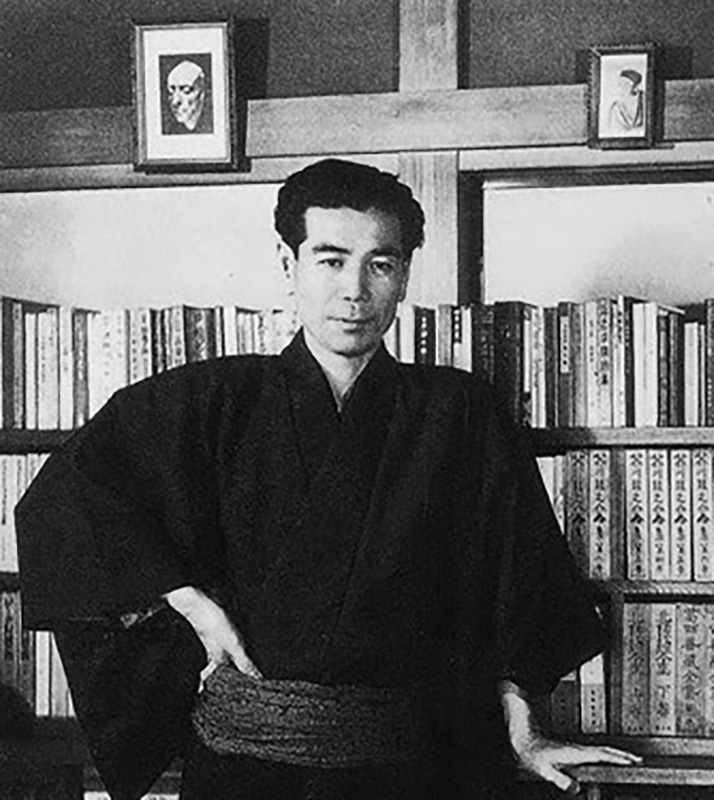
「戞々とゆき戞々と征くばかり」などの句は戦地で書かれた。日野草城主宰の「旗艦」に掲載され第一句集『天の狼』に収録された。「旗艦」は「京大俳句」などと並ぶ新興俳句系句誌である。句を読めば赤黄男が凄惨な戦闘を体験したことが手に取るようにわかる。ただ井上白文地「我講義軍靴の音にたたかれたり」や西東三鬼「機関銃眉間ニ赤キ花ガ咲ク」といった直截な戦争批判句ではない。戦争の悲惨の客観的描写であり内面化された風物で心身の疲弊と絶望が表現されている。
赤黄男が応召解除となった昭和十五年(一九四〇年)二月に平林静塔、井上白文地らが治安維持法違反の嫌疑で検挙された。最初の新興俳句弾圧である。弾圧は最も旺盛に反戦句を書いていた同年八月の西東三鬼検挙で一応終熄した。しかし赤黄男には累が及ばなかった。また初出語句を多少宇穏当なものに置き換えているが『天の狼』は検閲差し止めになることなく翌十六年(四一年)に刊行された。検挙俳人の多くが銃後俳人であったのに対し赤黄男が従軍兵士だったことが影響したのかもしれない。赤黄男句があからさまな反戦句ではなかったことも弾圧を免れた理由だろう。
虚子は俳句は「花鳥風月」だと見切っていた。花鳥風月以上でも以下でもないと言い切った。関東大震災直後には「地震が俳句になりそうにない」と言い、「戦争というものは、俳句に詠むには適さないのではあるまいか」と言って実際震災句も戦争句も書かなかった。虚子は俳句は人間の自我意識表現のための器ではないという断念に近い認識を抱えていた。それは正しい。では赤黄男はどうなのか。
蝶墜ちて大音響の結氷期
椿散るああなまぬるき昼の火事
海峡を越えんとして紅きものうごく
これらの句は赤黄男が最初の応召を解除された後、マラリアの療養中に書かれた。官憲による新興俳句弾圧最中の句である。
「蝶墜ちて大音響の結氷期」が太平洋戦争に突入してゆく当時の世相をクッキリと描き出した作品であるのは言うまでもない。安西冬衛「てふてふが一匹韃靼海峡 を渡つて行つた。」(『春』)や北川冬彦「軍港を内臓してゐる」(『馬』)と並ぶ優れた一行詩としても読める。もちろん「椿散る」「海峡を越えんとして」も不安な世相を言語化している。しかし直截に赤黄男の自我意識が表現された句ではない。極論を言えばこれらの句は虚子が言った〝花鳥風月の枠内〟に留まっている。それが赤黄男の句を多くの新興俳句の中で突出したものにしている。たまさかの偶然でこういった句は生まれない。そこには赤黄男の強い思想がある。
俳句の本質ということが、しきりに言はれる。これの安易な使用が紛糾のもとになる。
俳句の本質は、勿論、文学の本質の謂ひだ。俳句も詩も小説も、文学一般を貫く一本の筋金のことでなければならぬ。
各ジャンルは、各々の特性に於いて、各々のジャンルなのである。本質は本質で特性ではない。
こんなところから、季題季語まで俳句の本質だなどと言ふものが出てくることになる。ここで話が、ますますこんがらがることになる。
富澤赤黄男『雄鶏日記』
数少ないが赤黄男は優れた詩論を書き残している。その思考は原理的だ。99・9パーセントの俳人たちの思考は俳句の本質は「季題季語があること」でピタリと止まる。それ以上何ひとつ探求しようとはしない。しかし赤黄男は「季語季題」は俳句が他の文学ジャンルと区分される「特性」に過ぎないと論じている。では俳句の「本質」とは何か。
詩は〈完成〉を希求ひながら、しかも、みづから〈完成〉を拒否しつづける――この根源的な矛盾が、われわれを詩に趨かしめる。
詩には〈結論〉というものはない。〈必然の過程〉だけがある。
〈純粋〉とは、〈意味〉を峻拒したものが、そこから〈新しい意味〉を創り出すもののすがたであらう。
詩人は、自己の《詩》によって、自己の〈限界〉を超えようとする悲願の中に生きるほかない。
詩人とは、つひに永遠に〈実験するもの〉でしかないのではないか。
詩のもつ〈空間〉は、つねにまた《詩》によって極度に〈充塡〉された〈空間〉である――詩の、〈書かれない〉部分が背負つてゐる〈重量〉を思ふ。
俳句をのりこえた俳句をめざして・・・・・・
富澤赤黄男『クロノスの舌』
赤黄男は「詩」や「詩人」という言葉を明治維新以降に新たに日本文学に加わった自由詩の文脈で使っている。自由詩は欧米詩の翻訳から始まった文学ジャンルである。江戸時代までの漢詩が最先端の中国文化の流入窓口だったように維新後は自由詩が最新欧米文化の流入・受容の受け皿になった。自我意識文学であるのは言うまでもない。また日本の自由詩は一貫して日本文学における前衛の役割を担って来た。「詩は〈完成〉を希求ひながら、しかも、みづから〈完成〉を拒否しつづける」「詩人とは、つひに永遠に〈実験するもの〉でしかないのではないか」といった言葉からわかるように赤黄男は自由詩の特徴を正確に理解している。
この俳句に自由詩的自我意識と前衛性を取り込もうとする姿勢は赤黄男以降の高柳重信、加藤郁乎、安井浩司といった前衛俳人に共通している。赤黄男がその基礎を作ったと言っていい。実際赤黄男や郁乎、浩司は一時期自由詩の創作を行っている。重信の自由詩作品は確認されていないがその実質的主宰誌「俳句評論」で詩人たちと密に交流したのは周知の通りである。また自由詩への接近は〝詩とは何か〟を確認するために必要だった。
短歌はすべての日本文学の母胎である。五、七の韻律を定着させたのはもちろん物語、謡曲、俳句といった文学ジャンルを生み出した。王朝短歌で頂点を究めた短歌最大の特徴は〝わたしはこう思う、こう感じる〟の自我意識表現である。しかし『万葉集』やポスト『新古今和歌集』の源実朝短歌はほぼ純粋な写生短歌である。また短歌は明治時代に自由詩(新体詩)の接続基盤として機能した。北原白秋を生んだのは与謝野鉄幹・晶子の「明星」だ。短歌は現代に至るまで――いささか不気味なほど――日本文学の母胎として蠢いている。短歌では五七五七七の定型を守っていれば文学だという不文律は存在しない。内容面か形式面で優れた特徴を有していなければ秀歌として認知されない。当たり前のことだ。
これに対して七七を切り落とし五七五の最短形式に季語必須として成立した俳句は表現領域が極端に狭い。俳句は日本文化が内包している〝循環的かつ調和的世界観〟を表現するためにある。それは季語――季節の移り変わりに表象される。虚子が〝俳句は花鳥風月〟と断言したのはそういうことだ。金魚の糞のように虚子につきまとうならそこまで認めなければならない。ただ一方で俳句の極端なほどの表現可能性の狭さは虚子による〝五七五に季語定型を守っていれば立派な文学だ〟という戯言を生んだ。師の正岡子規はそんなことは言っていない。俳句界では優れた句は三十年、五十年経たなければ明らかにならない。凡百の現存俳人たちが自分が所属する結社主宰(師匠)や友だちの句を評釈と称するこじつけで過大評価しまくっているからだ。俳句界ほど〝詩とは何か〟〝優れた詩とは何か〟が分かりにくいジャンルはない。
種田山頭火や尾崎放哉の句を持ち出すまでもなく優れた俳句は五七五に季語定型でなくても成立する。しかし無季無韻派の俳人たちは徒手空拳だった。赤黄男が自由詩に詩の原理を求めたのは自由詩が形式・内容面でまったくなんの制約もないからである。優れた詩は作者が〝これは詩である〟と提示し読者が〝これは詩であり優れている〟と認知した時点でその都度成立する。それは一瞬のことだ。詩は直観的断言表現だから優れた詩は一瞬で認知され認知できる。また短歌のように形式を持たない自由詩の方が詩の原理を把握しやすい。ただもちろん俳句は形式文学であり赤黄男は形式内で前衛であろうとした。
石の上に 秋の鬼ゐて火を焚けり
神怒り 神怒り 人消えゆけり
いっぽんの枯木に支へられし 天
稲光り わたしは透きとほらねばならぬ
葉をふらす 葉をふらすとき 木の不安
切株はじいんじいんと ひびくなり
赤黄男が残した句集はわずか三冊。第二句集『蛇の笛』は昭和二十六年(一九五一年)に刊行された。「あはれこの瓦礫の都 冬の虹」など戦中体験や戦後社会を表現した句もあるが多くの句が抽象性を増している。また赤黄男の自我意識を表現した句も増えるが強烈な思想や意志は表現されていない。「稲光り わたしは透きとほらねばならぬ」にあるようにむしろ自我意識の消滅が目指されている。それは「葉をふらす 葉をふらすとき 木の不安」「切株はじいんじいんと ひびくなり」といった句によく表現されている。
新興俳句俳人として赤黄男が強固な自我意識に基づく個性的表現を目指した作家だったのは間違いない。しかしその個性は対社会批判ではなく社会全体を俳句で表現することに向かった。初期の晴れやかな「蝶墜ちて大音響の結氷期」などがその代表である。しかし『蛇の笛』では明らかに表現が一回り小さくなり始めている。赤黄男は自我意識を縮退させモノに憑いて世界を表現しようとしている。モノに憑いた自我意識が感受するのは不安だ。恐らく複雑に膨脹し続けるそう簡単に相対化できない戦後社会が影響している。またモノに憑いた赤黄男の希薄化した自我意識が感受する不安は俳句で世界を表現し切れるのかという不安でもある。その意味で『蛇の笛』は赤黄男にとっての〝危機の句集〟である。
草二本だけ生えてゐる 時間
雨けむる あるひは白き砂上樓閣
沈默 ―― 天の埋葬いま始まる
石を積む宿命 鳥は水平に翔び
蛇よ匍ふ 火藥庫を草深く沈め
零の中 爪立ちをして哭いてゐる
第三句集で最後の句集となった『默示』は昭和三十六年(一九六一年)に刊行された。同年一月に赤黄男は体調を崩して入院し翌三十七年(六二年)三月六日に亡くなった。死期の近いことを予感した赤黄男が重信を呼んで刊行を依頼したのが『默示』である。そのため収録句数は三冊の句集の中で一番少ない。また赤黄男が長命なら違う形で刊行された可能性もある。ただ『默示』は正直な句集であり赤黄男俳句の前衛性がどのようなものであったのかを明確に示している。
『默示』というタイトルには『聖書』の「黙示録」――最後の審判とキリストの再臨――と「沈黙」のダブルミーニングが示唆されている。赤黄男はあくまで俳句形式の中に留まって新たな前衛的表現を模索した。彼が俳句形式を破壊しようとした気配は一切ない。しかし俳句形式の中で前衛表現を求めれば求めるほど句は奇矯な姿となっていった。なぜか。俳句を知り尽くしていたからである。
俳句における新たな表現は「砂上樓閣」であり俳句形式から逃れよう、根本から変えようという試みは「石を積む宿命」となり「鳥は水平に翔び」という結果になる。高く飛翔してくれない。ただそれを初めて言語化した俳人が赤黄男だった。赤黄男個人の句業に限れば「零の中 爪立ちをして哭いてゐる」が絶唱であり最高傑作ということになろう。直観把握として〝優れた詩〟だと感受することはできるが俳句としては行き止まりである。
比喩的に言えば赤黄男は俳句の〝零のエクリチュール〟まで下りた。前衛舞踏家・土方巽が「肉体は経験を超えない」という断念を持って晩年に前衛舞踏から能のような様式舞踏に転換しようとしたように、もし赤黄男の句業が続いていれば当然のように零からの脱却が求められただろう。言うまでもなく高柳重信がそれを受け継いだ。
重信は赤黄男が下りた零地点からプラスの、様式化への道を選んだ。ただ重信もまた生粋の俳人であり俳句を知り尽くしていた。赤黄男の「黙示録」に倣うように彼は「黒彌撒」――禁じられた黒魔術――によって不可能を可能にする活路を見出そうとした。
鶴山裕司
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 金魚屋 BOOK SHOP ■
■ 金魚屋 BOOK Café ■


