第1回 文学金魚大学校セミナー ① 三浦俊彦&遠藤徹

三浦俊彦:昭和34年(1959年)長野県生まれ。都立立川高等学校卒業後、東京大学文学部美学芸術学科を卒業。東京大学大学院人文社会系研究科(美学芸術学講座)教授。美学・哲学の研究者で小説家。和洋女子大学名誉教授。代表作に『M色のS景』、『この部屋に友だちはいますか?』、『サプリメント戦争』、『エクリチュール元年』など。文学金魚で『偏態パズル』を連載中。
遠藤徹:昭和36年(1961年)兵庫県生まれ。東京大学文学部英米文学科・農学部農業経済学科を卒業。同志社大学言語文化研究センター教授。アメリカを中心にした現代文化の研究者で小説家。代表作に『姉飼』(日本ホラー小説大賞)、『戦争大臣』(小説)、『プラスチックの文化史―可塑性物質の神話学』、『ケミカル・メタモルフォーシス』など。文学金魚で『ゆめのかよひじ』を連載中。
二〇一六年六月十八日に、東京目黒の日仏芸術文化協会で行われた第1回文学金魚大学校セミナーのレジュメをお届けします。トップバッターは三浦俊彦さんと遠藤徹さんで、お二人の小説作法についてお話していただきました。三浦さんと遠藤さんは二十数年来の友人ですが、三浦さんは学究肌の小説家としてご活躍されており、遠藤さんはエンターテイメント性の強いホラー作家としてご活躍中です。同じ小説といってもジャンルなどによって様々な小説作法があります。
文学金魚編集部
三浦 みなさんこんにちは。今回は、遠藤徹さんとわたし、三浦俊彦とで対談するということになっていましたが、別々にお話したいと思います。まず最初に、我々は大学教授ですが、二人とも小説家としてデビューした経緯は、大学の仕事とはぜんぜん関係がありません。大学教授として本が売れてから、その流れで小説も書くという方がけっこういらっしゃいますが、我々はそういうクチではなかったんです。遠藤さんはホラー大賞でデビューしましたし、わたしも学術書や評論集より先に小説を出版しました。
また最近では小説家として大学教授になる方が多いですが、我々はそういうタイプでもない。普通に学術的な仕事を認められて大学に採用されて、そのあとで小説家としてデビューしています。学問と小説家の仕事を別にやったという意味で、我々は少数派ではないかと思います。ほぼ純粋な二足のわらじなんです。

こういう共通点を持っている我々なんですが、このセミナーが始まる前に二人で話しをしてみたら、どうも正反対だということがわかりました。わたしはどちらかというと、編集者と喧嘩をしてしまうタイプなんです。遠藤さんは、これは謙遜なのかもしれませんが、自分は弱いので、すぐに編集者の要求に順応してしまうということをおっしゃっていました。
そこでまずは遠藤さんの、編集者とうまく付き合ってコラボレーションを進めてゆくというお話をうかがいたいと思います。それを十分参考にしていただいた後から、わたしの方の、どうして編集者や出版社とのトラブルを経験せざるを得なかったかというお話をしたいと思います。つまり我々から、デビューした後の方が大変なんだよというお話をさせていただきたいと思います。
遠藤 遠藤です。今日はわざわざお越しいただきありがとうございます。わたしは二〇〇三年に『姉飼』というホラー小説で作家としてデビューしました。まずわたしの基本的な書き方がどういうものなのかから、お話していきたいと思います。
みなさんこういうものはご存じでしょうか。美術について詳しい方はご存じかと思いますが、シュルレアリスムの世界で『優美な死骸』(le cadavre exquis)と呼ばれているものです。たとえばこの作品は、イヴ・タンギーとマン・レイ、マックス・モリス、ホアン・ミロのコラボレーションです。恐らく最初にタンギーが下の部分を描いて、マン・レイとマックス・モリス、ホアン・ミロがそれを引き継いで次々に絵を描いていったのだと思います。絵を描き足していっているわけですが、この方法だと一人の人では思いもよらなかった方向に絵が発展していってしまう。それが描き手だけでなく、見る人にも大きな驚きを与えるという手法です。

Nude (1926-27) Cadavre Exquis with Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise, Man Ray (Emmanuel Radnitzky)
こういうふうに、シュルレアリスムでは無意識や偶然性を重視します。わたし小説の書き方は、このシュルレアリスムの手法によく似ているんです。極端に言うと、最初の一行を書きますね。『姉飼』で言うと「ずっと姉が欲しかった。姉を飼うのが夢だった」というのが最初の一行です。これを書いてから、じゃあ姉ってなんだろうと初めて考えるんです。そして次の一行を書いてみる。そういうふうにして、最初の一行から自然発生的に物語が生まれていくというのが、わたしの基本的な書き方です。
ちなみに『姉飼』というタイトルも、国語辞典で適当に漢字を拾っていきました。「姉」とか「豚」、「祭」、「脂」なんかの言葉を拾い、それを紙に書いて線でつないでいくんです。そんなことをしていたら、「姉」と「飼」が結びついた時に、不思議なインパクトがあった。「姉飼」ってなんだろうって、そこで初めて考えるわけです。小説の中に出て来る「脂祭り」もそうです。「脂」と「祭」という単語がくっついたんです。「蚊吸豚」もそうで、「蚊」と「吸」と「豚」がくっついた。ですからほぼ完全に、偶然の出会いを利用して、物語を作っていったんです。
基本的にわたしは、こういう偶然を利用して小説を書いてゆくんですが、石川淳という作家も同じような手法だったようです。石川淳もまず一行書く。それに触発されて二行目、三行目を書いて物語を作っていったんです。わたしの場合、小説の真ん中くらいまで書き進んでから、さて、この物語をどう終わらせようかと考え始めます。その時点で今まで書いてきた小説を読み返して、終末に向けて物語をまとめていくんですね。
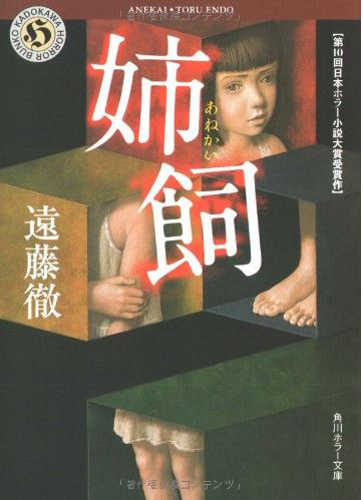
遠藤徹著『姉飼』
平成十五年(二〇〇三年)角川書店刊
この方法では一つのきっかけからどんどん話を拡げていって、最後までほったらかしのままにするというやり方も当然あります。だけどわたしは、一つの物語としてオチをつけるという方向に持っていきます。途中までは無意識的に、自由連想的に書いていって、最後はまとめるという方法です。
こんな書き方で小説をずっと書いてきたわけですが、でもまあだんだんわたしの小説が売れなくなってきたんですね(笑)。で、ある日、某出版社の文庫担当の一番偉い人と担当編集者に、ホテルに呼び出されました。その時、こういう話をされました。「昔わが社には、赤川次郎と森村誠一という二本の柱がありました。赤川次郎は一人で三億冊本を売りました。森村誠一は一億五千冊売りました。この二人で稼いでくれたので、ほかの作家は何をやってもよかった。つまり、バリエーションを出すためにほかの作家の作品も出版していました。ところが今は赤川次郎も森村誠一も本が売れない。こういう状況では、各作家に、売れる本を書くよう、自主努力をしてもらわないと困るんです」、と。

わたしはその時まで、読者を意識して本を書いたことがなかったので、どうすればいいのかわからなかった。その時に編集の方から、まずあらすじを書いてくださいと言われました。わたしの場合は自然発生的に小説が生まれるのに、あらずじを書くよう求められたんです。どうしたものかなぁと悩みましてね。そこでまず、大塚英志さんの『キャラクター小説の作り方』を読んでみたんです。あれを読むと、最初に登場人物のキャラクターを設定して、カードに時と場所とその時に起こった事件を書いてゆく。それをたくさん蓄積して、シャッフルして物語を作れとありました。
わたしはまずこの方法で、三十枚くらいの短い小説を書いてみました。そしたら書けたので、大塚さんの言うような方法でも小説は書けるんだなぁと理解しました。この方法で、『戦争大臣』という三冊本のあらすじを作り始めました。あらすじだけで二百枚くらい書いたかな。それを編集者に送ったんですが、編集者が、ここはこうした方がいいんじゃないかと色々言ってくるんです。たとえば女の子のキャラクター設定とかですね。
わたしとしても忸怩たる思いがないわけではなかったんですが、こういった方法で小説を書くんだから仕方ないなと腹をくくって、編集者に言われるままに内容を直してあらすじを送り続けました。七回くらいあらすじを書き直し、ようやく内容が決まってそれに基づいて書き始めたんです。全部で千二百枚か千三百枚くらいの作品です。
この書き方は、あらすじがあるので、あとは内容を膨らませてゆくだけです。だから書くのは非常に楽ちんです。音楽を聴きながらでも書けるんです。ただ以前のように、次がどう展開してゆくのかわからないということがないですから、ハラハラドキドキ感がまったくない。ただまあ自分でも、小説にはいろんな書き方があるんだなぁということがわかって、それが面白かった。また確かにあらすじに沿って書いているんだけど、書いていくうちに、どうしてもズレてしまう部分もあるわけです。物語は一つの自律性を持っていて、最初の設計図通りにはいかないんです。そういう物語のダイナミズムも感じることができました。
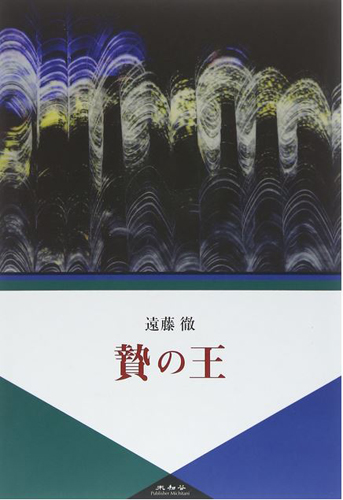
遠藤徹著『贄の王』
平成二十六年(二〇一四年)未知谷刊
こんなふうに、小説の書き方は人によってそれぞれ違うと思います。ある人は本当に思いつくままに書いてゆく、ある人は綿密に調査をして資料を用意し、それに基づいて書いてゆく。ただわたしとしては、どちらが楽しいかというと、やはり先が見えないような書き方の方がワクワクする。書いている時の楽しさ、充実感があります。
ただエンターテイメント小説の世界では、わたしのような書き方では最後にうまく着地できないことがあるので、あらかじめあらすじを決めておくのは、安全な書き方なのかなとは思います。ただそういう作業をするときは、編集者との二人三脚のような仕事になります。好きに書いていいということはありません。マンガ家の制作現場はそういうものだとよく言われます。最初にきちんとストーリーを決め、コマ割りも決めて書いてゆく。エンタメ小説の世界も、そういったマンガの世界に近づいていっているようなところはありますね。
それについては、わたしもいろいろ思うところは当然ありますが、とりあえず編集者の言うことを聞いて、仲良く仕事をしていったという過去があります。でもわたしと違って三浦さんはいろいろ衝突があったということなので、これからそういったお話を、三浦さんから聞かせていただきたいと思います。
三浦 わたしは遠藤さんのように、オーダーメイドの小説は書いたことがありません。好き勝手やってしまう方なんですね。学術書や啓蒙書を書くときも同じです。学術書や啓蒙書の場合は、たいてい出版社の方が、こういう本を書いてくださいと企画を持ち込んでくるんです。「いいですよ」と承諾してその場で企画を詰めて、編集者の方に持ち帰ってもらって社内で了解を取ってもらうんです。で、企画が通ってしまえばもうこっちのものなんですね(笑)。企画が通ればこちらはもう自由に書ける。
たとえば『のぞき学原論』という本があります。この本は元々、日本文学におけるのぞきのパターンをいろいろ分析してくださいという依頼だったんです。出版社の社長さんが編集者といっしょに、わざわざわたしの家まで来て依頼してくださった。それで企画が通ったんですが、わたしは前半部分は依頼通り原稿を書きました。でも後半、というか本の八割くらいは盗撮AVの分析をやってしまった。こういうことをすると当然、難色を示されます。でももう書いちゃったんだからしょうがないですよね(笑)。だから考えてみれば、関係者の方にいろいろご迷惑をかけて来ましたが、一回通った企画については好き勝手に、価値あると自分で信じるものを書くというやり方で本を書いてきました。

三浦俊彦著『のぞき学原論―-The Principles of Peepology-』
平成十九年(二〇〇七年)三五館刊
で、みなさんにお配りした資料なんですが、これは実はわたしのトラブルにかかわる資料なんです。まず朝日新聞に掲載された小説からいきましょう。これは二〇〇〇年正月の紙面です。この頃、わたしはあまりもう小説を書いていませんでした。五年くらい前、一九九五年くらいが一番盛んに小説を書いていた時期かもしれません。
これは朝日新聞の新年特集のために書いたんですが、すでに芥川賞を受賞されていた川上弘美さんと、最近になって直木賞を受賞された黒川博行さんとの競作です。テーマは二〇〇〇年問題でした。コンピュータは下二桁でデータを管理するんですが、それが〇〇(ゼロゼロ)になったら、コンピュータが誤作動してとんでもない混乱が起こるんじゃないかと当時言われていたんです。二〇〇〇年になったとたんに、大惨事が起こるんじゃないかと。編集部の依頼は、それを踏まえて三〇〇〇年問題について書いてくださいというものでした。これはわたしが過去に書いた、数少ないオーダーメイド作品の一つということになりますね。
ところが原稿依頼と同時に記者がこう言ったんです。冗談のような口調でしたが、もし万が一、本当に大惨事が起こったら原稿掲載は中止になります、と。それはそうですね。現実に大惨事が起こった時に、こういうお遊びの企画を紙面に載せるのは、やはりタブーになります。まあそういう了解の下で原稿を書きました。三人の作家の競作ですが、執筆者はみんな自分が一番いいものを書いていると思い込んでいるので、わたしもまたそう思っています。わたしのが断トツだと。それについてはみなさん後でその紙面コピーを読んで判断してください(笑)。

で、わたし以外の二人の作家さんは、未来の話を書いておられます。だけどお題になった、二〇〇〇年問題、三〇〇〇年問題については書いておられないんですね。単に未来の話を書いてる。お題を守ったのはわたしだけなんです。ただ考えてみると、編集部から与えられたお題を守らないというのが、小説家のスタンスでもあります。そういう意味で、ここではわたしが一番小説家らしくなかったのかもしれない。学者的に書いてしまったのかもしれません(笑)。
実はこの三年前、一九九七年にも毎日新聞から新年のショートショートを書いてくださいという依頼がありました。ところが書いて出したらボツになってしまった。ボツというより、記者から「なんとかなりませんか」と。わたしは「なんともなりません。自信作ですから」と返答したので、結局通らずにボツになり、原稿料だけ振り込まれた。どうしてかと言うと、人質が殺される話だったんです。
当時、十二月の後半になってから、ペルー日本大使公邸の人質事件が起こった。わたしのショートショートは学校でテロリストが暴れるという話で、ぜんぜん内容が違うんですが、これはマズイということになってしまった。二〇〇〇年問題の小説の時も、また同じことが起こるんじゃないかと心配したんですが、幸いなことに何事も起こらず掲載されました。毎日新聞に載らなかった作品は「心霊派革命」というタイトルで、もう品切れになって入手しにくいですが、岩波書店から出た『たましいの生まれかた』という短編集に収録してあります。

三浦俊彦著『たましいの生まれかた』
平成十年(一九九八年)岩波書店刊
この逆に、わたしの方から掲載を打ち切ったというケースもあります。お配りした『誤読の解放区』というエッセイで、これは一九九五年に若者向けの『ez』という雑誌の創刊号から始まった連載でした。若い編集者が毎回お題を持ち込んでそれにわたしが応ずる方式ですが、どうも彼はわたしのことを性的に過激なことを書く作家だと期待していたようなんです。連載二回目はピアシングでした。このテーマでの書き方に、編集者はどうもがっかりしたらしい。「もっと煽ってください、イマドキこの内容では」と言うんですね。「どうもセックスを抑制するようで、景気がよくありません」と。
しかしわたしは当時女子大の助教授で、ガールズトークをしょっちゅう耳にしていましたから、それをフィールドワークして書いたんです。だからリアリティという意味でも自信があった。小説ならともかくエッセイでウソは書けない。そこで編集者と喧嘩のようになってしまった。女性誌と同じようにセックスセックスと、性的に解放されようというスタンスばかり求めるなら、連載をやめると言って一方的にやめてしまったんです。このあとわたしのページは毎回広告欄になっていました(笑)。今思うと非常に若い編集者で、わたしを見込んで張り切って企画を立てていた様子でしたから、ずいぶん気の毒なことをしたと思います。が、そういう通り一遍の、マスコミ的価値観に染まらなければ安心できない、雑誌が売れないという思い込みはどうも我慢ならなかったんです。

三浦俊彦著『下半身の論理学』
平成二十六年(二〇一四年)青土刊
そういうわけで、いろいろトラブルはありました。最大のトラブルでは裁判になっちゃったケースもあります。詳しくお話している時間はありませんが、裁判のせいで出版できなくなった小説があります。それが実は、今文学金魚で連載している『偏態パズル』という小説です。このコンセプトの小説を依頼してくれた出版社とトラブルになったんです。そのトラブル自体は小説とは関係ないんですが、別件の出版権がらみで訴えられて、民事裁判の被告になってしまった。それでお蔵入りになってしまった原稿に加筆修正しながら、いま、なんでもやらせてくれる文学金魚で公開しているわけです。
せっかく今日来ていただいたので、ちょっとだけ秘密を漏らしてしまいますと、『偏態パズル』の第××××××××××××は、二十年以上前に×××××××××××××××××××××××です。当時×××××××××××××××××××××××られて、×××××××××××××××××らしくて、××××××××だった(笑)。そういう感じで、わたしはかなり出版社とか編集者とトラブルを経験しています。日常生活ではほとんど喧嘩しないんですが、こと執筆活動になると、けっこうトラブルが多かったかなぁという気がします。
今日集まっていただいたみなさんの中にも、小説家としてデビューしたいとお考えになっている方がいらっしゃると思います。だけど本当に好きなものを書きたい、書き続けたいと思ったら、デビューする前よりも、デビューした後の方が大変です。それがわたしの実感です。みなさんもよくお考えになって、それぞれの道を進んでいただければと思います。短い時間ですが、耳を傾けていただきありがとうございました。
(2016/06/18)
 縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。
■ 遠藤徹さんの本 ■
■ 三浦俊彦さんの本 ■
■ 予測できない天災に備えておきませうね ■




